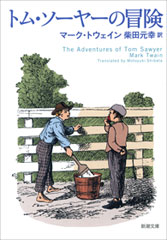書評
2012年7月号掲載
そういう大人たちのためにこそ
――マーク・トウェイン著/柴田元幸訳『トム・ソーヤーの冒険』(新潮文庫)
対象書籍名:『トム・ソーヤーの冒険』(新潮文庫)
対象著者:マーク・トウェイン著/柴田元幸訳
対象書籍ISBN:978-4-10-210611-2
柴田元幸訳『トム・ソーヤーの冒険』を「モンキービジネス」誌上で読んだのは去年の秋のことで、あまりの面白さにうひゃうひゃ言いながら一気読みしたことを覚えている。
まず驚いたのは、それが一世紀半ちかい時間のギャップをまるきり感じさせない“今”の面白さだ、ということだ。子供という興味ぶかい生き物の生態がどこまでもリアルに描かれていて、まるで自分の子供時代を見ているような「あるある」感だった。
けれどももっと新鮮だったのは、その語り口だ。新しい『トム・ソーヤーの冒険』には、大人が子供の目線に合わせて身を屈めて話しかけるような「児童文学くささ」がみじんもなかった。かわりにあるのは、真顔で面白いことを言ったあと片眉をひこひこ動かしてみせる剽軽(ひょうきん)な小父さんの語りだ。まるでマーク・トウェインその人の顔がありありと見えてくるような。
あらためて読み返してみると、まずもって気がつくのは、地の文を意図的にかなり硬めに訳してあることだ。〈そこで(トムは)、整理の済んだ資産(しさん)をポケットに戻し、買収(ばいしゅう)案は放棄した。と、この暗黒なる、望みなき瞬間、ひとつの霊感(れいかん)がトムを見舞った――偉大にして壮麗(そうれい)と言うほかない霊感が!〉〈やがてプードル犬が一匹、ふらふら浮かぬ様子で迷い込んできた。夏の閑(のど)かさ、静けさに犬は倦怠(けんたい)を覚え、囚(とら)われの身を憂(うれ)い、変化を希(こいねが)って溜息をついた。〉これはほんの一例だけれど、「放棄」「暗黒」「壮麗」「倦怠」といった重厚な漢語が腕白小僧や犬の心情を描写するのに使われていて、その落差がえも言われぬ可笑しみを生みだしている。
それに、ところどころ「あえての直訳」がとても効果的に使われている。たとえば有名な塀塗りのシーンで、トムが友人の一人を騙して仕事を肩代わりさせたあと、次は誰をカモにしようかと企むくだり。〈……脚をぶらぶらさせてリンゴを齧りながら、無垢(むく)な者たちをさらに虐殺(ぎゃくさつ)する案を練った。〉原文の the slaughter は、穏当な日本語にするなら「陥れる」とでもするところを、あえて「虐殺」と直訳を当てて、原文のフックをそのまま伝えている。(個人的にいちばんぐっときたのは girded up his loins を〈褌(ふんどし)を締めてかかり〉としてあるところだ。“褌”のような和の言葉はなるべく使わないのが定石だけれど、たしかにこっちのほうがずっと原文の可笑しみが出るし、何より実感がこもっている。ただしこれは良い子が真似するには危険な技だ。)
地の文がそんなふうに硬めに作りこんであるのとは対照的に、会話の部分は一転して、今の子供たちの生の言葉をそのまま写しとったような、自然でアップテンポな文体で、読んでいると、こちらまで子供に戻って一緒にやりとりに加わっているような気分になる。〈「いいや、何でもないよ」「何でもあるわよ」「何でもないって。見ても仕方ないよ」「仕方あるわよ、見たいのよ。ねえ、見せてよ」「言いつける気だろ」「言いつけない。嘘(うそ)ついたら針千本(はりせんぼん)飲ませていいから」〉〈「どこで捕(つか)まえた?」「森の中」「何と取っ替えてくれる?」「さあなあ。売る気はないよ」「分かったよ。どっちみちすごく小さいダニだし」「他人(ひと)のダニはいくらでも貶(けな)せるよな。俺はこれで満足してるんだ。このダニで俺は十分だよ」「ふん、ダニなんてどっさりいるからな。俺だってその気になりゃいくらでも捕(つか)まえられるさ」「じゃあ何で捕まえない? できないって分かってるからだろ。こいつはまだはしりのダニだよ。今年初めて見たよ」「なあハック――代わりに俺の歯やるよ」〉(ああ、もっと引用できないのが残念だ。ことにトムとハックのやり取りは、永遠に続いてほしいと思うくらいすばらしい。)
かくして読み手は、時に眉毛ひこひこ小父さんたる作者と一緒に遠い子供時代を郷愁とともに眺め、時に自分がそのまま子供になり、そうやって大人と子供のあいだを何度も行き来することになる。それは、自分の中に大人の部分と子供の部分と、両方が生きているのだと気づかされるような、不思議で奥深い読書体験だ。
「ああトム・ソーヤーね、それならもう子供のころ読んだよ」という人がいたら(たいていの人がそうだろう)、そういう大人たちのためにこそ、この新しい『トム・ソーヤーの冒険』はあるのだと思う。
(きしもと・さちこ 翻訳家)