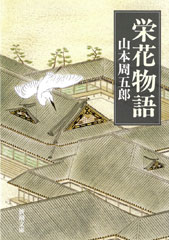書評
2013年8月号掲載
山本周五郎と私
「信じる」ことの力
対象書籍名: 山本周五郎長篇小説全集第6巻『栄花物語』
対象著者:山本周五郎
対象書籍ISBN:978-4-10-113421-5
冒頭で月食が話題になる。自分にこのエッセイが依頼された理由はそれに尽きる。近頃私は「江戸時代の天文学者について書いた人」と見られている。他にも色々書いているのだが世評ではそうなっている。そういう意味で私は、『栄花物語』の作中でいわれのない世評にまみれる田沼意次に共感する。
というのはもちろん冗談だが、本作を読んで田沼に同情しない人はいないだろう。そのくせ、現代の政治家や官僚に対しては、当時の世人が田沼にしたようにする。政治経済という奇怪きわまりないしろものは、不可解であるということ自体がストレスになる。自分の生活を左右するにもかかわらず、よくわからない。わからないことに腹が立つ。だから、わかりやすく批判できる人物がいると安心する。わからない鬱憤をぶつけることができるからである。
田沼が推進する経済策が、さして詳述されないのも、そのせいだろうか。小難しい理屈は読みたくないという、読者の要求を想像してしまう。
そしてこの構造は、山本周五郎作品には珍しいのかもしれない。無名の人々の輝きと悲愴を描くにあたって、田沼のような人物がいると、意味合いが違ってくる。田沼への同情は、ひるがえって無名の人々の無知を咎め、自業自得であるとの結論を招くからである。
四人の主人公の一人である信二郎が、きわめて皮肉屋で退廃的な気分を醸し出しているのは、そういう理由があるからだろう。
彼は田沼批判の急先鋒である。しかも金で雇われてやっている。そんな自分を嫌悪しつつ、面白がってもいる。田沼本人から協力を乞われても、この信二郎という男は世直しのための千載一遇の好機と決して思わない。ぐずぐずと自分のちっぽけな正義感を盾にして逃げる。
そのくせ田沼に好意を抱き、対立する白河(松平定信)派から守ろうとする。が、結局、自分の満足以上のことはしない。ちょっとばかり助けただけで、あとは自分の目の前にある満足の方を優先してしまう。そうして世を拗ねた生活を繰り返す。
なんと人間的であることか。
孔子は、こういう人物を小人と呼んで退け、田沼のような人物を君子として尊ぶ。だが現実にそうはいかない。人がそう簡単に無私になれるものか。むしろ無私になりきれないところに人間がいる。運命の奔流に巻き込まれて行き詰まり、救いを求めて水面から必死に顔を出すが、最後には水底に沈んで消えていくしかない、とことん生身の小人たち。
こうした人々こそ、愛さねばならない。人が人らしく生きようとすることを誰が咎められるのか。本作を読むと、強くそう訴えられている気がする。事実、信二郎の情事と金稼ぎから始まるこの物語の冒頭で、私はあっという間に信二郎が好きになった。彼が田沼を評価しながら、自己評価の低さ(小人としての自覚)ゆえ君子たる人物を避けてしまう気分が、わかってしまうのである。
ならばなぜ本作では田沼に紙数が割かれるのか。そもそもなぜ田沼の経済改革が題材として選ばれたのか。田沼もまた、一個の小人であるとしたいからか。過ぎたるは猶及ばざるがごとしで、改革路線を盲進した結果、自分ではなく、かけがえのない息子が死ぬ。改革も水泡に帰す。だがそれだけでは、上の者を引きずり下ろして喜ぶ卑屈な作品になるし、本作は悲劇ではあっても、卑しさとは無縁である。
まっとうさが周囲の迷惑になる。作中でたびたびそのようなフレーズが繰り返される。田沼に信二郎とはまた別の関わり方をし、田沼の鏡写しのように死んでいくのが、保之助である。田沼と信二郎の二人の運命に翻弄された善人である一方で、その高潔さが逆に二人を翻弄する。明確な敵意を持つ相手よりも、好意を抱く相手の方をおかしくさせていってしまう様子もまた、ひどく人間的で、清々しくさえある。
田沼と保之助は、心中へとひた走る。一方は改革との、他方は理想の女との。本作はこれらを等価値に扱う。単に、人情が積み重なったところに政治がある、というようなことを言っているのではない。たとえ人情がピラミッドのように積み重なったとしても、その頂点でいきなり人情を超えた高潔な何かが出現するものか。人はあくまで人である。田沼の改革への執念は、保之助が理想の女へ傾倒するのと何も変わらない。描かれるべきは「人間田沼」であり、雲上の君子ではない。雲上など人間と関係ない――と言わんばかりの徹底した小人描写が、おそろしく生々しいのである。
敵役の白河侯が、立派ではあるが無機質かつ非人間的に描かれるのは、事実、この作品において彼は人間ではないからだろう。抽象的な伝統墨守を目的としており、現実的な利益は視野の外だ。彼を御輿に担いで、利益をむさぼろうとする人々こそ人間なのだろうが、そこにもさして紙数は割かれない。
現代にも伝わる有名な落首に、
田や沼やよごれた御世を改めて 清くぞすめる白河の水
白河の清きに魚の住みかねて もとの濁りの田沼恋しき
というのがある。当時の人々にとって田沼と白河の二人は、一対だった。だが「清き」誇りの化身たる白河の存在は、本作であたかも天災のように描かれるばかりで、田沼と拮抗するもう一人の主人公としての地位は決して与えられないのだ。
もし、白河が主人公であったなら、題名は『栄花物語』ではなく『大鏡』になっていたかもしれない。どちらも平安時代の歴史書だが、視点がまったく違う。『栄花物語』は女性による大著で、日本で物語と歴史を融合させた初めての例として知られる。同時代に『枕草子』と『源氏物語』が流布しており、影響を与えている。
すでに評論分野で語られているに決まっていることを、くどくど書くべきではないが、これはもちろん、ただ語呂が良いから題名を拝借した、という次元の話ではない。
千年前の文学的革命であった『栄花物語』において、最初の章は「月の宴」である。もちろん主要人物の大半は、藤原氏の血統だ。で、本作『栄花物語』では最初の章は「月の盃」。藤代と藤扇が、その名ゆえに「凶」と断じられるくだりがある。
他にもこまごまと相似はあるが、政治経済の話題が深く関わるこの題材にもかかわらず、分析と批判を主軸とする『大鏡』を題名に採らなかった、ということが私には驚異なのである。田沼と白河の政策談義ではない。むしろ小人たちの情念を描き、歴史物語としての血脈を『栄花物語』に求めた。その一点に山本周五郎作品としての本作の神髄があるのだと思われてならない。
この作品を担当した者として主張させてもらえれば、山本周五郎作品群の中でもあまりハイライトが当たっていない(気がする)本作に、小人への愛情を土台に、「歴史」を「物語」として世人に広く届けようとした、山本周五郎の心血を感ずるのである。
田沼、信二郎、保之助の三人の主人公達が、人間らしさゆえに転落していく一方で、生まれてから死ぬまで小人であり続けたのが、四人目の主人公たる千吉である。もし題名が『大鏡』であったなら、白河ではなく千吉こそ人間として描かれず、一揆も天災のように扱われていただろう。千吉は、構造的な貧困ゆえに犯罪者となり、やがてはテロリストへ変貌していく。ごくふつうの一般市民、すなわち生粋の小人だ。
前述の三人に比べ、千吉は経済的には転落ではなく改善されていく。だが倫理の面で、悪の側へ呑み込まれるほかなく、その良心の爆発を、とことん政治的に利用される。
作中で、彼だけが生身の女に翻弄されずに済むのは、彼こそ最も清潔な人であるからだろう。社会の底辺で踏みにじられ、愛する家族を捨て、殺人の罪に汚れていく。にもかかわらず、その無知、その無名ゆえのしぶとさに、政治的ではない、人間の正義がみなぎっているのである。本作を悲劇へと突き進ませる本当の活力は、千吉によって芽生えている。
悲劇は絶望を訴えない。絶望的な状況下においても失われない希望を訴えるのが悲劇である。田沼は改革を、保之助は理想の女を、信二郎は自由を、それぞれの希望と信じた。全身全霊で、ゆいいつ信じられるものとして信じたのである。
千吉は何を信じたのだろう。彼は、意識を奮い立たせて、混沌とする世の中で必死に信じられるものを探したのではない。最初からあった、家族や友愛を、最後まで愚直に信じ続けたのである。その千吉を死から救えなかった信二郎は、さらに保之助の訃報を経て、そこで初めて自分自身と決別するため、ぬかるみを歩む。不安を抱く者に迫る足音という作中のフレーズが、終盤では明記されていないものの、自然と読者が連想するものとして、ここで効いてくる。
なんと見事なラストシーンか。
田沼と白河ではなく、田沼と千吉の物語として宝暦天明の時代を書き上げ、保之助と信二郎の二人の物語をもって歴史を『栄花物語』へと昇華させた山本周五郎の筆に、どうにもこうにも、じわじわと目頭が熱くなってしまうのである。
(うぶかた・とう 作家)