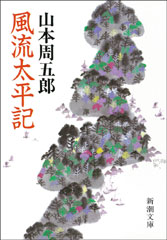書評
2013年9月号掲載
山本周五郎と私
最大多数の庶民に
対象書籍名: 山本周五郎長篇小説全集第10巻『風流太平記』
対象著者:山本周五郎
対象書籍ISBN:978-4-10-113444-4
常に庶民の中にあって弱い者や虐(しいた)げられた者の側に立ち、生きることの意味を問いつづけた作家というイメージが強い。
ところが『風流太平記』は、こうした作風とは一線を画した娯楽性の強い、まるで往年の東映時代劇映画を活字化したような軽妙な作品である。
物語は次の一文から始まる。
「九月中旬のある晴れた日の午後。
芝新網にある紀州家の浜屋敷の門前へ、一人の旅装の若者が来て立った」
この若者こそ主人公。花田三兄弟の末弟万三郎で、長崎奉行所につとめていたが、紀州藩甲野家に養子に行った次兄休之助に、急に江戸に呼びもどされたのだった。
ところが浜屋敷の老番士の話では、甲野家は前の晩に自火を出し、家族全員が焼け死んだという。
「いったい、何があったのだ」
当惑する万三郎のもとに、休之助の妻の妹であるつなが訪ねてきて、休之助はある陰謀の真相をあばこうとしたために襲われたのだと伝える。
そして陰謀の証拠の品だという包みを預けて立ち去るが、その後何の音沙汰もない。やがて自分こそがつなだと名乗る妖艶(ようえん)な娘が現われ、万三郎が江戸に来た理由をいろいろと聞き出そうとする。
こうした謎めいた幕開きから、紀州公の大陰謀を未然に防ごうとする花田三兄弟と、少年半次たちの活躍が始まる。
しかも万三郎をめぐるつなとかよ(初めつなと名乗って現われた妖艶な娘)との恋の鞘当てや、半次とおちづの幼い恋が描き込まれ、物語は大団円に向かって息もつかせず展開する。
大陰謀とは何か、彼らの恋の結末はどうなるのか。作者は二本の興味の糸を巧みにあやつりながら、読者を物語の楽しみへと誘(いざな)うのである。
それにしても周五郎は、どうしてこうした異色の作品を手がけたのだろうか? その謎を解く鍵は、新聞連載開始にあたって記した次の一文にある。
「歴史のなかにはヤミからヤミへ抹殺された出来事が多い、この物語もその一つではあるが、その“事実”よりも内容のケタ外れなところを書きたい、科学の進歩は人間の空想や夢の極度にまで達したがそれゆえにこそ空想や夢が必要だと思う。――時代は徳川氏の末期、御三家の一である某藩がイスパニアと結んで政権を顛覆しようとしたが、危ぶく摘発され、大事に至らなかった。そのかげには旗本三人兄弟と二人の女性の命をかけた奔走があった、私は考証や傍証をぬきにしてこの五人の活躍を書きたいと思っている」
この中で周五郎は三つの要点を示しているが、その意味を彼が昭和三十六年五月に中央大学会館でおこなった『歴史と文学』という講演を手がかりに探ってみたい。
第一点、歴史のなかにはヤミからヤミへ抹殺された出来事が多いという認識は、作者の歴史に対する基本的な態度である。
講演の中でも戦時中の大本営発表を例に上げ、もし日本が戦争に勝っていたなら、あの嘘やデッチアゲに現実的な裏付けを添加し、歴史として残していただろうと語っている。
つまり歴史は権力側の都合によって修正され、改ざんされ、抹殺され、ねつ造されるもので、一般に信じられているほど当てにはならない。だから文学の出番があるというのである。
第二点、事実よりも内容のケタ外れなところを書きたいとは、「歴史ではできないけれども、文学の世界であるならば可能である」という講演での発言に通じている。
歴史の定説などは空虚なものだが、当時の人々の事情を丹念に調べていけば、おのずと浮かび上がる真実があると、周五郎は信じていた。
『樅ノ木は残った』などはそうした手法で書かれたものだが、この作品ではこれをもう一歩おし進め、作家的直感による大胆な推測を元にした構想に取り組んでいる。
今日のファンタジーノベルに近いもので、本人が空想と夢について語っているのも、そうした方法のことを指しているのだろう。
ケタ外れの内容とは、紀州徳川家がイスパニア(スペイン)と結んで幕府転覆をはかったが、フランス革命の勃発(ぼっぱつ)によってイスパニアの支援が得られなくなり、計画が失敗したというものである。
これはまさにケタ外れだが、周五郎の手元にはこの構想の基礎となる何らかの資料があったものと思われる。(イスパニアは突飛だが、オランダなら可能性は充分にある)
そしてこの構想こそ鎖国史観に風穴をあけ、もうひとつの江戸時代史を提示するものであったはずだが、残念ながら作者はそこまで書ききれなかった。
そう想像する根拠は、この大陰謀が尻切れトンボのように片付けられていることと、連載が二百十二回という中途半端な回数で終っていることである。
書ききれなかった理由は、作者が書いている途中でこの構想に興味を失ったか、基礎となる資料を公表することがはばかられる事態がおこったか、他の仕事が忙しくなったために時間が取れなくなったからだと思われる。
この大陰謀にかわって物語の本流となったのが、第三点。旗本三兄弟と二人の女性の命をかけた奔走である。
これには花田三兄弟の立場や性格のちがいによる対立や相克、万三郎をめぐるつなとかよとの女の戦いがからみ、物語は波乱万丈、軽妙洒脱(けいみょうしゃだつ)な展開をみせ、ページをめくる手を止められない。
「周五郎さん、楽しんでやがるな」
読みながら思わずニヤリとする場面も多く、ドラマは快調に進んでいく。
三兄弟の長兄である花田徹之助は、八百五十石の旗本の家をつぎ、大目付の書役(かきやく)をつとめている。視野が広く思慮深い男で、大陰謀に立ち向かうチームの指揮をとっている。
次兄で甲野家の婿養子となった休之助は、紀州公の大陰謀に気付いたために家に放火され、養父と妻を犠牲にしている。それでも打ちひしがれることなく、目的のためなら犠牲をいとわない厳格さをもって陰謀に立ち向かう。
三男坊の万三郎は吉岡家の養子になり、親類の娘と結婚することになっていたが、娘が病気で死んだ上に、長崎勤番を命じられて現地に赴任(ふにん)していた。それに同情した次兄の休之助が、義妹のつなを妻にするように内々にはからっていた。
腕もたつし気性もおおらかで、敵に対しても情をかける好漢だが、女には奥手で初心(うぶ)で、つなとかよの間で翻弄(ほんろう)されることになる。
この二人の女の造形が際立っている。つなは身分ある武士の娘で、誇り高く意地っ張りで、万三郎の欠点ばかりを目ざとく見つけて責め立てる。
一方のかよはつなの親戚で、甲野家にしばらく居候(いそうろう)しているうちに休之助から万三郎のことを聞き、会う前から恋心をつのらせている。妖艶で行動的で、初めは敵役(かたきやく)として現われるが、万三郎との付き合いが深まるうちに身方になり、陰謀阻止のために働くようになる。
かよはライバルのつなに、次のような痛烈な言葉を投げかける。
「あなたは万三郎さまを訓戒したり叱(しか)ったり、やりこめたりすることはできるでしょう、でも愛してあげることはできやしないわ、愛するというのは、相手の悪いところも欠点もすべてそのままうけいれることよ、あなたにそれができて、つなさん」
周五郎が追い求めた真の愛とは何かというテーマは、万三郎をめぐるかよとつなの争いの中にもしっかりと描き込まれているのである。
こうした人間模様に彩(いろどり)をそえるのが、下町の浮浪児ながら万三郎らに協力することになった半次とおちづである。
二人はまだ十三、四歳。互いに助け合い、己の手で人生を切り開いていこうとするうちに、ほのかな恋心を抱くようになる。二人にそそぐ周五郎の目は慈愛に満ちていて、互いを初めて異性と意識して戸惑うシーンは出色の出来である。
この作品が発表された昭和二十八年には、女性が戦前の家父長制的なくびきから解き放たれて、新しい生き方を模索(もさく)し始めていた。
周五郎はつなを古いがしっかり者の、かよを自由で開放的な、ちづを新しい時代を切り開いていく行動的な、女性の代表として造形したのだろう。
この頃周五郎は、大衆小説の新しい可能性をさぐるべく、試行錯誤(さくご)をくり返していた。
前記の講演において「文学というものは、最大多数の庶民につかえるものでなければならない、と思うからでございます」と語っているが、この作品ではそれを体現するためにファンタジーノベル的な手法をもちいて、小説の面白さと読みやすさを追求している。
『風流太平記』は周五郎の作品群の主流からはずれ、文学的な評価はそれほど高くないようだが、注目すべきは最大多数の庶民につかえるために、あえてこうした作風に挑んだ作者の心意気と努力ではないだろうか。
(あべ・りゅうたろう 作家)