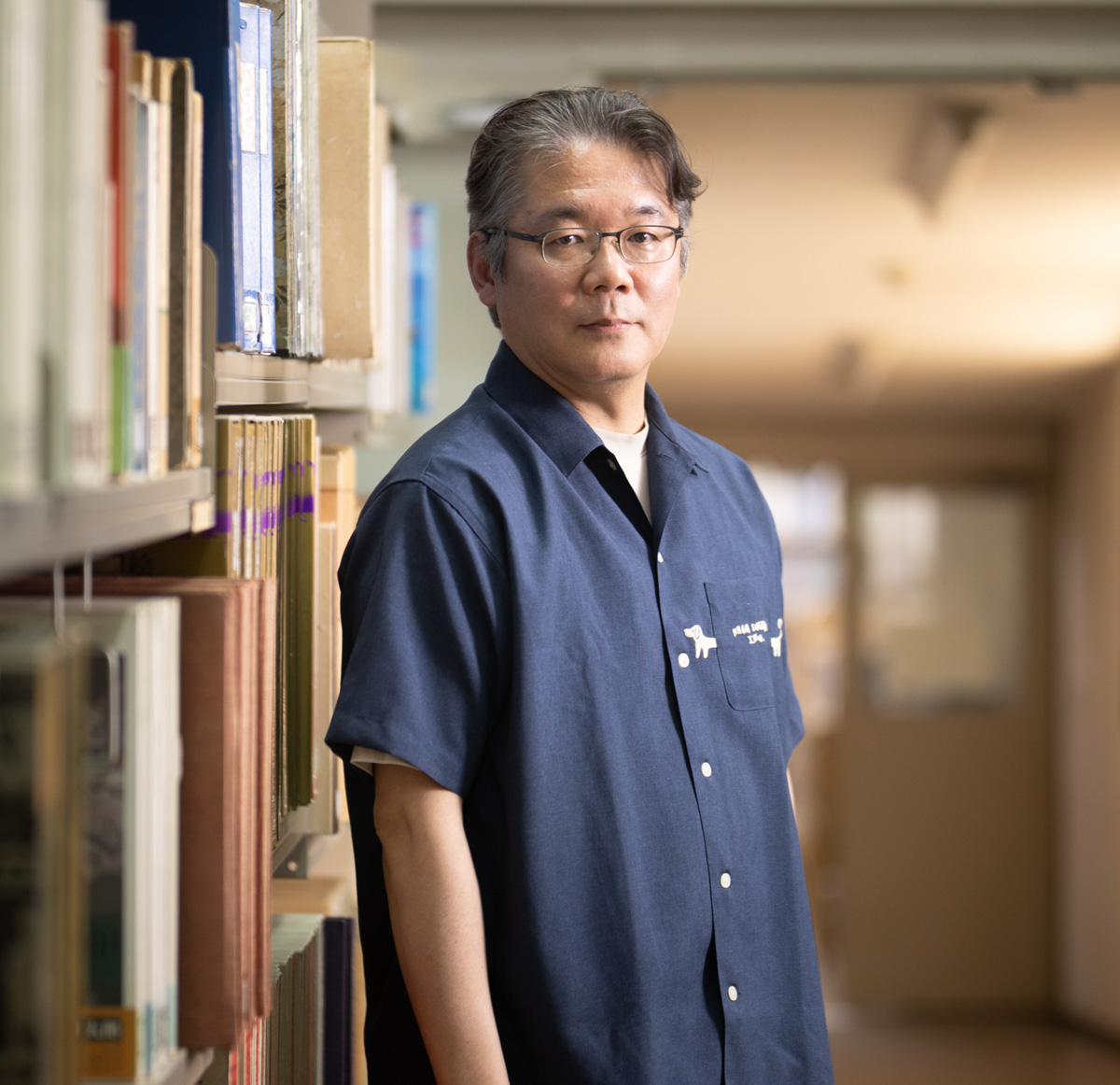インタビュー
2014年2月号掲載
刊行記念インタビュー
「単品で勝負!」だらけの贅沢連作集
『首折り男のための協奏曲』
趣向の違う話がグラデーションのようにつながっていく唯一無二の連作集『首折り男のための協奏曲』。収録された全七編は単品として勝負するために書かれたものばかりで、出し惜しみすることなく「ネタ」が詰め込まれております。依頼方法から「タイトル」のことまで、いろいろな裏話をお伺いしました。
対象書籍名:『首折り男のための協奏曲』
対象著者:伊坂幸太郎
対象書籍ISBN:978-4-10-125031-1

首折り男の周辺(二〇〇八年)
これは、デビューの時からの担当者が、「Story Seller」という雑誌を作る! と熱く言ってくれて、そのために書いたんですよね。こういう、複数のパートが絡み合うというパターンは何度かほかの作品でもやっているので、自分では慣れもあるから、書いた頃はあんまり自信がなくて、読み返したくなかったんですが、いま読み返すと、良くできていますよね(笑)。ただ長い感じがしていたので、単行本に収録するにあたり短くしました。骨格だけ残す感じで。
そうそうこの中で、「大人になっても人生はつらい?」という台詞が出てくるんですよね。これは映画『レオン』の引用で、一応引用と分かるようにしたつもりだったんですが、僕のオリジナルな台詞だと思われることもあるみたいで。そういう意味では、『砂漠』で引用した、サン=テグジュペリの言葉「人間にとって最大の贅沢とは~」を僕の言葉として注目してくれたり、『終末のフール』の、「明日死ぬとしたら、生き方が~」というのもゲバラの台詞だったりしたんですけど、それは本当に僕の書き方が不親切だったからで、オリジナルだと誤解させてしまって、本当に申し訳ないんですよね。引用って難しいです。
この短編はまったくプロットも立てずに、一直線に書いていったので、最後の一行もたまたま、ラストシーンを書いている時に出てきた感じで、つながって少しほっとしたのを覚えています。
濡れ衣の話(二〇一〇年)
「山本周五郎賞作家特集」のために書いたんです。短編を書くのは本当に苦手なんですけど、新潮社はデビューした版元でホームグラウンドの気持ちが勝手にあるので、できれば年に一回は短編を書きたいとも思っていまして。
僕の中では、モノローグって地の文を書かないので比較的、エネルギーが少なくて済むんですね。だから何となく、ずるをしているような気になっちゃうので、いつもはなるべくモノローグで書かない、という思いもあるんですけど、この時は本当に時間的に余裕がなくて、だから、モノローグで書くことにして、とはいってもそれだけじゃつまらないので、面白い構造を作れないかなといろいろ考えた記憶があります。第一稿はもう少しシンプルだったんですけど、担当編集者に、「もうひとひねり、ほしい」と言われて、改稿してたら、タイムパラドックスとか変な方向になっちゃったんですよね(笑)。
僕の舟(二〇一一年)
「新潮社で年に一回短編を書きましょう」シリーズです(笑)。担当者が仙台に来まして、どの特集に挑戦したいですかと蕎麦を食べながら言ってきたんですよね。「ミステリー」「山本賞受賞作家」「最後の恋」の三つだったかな。それで、一番書いたことのないのが「恋愛もの」だったので、「じゃあ、それで」と。
タイトルだけ先に決めたんです。元素記号の語呂合わせですけど、「僕の舟」って勇ましくていいなあ、と。それで編集者と何度か打ち合わせをして、元素記号をスマホでどんどん調べて(笑)、何とか作りました。
作中に六十年代の銀座が出てきますが、雰囲気をつかむために、当時どういう服を着ていたのかと母に訊ねたんですよね。「植木等さんの映画を観れば判るわよ」とアドバイスを受けたので、DVDボックスを探して手に入れたんですけど(笑)、書き上げるまでに観ることはできませんでした。当時の広告の資料とか、そういうのが役に立ちましたね。
人間らしく(二〇一三年)
これは文芸誌「新潮」に書いた短編です。純文学が好きだった僕からすると、「新潮」は畏れ多い文芸誌、という感じで、書いたらいけないんじゃないかな、と悩んだんですけど、「新潮」に載りたい、という思いも捨てきれず(笑)。
このアイディアは、実生活で思いついたものでして。当時、家でクワガタをひとつのケースの中に複数飼育するという「多頭飼い」に挑戦していたんですね。で、クワガタ同士がかなり、えげつない喧嘩をしているのを見て、いろいろ考えさせられまして(笑)。そのことを人間の暴力性と関連させて、構造を工夫して描くと面白いかな、と。ただ一つ困ったのは、新潮社の雑誌「yom yom」からすでに依頼があって、そっちの短編で、使おうと思っていたアイディアだったんですよ。だけど、何となくこれは、「新潮」に書くほうが面白いんじゃないかと思って、結局、そうすることにしたんです。
なかなか物語の導入がうまくできなくて、試行錯誤した結果、黒澤を登場させることにしました。「新潮」に書くのに、黒澤を出したのが正解だったのかどうか、それは今もよく分からなくて。ただ、依頼人が相談してくる場所をどこにしようかと考えて、探偵事務所や喫茶店ではなく、釣り堀にしたのは結構、良かったんじゃないかと思っています。息子と釣り堀に行ったから閃いただけなんですけど(笑)。「釣り堀」シリーズ第一弾です。まだ、二編しかありませんが(笑)。
作中で、クワガタを飼っている小説家が、戦争について話をするシーンがあって、ただ、そういうたぐいのことを書くと、「政治的」「説教臭い」と言われるのは過去の経験上分かっているので、この単行本に収録する時にごっそり削ろうと思ったんです。ただ、ここで書いていることって、政治的でも説教でもなく、そんなにたいそうなものでもないので(笑)、残しておこうかと。もちろん、これは僕の考えと百%イコールではなく、作中の作家の主張には、僕自身が反論できるくらいなので、ぴったり一致はしないと思ってもらえると助かります。
月曜日から逃げろ(二〇一三年)
「yom yom」に書いた短編です。「人間らしく」でアイディアを使ってしまったので、書くべきアイディアがゼロ! という状態で、〆切がどんどん近づいてくるという危機的状況に陥ったんです。悩んだ結果、昔から長編用にあたためていた、ある仕掛けを使うことに決めました。これは、『アヒルと鴨のコインロッカー』を書いた後、東京創元社の担当者と、「こういう仕掛けは前例がないんじゃないか」という話で盛り上がって、長編にしようと数年悩んでいたものでして。悩んでいる間に、同じ構造のミステリーが発表されがっくり来たり、結局プロットが作れなかったりして。自分で言うのも何ですけどこれでストーリー作るのはかなり大変なんですよ(笑)。別のアイディアが浮かんだので、東京創元社の長編は『夜の国のクーパー』になるんですが。
とにかく、その仕掛けを使うしかない、と東京創元社の担当者にメールして、「短編で使おうと思ってるけどいいですか」と訊ねたら、「いいですけど、あれって〆切が迫ってる時に、挑戦するネタなんですか」という返事があったりして。でも、短編ならどうにかなるんじゃないか、と思ったんですよね。
相談役の話(二〇一〇年)
初めて書いた「怪談」です。仙台にある荒蝦夷(あらえみし)という出版社から依頼を受けて書きました。しつこいですが基本的に短編を書くのはつらいので(笑)、引き受けないようにと考えているんですが、荒蝦夷さんとは昔からの付き合いなので。
怪談をまったく知らないので、まずはそのジャンルの本を読んでみようと思ったんですね。『怪談実話系』というアンソロジーを買って読んでみまして。一本目が京極夏彦さんの「成人」なんですが、これが、すごいんですよ。余韻もあって。「これはノーベル怪談賞でしょう!」と叫びたくなるほどの、いや叫ばなかったですけど(笑)、それくらいの傑作で、「ちょっと太刀打ちできない」と思ったんですけど、何か書かないといけなくて。そうしたらたまたまタクシーの運転手さんが山家清兵衛(やんべせいべえ)さんの呪いの話を教えてくれて。市街地の「FORUS」といえば僕たちの学生時代は、若者の中心地だったので、その屋上に、山家清兵衛さんが祀られているなんて、仙台に二十年以上住んでいる僕も知らず、かなり興奮しました。荒蝦夷の編集者さんとお参りに行って、それで書いたんですね。雑誌掲載時は黒澤は出てこなくて実話っぽくしていたんですけど、今回、改稿して、「人間らしく」と重ねてみました。
合コンの話(二〇〇九年)
「首折り男の周辺」と同じく、デビュー時からの担当者が、「Story Seller」の二冊目を作るというので、書いたものです。とにかくこの頃は、普通のエンタメ、起承転結があってオチがあって、というものを書くのが面白くなくて、どうしようかな、と悩んで。その結果、レーモン・クノーの『文体練習』を思い出して、「やっぱり小説って、書き方によっていろいろ変わるよね」というのを短編でやろうと思ったんですよね。
合コンのことは知り合いの人にレクチャーしてもらいまして(笑)。作中に出てくる、「おしぼり」システムもその方に教えてもらって、「書いたら、合コンのときに使えなくなるかもしれませんが、大丈夫ですか」と何度も念押ししたのですが、「他の方法もあるから大丈夫です」と簡単に許してくれました。
パートごとに、「ですます調」にしてみたり「『だから』をたくさん使うパート」とか、擬音語ばかり使ったり、短い文ばかりでつなげていったり、いろいろやってみました。厳密に言うと、『文体練習』とは違うんですけど、楽しかったです。いちばん最後のシーンだけは、僕が好きな文章のスタイルで書いてあります。いろいろな楽器が好き放題やっている混沌のなかに、メロディーのくっきりしたサックスが入ってくる、みたいなのが好きなので、このラストもそういう気持ちで書いたんですよ。
首折り男のための協奏曲(二〇一四年)
今回、全作に亘って書き直してみて、面白いつながり方になったなと、自画自賛しています(笑)。共通キャラクターが出ずっぱり、というわけでもなければ、ドミノ的に話がつながっていくわけでもないですが、趣向の違う話がグラデーションのようにつながっている感じで。しかもどれも、単品として勝負するために書いたものなので、贅沢だなあと自分では(笑)、思います。
短編集全体のタイトルは悩みました。「首折り男」という言葉は使おうと最初に決めたんですが、言葉として強過ぎるから。最初は、『首ソナ』と呼んでもらいたいから『首折り男のソナタ』にしようかとか、『首フィル』と呼ばれるために、『首折り男フィルハーモニー』だ、とか担当編集者と言い合っていたんですが、「まあ、誰も呼ばないだろうね」と気づき、やめました(笑)。
(いさか・こうたろう 作家)