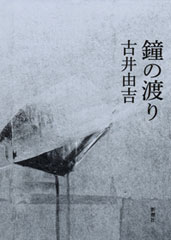書評
2014年3月号掲載
机の上
――古井由吉『鐘の渡り』
対象書籍名:『鐘の渡り』
対象著者:古井由吉
対象書籍ISBN:978-4-10-319210-7
古井由吉氏の小説をはじめて読んだとき、たとえば、濃い匂いの尿であるとか、大蛇に頭から飲まれるナマケモノであるとか、不思議に生々しい言葉に戸惑った。しかし、最大の謎は、おそらく誰もがそう感ずるように、それらの強烈な言葉が「何処から」語られているのか、という一事に尽きる。
凡そ普通の小説ではない。構造があり、主人公があり、といった物語小説の定型どころか、人称や時空といった、私たちの生活を規定する約束が、破られている。かつて「内向の世代」と呼ばれた政治や世間への不信は、それらと補完的に対立する「個」であることからも外れて行く。何処へ。言葉へ。その途方もない自由さと、正体のない不安の只中へ。
何処からか生まれ、一瞬で死んでしまう言葉のみが、本来的に空虚である自己を満たす。とはいえ、言葉という記号に自己を託すのはやはり、危険なことだ。だから〈人は言葉から漸次、狂うおそれはある〉という(「眉雨」)。古井氏は、生にも死にも近いその瞬間に立ち会うことを、創作の本義としてきた。この傾向は、現在と過去が古歌を介して交錯する『山躁賦』あたりに強まり、聖人の奇行的な死様が現在を問い返す『仮往生伝試文』を経て、近年の連作まで続いている。
今作『鐘の渡り』では、八つの短編が不揃いな連峰のように、一つの尾根を成している。死を瞑想するドイツ青年の棲む序章「窓の内」の室内は、終章「机の四隅」の机の置かれた部屋でもあるようだ。机の位置が大切らしい。窓への姿勢を決めるからだ。書く姿勢を決めるということでもある。〈私にとっては四十何年前に定職から逸れた、その前途へのいましめのように、こんなでかい机を買いこんだというつまらぬことが、このひとすじにつながる機縁となったか〉。氏が八年続けた大学の職を辞したのは三十二歳のとき。妻と二人の幼い娘がいた。まだ一冊も本は出していない。私には、氏の文章の巧みや高みを云々する前に、その覚悟が迫ってくる。
そこから外に顔を向けて死ぬことばかり考えている。自己省察に熱中していると時は一瞬に過ぎる。奇妙な愉悦と充実がある。その顔を通行人が窓越しにどう見ているかも当然意識している。そんな風に自殺したらしい知人の通夜、共通の友人から〈人のことがわからない〉と言われた。〈自分は母親というものを知らないので〉と。赤児のうちに母親を亡くしたこの友人の話は、のちに「八ツ山」で〈私〉の話として変奏される。鏡の中に入り込むように、自己と他者が入れ替わる。この交換は「鐘の渡り」の二人の男にも起こる。〈女を亡くしたばかりの男と、これから女と暮らすつもりの男〉。一見すると対照的な、二人の山登りは、やはり危険だった。
いったいどうしてそういうことになるのだろうか。
氏は〈人の心がわからないということでは、生きていても死んでいるようなもので、いま現在からして、今夜の死者(ほとけ)と変わりもない〉と感じている。だから「水こほる聲」でも〈お前は生きているのか、もう死んでいるのか、それともまだ生まれていないのか、どうしてそんなに、今なのか〉と、目の前の子供に問いかけようとする。いや大人と子供の区別もない。むしろ「地蔵丸」で描かれているように、あるいは泣き声は大人たちこそ、高く上げているかもしれない。〈一瞬の間、泣き声の往き交う光景が見えかかる。もしも菩薩のごとき目から眺めたら、無惨にもあわれな光景のはずだ〉。
この泣き声の極まるところ、生と死のあわいに、鐘の音が響いてくる。二人の男が夢現に聴いた〈成仏の鐘〉が、洪水警報の連打される半鐘が、幼き日の空襲の記憶が。それは無音の〈天上の音楽〉の苟(かりそめ)の空蝉(うつせみ)なのか。〈人間の耳はそれを感受するようにはできていない。音として聞くものは人間の耳の、すでにして思い寄りみたいなものだ〉(「明日の空」)。
生きているのか、死んでいるのか。そんなことを思いながら、古井氏の浮遊する霊魂が何を通り、何処に行くのかを見ている。氏は〈今日ばかりは心静まったらどうなのだ〉と机に就くという。まるで言葉のなかへ死にに行くようだ。それなら「方違え」の引越しは机を動かすか。その引越し先の窓からは〈あしたのお天気は御飯〉という意味不明だが健康な子供の声が聞こえて来るだろうか。氏の到達した無類の非人称に、死体化しつつある自己を解(ほぐ)されながら、冀(こいねが)っている。
(おおさわ・のぶあき 批評家)