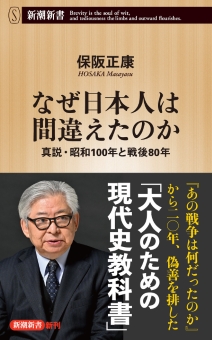書評
2014年4月号掲載
当節結婚事情と、パートナーシップと
――深沢潮『伴侶の偏差値』
対象書籍名:『伴侶の偏差値』
対象著者:深沢潮
対象書籍ISBN:978-4-10-333542-9
都下に父が建てた一軒家で、いまは母とふたりで暮らす三十五歳の真紀。つき合っている恋人はいるにはいるが、デートもセックスもおざなりで、大事にされている実感もない。
だが、十年前に父を亡くした真紀にとっては、会社の上司で十歳年上の新宮は、肉の喜びと父と似た匂いを持った失いがたい男。それに、「このまま関係を続けていけば結婚できるかも」と思うと別れられない。どっちつかずの恋のつらさを、真紀は大学時代からの友人である未央と佳乃にさえ打ち明けずにいる。自分がみじめになりそうで怖いのだ。
一方で、真紀は周囲の女たちに苛立っている。
いくつになっても作家になるだの歌手になるだの夢ばかり語り、二度めの夫とは別居中だという地に足のつかない未央。初めての恋人と堅実に結婚して三児の母となり、裕福な家庭でぬくぬく鈍感そうに生きている佳乃。結婚後にオバさん化した幼なじみ。結婚を半ばあきらめてマンションを買った会社の先輩。何より、娘の真紀と息子の麟太の心配をすることだけが生きがいのような、重い母。
真紀からすれば、どの生き方も、どの結婚も、自分が求めている幸せではないように見える。けれど、自分はそれさえも得られないのではないかと不安で、彼女たちなりの幸せを羨ましくも思う。真紀は中盤まで、そうしたいまどきの女子のメンタリティーを転写したような存在として描かれる。
そんな矢先、3・11がやって来る。混乱の中、登場人物たちが隠してきた思いがけない事実が次々と明るみになる。信じてきたことがオセロのように裏返り、ひとりひとりがこれまでの生き方を問い直し始めるのだ。
いちばん大きな変化は、パートナーシップについてだ。三年前の東日本大震災をきっかけに、震災婚、絆婚といった言葉が話題になったが、本書の中でも震災を機に、真紀だけでなく新宮も重い腰を上げて結婚を意識するようになる。
だが現実の「人口動態統計」によれば、二〇一一年の結婚総数は戦後すぐと並ぶ最低水準。結婚しない男女がますます増えている昨今、自分はどんなパートナーシップを築いていくのかは、誰にとっても切実な問題だ。そして、それはもう、男女間のごく普通の結婚に限らないのかもしれない。
本書には、そうしたパートナーシップのいくつもの可能性が描かれていく。ここで詳しくは触れないが、真紀が、親しくなったカフェの店員ヒロトと一緒に選びかける、いかにも二十一世紀的な関係はそのひとつだ。また、普通の結婚には違いないが、姑に支配されて歪んでいた夫との関係を立て直そうとする佳乃のようなケースもあるだろう。
三者三様過ぎて物語の途中まではちょっと不思議に思えた真紀、未央、佳乃の関係も、震災によって、彼女たちの友情はなかなかどうして捨てたものではなかったとわかる。これも得がたいパートナーシップと呼んでいいはずだ。
震災以降、みな大切な「誰か」「何か」を選び取っていくわけだが、どんなパートナーシップを選ぶかは結局のところ、こんな言葉に尽きるだろう。〈なんでもそうだよな。自分にとってどうかってことだよな。だから、ねえちゃんはねえちゃんの幸せを考えなよ。自分のものさしで測ってさ〉。
これは麟太が、姉の真紀と福島で再会したときの言葉。物語の最初のころ、麟太はふらふらして姉に心配と迷惑ばかりをかけていた。なのに、震災と、とある失敗を経て、ひと皮剥けて大人になった。
真紀もまた、自分が心から求めていた本当の絆のあり方に気づき、変わることができるのか。意固地で不器用だけど幸せになりたい気持ちは人一倍。そんな真紀は、いまどきの女子にとって目が離せないヒロインだ。
著者はR-18文学賞受賞作を含むデビュー作品集『ハンサラン 愛する人びと』で現代の結婚と在日との問題に斬り込んだ。一見毛色は違うけれど、著者はまたも、切実な“当節結婚事情”というテーマに向き合ってくれたのだ。
(みうら・あさこ ライター、ブックカウンセラー)