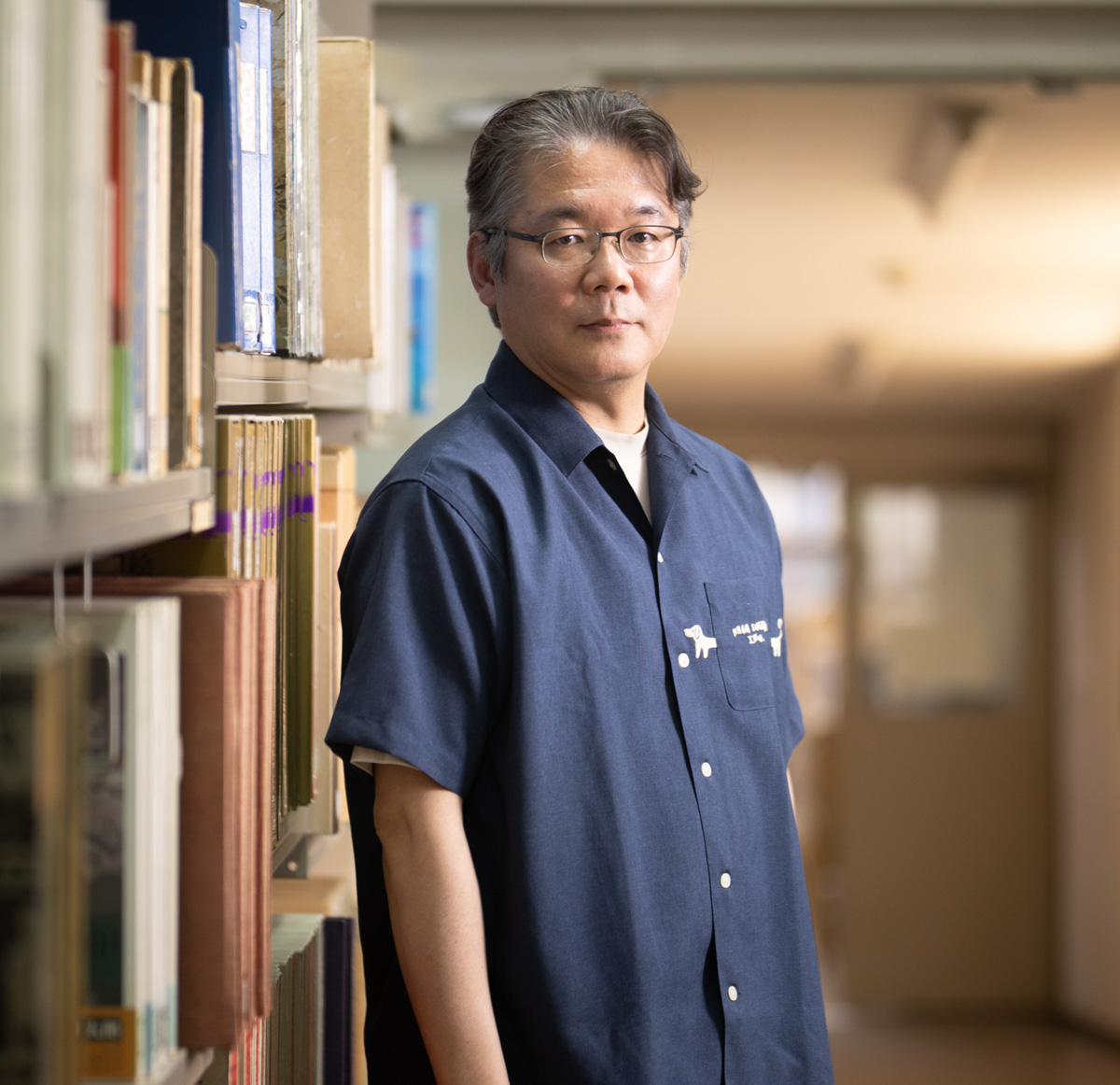インタビュー
2014年8月号掲載
万城目学『悟浄出立』刊行記念インタビュー
ずっとこんな話が書きたかった
「三国志」の趙雲、項羽の愛妾・虞姫、司馬遷の娘……。万城目学さんの新刊『悟浄出立(ごじょうしゅったつ)』は、中国の古典に登場する脇役たちを主人公に据え、これまで決して書かれてこなかった彼らの内面に光を当てる連作短編集です。足掛け五年に渡って書き継いできた物語について、たっぷり伺います。
対象書籍名:『悟浄出立』
対象著者:万城目学
対象書籍ISBN:978-4-10-120661-5

――脇役を主人公に据えるという、今作のテーマを着想したきっかけを教えてください。
始まりは高校の国語のテスト問題でした。「西遊記」の沙悟浄が、三蔵法師と孫悟空についてただひたすら考えるという文章が出ていて、それがめちゃくちゃ面白かったんです。問題自体は難しかったみたいですが、僕はめっちゃよくできた(笑)。でも、誰が書いてるかはずっとわからないままでした。太宰治かなと思ったこともあったんですが、大学三年のときに「ちくま日本文学全集」を手に取って、中島敦の「悟浄歎異」という短編とわかったんです。予備校に通っていたころから中島敦は好きで読んでいましたが、そのときはまさか「悟浄歎異」を書いた人とは気付かなかった。
中島敦には西遊記をテーマにした短編がもう一篇あります。「悟浄出世」というタイトルで、こちらは三蔵法師たちと旅に出る前の沙悟浄が主人公。川の底で、青春小説に出てきそうな男の子のうじうじした思考パターンを十個ぐらい考え続けるという、すごくいい小説なんです。
中島敦は三三歳で「悟浄出世」を書き、同年に亡くなってしまいます。この二篇に「『わが西遊記』の中」という副題を付けていたぐらいですから、このシリーズをもっと書きたかったはず。僕も、もっと読みたかった。もともと菊池寛の「忠直卿行状記」や芥川龍之介の「或日の大石内蔵助」といった、本史では描かれない登場人物の内面を丁寧に描いた歴史短編が大好きなんです。
――そこへ雑誌「yom yom」から短編の依頼があった。
このチャンスに自分が書いてしまおうと思ったのが表題作の「悟浄出立」。やはり沙悟浄が、「悟浄歎異」では注目されなかったもう一人の旅のメンバーである猪八戒について考えるという短編です。僕もそのとき三二歳になっていましたから、厚顔無恥ながら、どれぐらい差があるのか試してみようと。
――実際に書いてみていかがでしたか。
いやもう、天と地のような筆力の差でした。語彙力がまず違う。中島敦は漢文の素養が豊かだから、こちらが二行ぐらいかけて書くことを一語で表現する技術がある。それだけで文章がぐっと締まるんですね。自分の文章のひらがなの多さが嫌になりました。
そうは言いつつ自分では、青いけれどいい話が書けたと思いました。このまま西遊記の話を書き継いでいくか、他の物語の脇役にスライドするか迷ったんですが、西遊記だけでこれ以上書くのは自分には難しかった。
――もともと中国の古典も読んでいらっしゃいましたか。
僕の年代の進学校に通っていた男は、みんな歴史物を読んでいたようなイメージがあります。中学生で読んだ吉川英治の三国志や水滸伝から始まって、高校に入ってからは陳舜臣さんにはまりました。中国ものに限らず、中高生のときの読書は七、八割が歴史小説でした。中学一年生のときに骨折して、山岡荘八の『徳川家康』二六巻を一ヶ月かかって読んだこともあります。
ただ今回は、一冊の本の中に日本と中国の話が混在するのに違和感があったので、中国の古典に登場する脇役たちを主人公にして書き継いでいこうと決めました。次のモチーフはすぐ三国志と決まりました。二話目は趙雲という、三国志における準々主役ぐらいの登場人物を主人公にしています。
日本人がある程度知っている話から材を採ろうとしたんですが、「忠臣蔵」級の有名なエピソードはなかなか見つからない。そのうち、三話目で項羽の愛人である虞姫の話を書こうと思いたち、「史記」を何度も読み返すうちに四話目の荊軻のエピソードや五話目の司馬遷の娘の話を思いつくというように、資料を読みながら次の物語を考えていきました。
実はこのシリーズは、二話目と三話目の間に四年間の中断があります。その間は二作の長篇を執筆していました。それで、二話目までとその後がちょっと違うんですね。最初の二本は小説から材を得ていますが、後半の三本は歴史的な事件、実際にあった出来事をもとにしています。前作の『とっぴんぱらりの風太郎』で歴史的な出来事を元に小説を書く訓練を二年間やった経験が生きていると思います。
五話目の短編「父司馬遷」の時点でもう、半年間ずっと「史記」ばかり読んでいた状態でした。もうね、面白すぎるんです。史実の上にかなりエピソードを盛りつけてると思いますよ。司馬遷は紀元前一〇〇年ぐらいを生きた人で、現代はそこから二〇〇〇年経ってるわけですが、中国史において「史記」より面白い話がほとんどないんです(笑)。
――作家としてはすごい実力ですよね。
はい、もう勝てないです。彼が「史記」に虞姫と項羽の話を取り入れたからこそ、それが脈々と残り、京劇になったり現代映画のモチーフになったりしている。ものすごい影響力ですよね。
彼の出生年については諸説あるのですが、司馬遷は三二歳で「史記」を書き始め、三八歳で宮刑を受け、四六歳で書き終えたという説に会ったときは衝撃を受けました。「宮刑」とは当時の刑罰の一種で、去勢される刑のこと。三八歳といえば、まさに今の僕の年齢にあたります。この齢で、男としての機能を失い、一生を蔑まれて生きるなんてありえないと思いました。ありえないからこそ、その内面にはいろんな思いがあったはずで、その思いを書いてみたいとも思いました。
今回の本では、三三歳の中島敦といい、三八歳の司馬遷といい、自分とどこか年齢がリンクしている。高すぎるハードルを前に、躊躇があっても、そういうときをチャンスと考えて思い切ってやってみるのがいいと思うんです。僕は文豪の作品の、巻末に付いている年表が好きで、自分と引き比べては「あっもう負けてる」などと考えてしまうタイプです。中島敦もそうです。ただ例外もあって、三〇歳前の、デビュー前の無職のときに夏目漱石の年表を見たら「三〇歳で神経衰弱」とあって、なんていい奴なんだと思いましたね(笑)。
――五話それぞれに、幅広い人間像を持つ主人公が登場しますね。よりご自身に近い登場人物は誰なんでしょうか。
シンパシーを覚えるのは四話目「法家孤憤」の主人公、京科ですね。始皇帝を暗殺しようとした男と同姓同名の、しがない官僚です。今まであまり自分に近い人間を書いたことがないんですが、この人に関しては、もし同じ立場だったらこう考え、こう行動するだろうことをそのまま書きました。
たとえば僕の同級生で、優秀で中央官庁に行った人がいるとしますよね。そこへ無職でへらへらしてた僕が作家になり、上手いことやってるのを見たとしたら、「あいつはあんなに楽しそうやけど絶対俺のほうが世の中の役に立ってる」と思うに決まってます(笑)。でも、男にはそれぐらいの負けん気があったほうがいい。この話には男同士が飲み会なんかで考える、他人のステップアップを素直に認められない、もやもやした感情がそのまま入ってます。
もうひとつ、この短編で書きたかったことがあります。大学で法律を学んでいたときに感じたことなんですが、法律の教科書の文章――特に序文――って、すごくピュアなんですよ。法律を定めることで世の中の仕組みが整理され、ひいては世の中が良くなるということがおそろしく真っ直ぐに書いてあるので、読んでいるとだんだん「ひとつの法律を作るだけで、こんなに世の中よくなるんや」と思えてくる(笑)。法が本質的に志向する善意のようなものを表現したかったんですが、なかなか難しかった。自分ではあんまりうまくいってないように思います。
――今作には、女性が主人公の作品が二篇納められています。
書いているときには、登場人物が女性だからといって特に区別はしていないんです。でも二篇とも、書いてみたら他の作品よりも感情の発露が激しくなっている。その理由を考えたときに、今回の二人は――特にこの時代の女性ですから――いい意味での視野の狭さがあるのかなと思います。目の前に一人の男がいて、その男しか見えず、ただぶつかっていくという気持ちで書きました。
今回に限らず、他の小説を書いているときでも、女性は強い色で描けるけれど、男性の場合は弱い色しか使えないように感じています。これまであまり考えたことはありませんでしたが、男性のはっきりした感情は、もしかしたら恥ずかしくて書きにくいのかもしれません。もしそういう感情を扱うなら、むしろ向き合うことから逃げて妄想に行く話を書きそうです(笑)。
――今回の本は、ファンタジー的設定が登場しないはじめての本ですね。
最初に目指した中島敦の作品の形に沿って書いたら、こうなったというだけです。自分ではあまりファンタジー的設定があるとかないとか意識しなかった。今回は短編ということもあって、そういう要素を出さなくても頭の中で終点までの道筋を作れたように思います。いや、本当は出さずに済むなら、これまでだって今作のように書きたかったんですよ! まあ、こんな作品、しばらく書けないでしょうね。
――前作の『とっぴんぱらりの風太郎』、続く今作と、これからも歴史小説を書いていかれるのかと思いましたが。
いや、当分ないです。同じ「脇役」という視点からの日本史版をやってもいいかなと思ったこともありましたが、あんまり心惹かれない。異国を舞台にするからこその面白さってあると思うんですよ。ファンタジー要素がないといいつつも、異国を舞台にしたことで、「いまここ」と違う世界に入っていく面白さが出せる。しかも中国史をモチーフにすると雰囲気が締まるというか、一気に知的になる。そう考えると、『悟浄出立』は、日本人が最大限に味わえる、「物語」の楽しみ方を提示しているかもしれませんね。
(まきめ・まなぶ 作家)