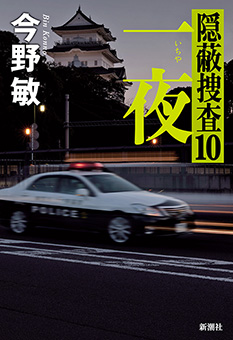インタビュー
2014年11月号掲載
『冬を待つ城』刊行記念インタビュー
戦国最後を飾る謎の籠城戦
聞き手:紫野京作(本誌)
天下統一も最終段階の一五九一年、秀吉は奥州北端の九戸城に、何と十五万もの大兵力を差し向けた。謎に包まれた包囲戦を描いた歴史大作の、舞台裏を作家に聞いた。
対象書籍名:『冬を待つ城』
対象著者:安部龍太郎
対象書籍ISBN:978-4-10-130527-1

――安部さんは一貫して時代の潮目を描くことに腐心してこられましたが、本作でも秀吉の天下統一から朝鮮出兵、つまり外征へ向かう節目の時期を選んでおられますね。
安部 天正十八年の小田原征伐で一応天下統一が終り、その後奥州の国分けが行われる。伊達政宗から会津領を没収して蒲生氏郷に与えるのですが、葛西・大崎一揆が起きた。背後にあるのは伊達の使嗾です。政宗と氏郷の対立に決着がつかぬまま天正十九年を迎える。大きく言えば国内統一が終り、外征へと向かう節目ですが、この年に九戸政実の乱が起きる。しかしこの乱は、歴史的解明がまだ進んでいないんです。
――天下統一の総仕上げ段階になってなお服従しない九戸政実にも驚かされますが、九戸勢は三千から多く見積もっても五千に過ぎない。彼らの立て籠もる九戸城に秀吉が差し向けたのは十五万。なぜこんな大兵力が必要だったのか。これは戦国最大の謎の一つですね。
安部 勝てるはずのない戦さに政実はなぜ踏み切ったのか。また多くの武将たちが彼に賛同して付き従った理由はどこにあるのか。戦うと決めた以上、政実には勝算があっただろう。怒りや反発や意地だけではなかったろうと思います。政実ならやってくれるというカリスマ性も要因の一つでしょうが、何か確信めいたものがあるはずだ。そうした疑問を抱えて九戸城に取材に行ったんです。そのとき私は、まず城のスケールに圧倒された。関東以南の城と全く顔つきが違うんです。何というか熊の親分みたいな野性的面構え。廓の一つ一つが広大であるだけでなく、河岸段丘の上に築かれているため防御性が頗る高い。しかも周囲の地形が大兵力の進軍を決して許さぬものだということが一瞬で見て取れるんです。奥州の冬という厳しい条件を考えれば、長い滞陣は出来そうもない。秀吉軍側から見れば、じゃあ補給はどうするんだ、兵士たちが起居する陣屋はどうなんだということになる。海からの補給が可能だった小田原攻めとは比較にならないじゃないかと。秀吉軍が攻めかかった旧暦九月朔は今日の十月十八日に当る。もう二週間もすれば雪の季節の到来です。ナポレオンやヒトラーの前に立ちはだかった冬将軍を味方につけ、勝てぬまでも負けない戦さが十分に出来ると政実は踏んだのでしょう。包囲軍の総大将・蒲生氏郷は、前年の一揆鎮圧のために雪中行軍を強いられた苦い経験がある。氏郷は九戸城を前にしたとき、罠に落ちたのは我が方だと瞬時に気づいたはずです。
――負けない戦さを仕掛ける、その目的ですが、この小説は読者を十分納得させるだけの卓見に満ちています。
安部 それは大きく言えば秀吉の奥州政策を変えさせることです。九戸の城兵の五十倍もの大軍をわざわざ冬を待つ奥州北端に差し向ける秀吉の狙い――これは常識的に考えれば次の外征を念頭に軍事演習をやったのだと結論せざるを得ない。日露戦争前に八甲田山で演習を行い多くの死者を出した陸軍を思い浮かべるとわかりやすいですね。それと、冬の厳しい朝鮮半島に攻め入るために寒さに慣れた人足を奥州から徴発する目的もあったに違いない。いわば人狩りです。こうした中央政府の理不尽な目論見から、いかに奥州の土地と民を守り抜くか、それが政実の真意だったと私は思うんです。
――九戸政実がその四兄弟を纏め上げ、力を結集するプロセスに紙幅が費やされている点も本作の特徴です。
安部 当時の九戸家は非常に複雑な立場に置かれていました。南部信直が主君ではあるが、一族の間で内紛が絶えない。九戸政実の三人の弟、実親、康実、政則も、それぞれの立場から主家の内紛に関わっています。そんな状況だから、我々の大儀はこうなので力を結集しようと、いきなり呼びかけたって簡単に納得してはもらえない。そこで政実は、南部信直との対立の節目節目で兄弟を取り込む手を打ってゆく。境遇の違う弟たちが、自主的判断で力を合わせる方向に導くためのプロセスですね。時間をかけ、TPOをわきまえつつ四兄弟を束ねてゆく政実の深謀遠慮には目を見張るものがあります。現代でも政治や会社経営の現場で同じような状況がしばしば起こっていると思いますが、不安定なポジションに長年置かれた政実ならではの知恵、現代風に言えばインテリジェンス感覚が、こうした難局の打開につながったと言えそうです。
――本作を読み進むさいに、おや、何だろうと気を惹かれるインターミッションにしばしば出会います。中央政府の目論見や諜報活動が、書状や会話等さまざまなスタイルで各章に配された部分ですが。
安部 知的な戦いを興味の糸として配してゆく欧米のサスぺンス小説の形式を、この作品では使いたかったんです。中央政府、特に石田三成の謀略の見えざる糸を少しずつ明らかにする流れを横糸とするならば、仕掛けられた情報戦を迎え撃つ政実の深謀遠慮が縦糸となって、四兄弟の結束が完成してゆく。視点人物は末弟の政則ですが、その行動範囲は九戸周辺にどうしても限定されるので、日本全体の構図のなかでこの戦さの意味を問うとすれば、中央からの情報が見え隠れするインテリジェンス小説のスタイルが最も相応しいのではないかと思ったわけです。政則は京都で仏道修行をした経験を持つ人物ですから、都を知っているだけでなく仏教という普遍的価値観を持っている。これは彼が物事を理解する上での幅になってくるんですね。つまり地理的な視野の広さと価値観の深さとを同時に備えた人物。そんな政則から見ても、初めのうち長兄のやっていることはいかにも危ういと映る――そんな外からの視野を作品に持ち込むために、この形を採用したわけです。そうすることによって初めて、九戸政実の乱が立体的に捉えられたのではないでしょうか。
――中盤にとても印象的なシーンがあります。奥州のスピリチュアルなパワーを感じさせる感動的場面でした。
安部 古えの日本列島に、南方から北方から、そして朝鮮半島から多くの人が渡ってきた。その頃の日本は、渡来民と先住民との多重複合体だったはずです。それが次第に単一化されてゆき、日本はずっと天皇制のもとで国家を形成してきたというフィクションを生んだ。地球が今より温暖だった頃は、日本列島では人口の九割が関東以北に住んでいたことが明らかにされています。先住民族である奥州の蝦夷は、その中心的存在だった。とすれば我々の意識の土台部分にあるのは、大和朝廷成立以前の多重複合体の記憶だろうと思うんです。オシラサマやイタコ、あるいはキリストの墓やピラミッド、奥州にはまだ解明されていない不思議なものが沢山残っている。近代化とともに否定されたり面白半分に取り上げられることもありますが、一概に荒唐無稽と全否定できるものじゃない。そこには六千年の歴史が堆積していて、その上に九戸城が立っているわけですよ。いわば休火山の上で人々が生活しているような具合。だから一朝事あれば、その地層につながる価値判断が浮上する。生死のかかった時の判断の拠り所として、人間はこうした地下水脈、集合的無意識に行き着くのではないでしょうか。主人公に奥州六千年の歴史を早廻しするようなスピリチュアル体験をさせたのも、そうした奥州のアイデンティティと大いに関係があります。逆に関東以南の人々はどうかと言うと、相次ぐ征服戦の犠牲となった奥州は夷狄であるという無意識が今も働いている。それが、東日本大震災の復興の遅れの遠因となってるんじゃないでしょうか。
――終盤の籠城戦、そして和議に至るまで、緊張感が持続する作品でしたね。
安部 これは領国が滅亡の危機にさらされた時の、家族の物語でもあります。主人公・政則は、妻子とともに籠城戦を戦わざるを得なくなるわけですが、籠城という密室状況で、一族がどんな犠牲を払って何を決断したか、また家族はどうやって危機を乗り切ろうとするのか――これもこの小説のテーマの一つです。
(あべ・りゅうたろう 作家)