インタビュー
2015年2月号掲載
『祖国の選択 あの戦争の果て、日本と中国の狭間で』刊行記念特集 インタビュー
世代を超えて
対象書籍名:『祖国の選択 あの戦争の果て、日本と中国の狭間で』
対象著者:城戸久枝
対象書籍ISBN:978-4-10-121051-3

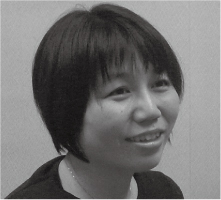
――国交がなかった中国から一九七〇年に自力で日本への帰国を果たした元戦争孤児の父・城戸幹さんのことを書いた『あの戦争から遠く離れて 私につながる歴史をたどる旅』(二〇〇七年、情報センター出版局刊。大宅壮一ノンフィクション賞、講談社ノンフィクション賞、黒田清JCJ新人賞を受賞。同書は「遥かなる絆」のタイトルでNHKでテレビドラマ化もされた。その後、文春文庫化)の出版から、七年余りが経ちました。その間、どのように過ごしてこられましたか。
城戸 十年以上かけて取材をして父の足跡を本に書いたことが、私にとってとても大きかったものですから、自分の気持ちとしては、なんだかそれでもう終わったような感じになっていました。正直なところ、その先のことについてはあまりよく考えていなかったのです。でも、『あの戦争から遠く離れて』の出版がきっかけで、いろんな出会いがつながっていきました。本を読んで、あるいはテレビドラマを見て、父の過去に興味を持ってくださる方も多かったのですが、戦争体験者の方に会う機会も増えました。たとえば、講演に行った先で、「実は私も満州にいたんです」とか、「私の母も戦争でこんな出来事に遭いました」などと仰る方に出会うこともよくあったのです。だからといって、すぐに、そういった戦争体験者の方々のことを書こうと取材を始めたわけではありませんでした。それぞれのお話はそれぞれに重く、私の中で受け止め切れないような苛酷で壮絶な事実に満ちていましたし。
――『祖国の選択』の第四章に書くことになった松永好米(よしめ)さんのお話を最初に知ったときは驚いたでしょう。城戸幹さんが「中国残留孤児」になる直接のきっかけとなった、林口駅付近でソ連軍の戦闘機による機銃掃射に遭った列車に、松永さんも乗っていて、城戸幹さんの姿を目にしていた。
城戸 林口で実際にどのようなことが起こったのか、当時三歳九カ月だった父から聞いた話ではよくわかりませんでした。ところが、その場に居合わせた人がいたわけです。それが、松永好米さんでした。松永さんは二〇〇七年十一月に電話をくださったのですが、そのとき私は新婚旅行に行っていて、旅行先で電話を受けたのでした。たしかに、お話を聞いて衝撃を受けました。旅行から帰ったらとにかく会いに行ってみようと思い、翌年、実際に、お住まいのある大阪へ行ってお目にかかってみたら、松永さんはとても気さくで明るい“大阪のおばちゃん”でした(笑)。おばちゃんといっても、そのとき松永さんはすでに九十三歳だったわけですが。
松永さんにお会いしたときは、やっぱり、まず、父についての話を聞きたいという思いが強かった。でも、お話を聞くうちに、松永さんご自身の体験談に私がどんどんと引き込まれていったのです。
――松永さんのみならず、『祖国の選択』には、あの戦争に翻弄された経験をもつ人たちが登場します。
城戸 本に書かせていただいたそれぞれの方々とは、偶然の出会いというとおかしいのですが、私から探しに行ってお会いしたわけではなく、自ずと縁がつながっていった感じです。それぞれの方々のお話を聞いているときは、こんな本を書こうという具体的な計画はありませんでした。でも、何度かお目にかかってお話を聞いていくうちに、戦争体験の断片を中途半端に聞くのではなく、その人の人生を丸ごと知りたいと思うようになったのです。
ただ、私は二〇一〇年に子供を出産したこともあり、途中で「取材」が中断するようなかたちになってしまいました。そうして時間がかかったことも、たぶん結果的には良かったのだろうと思っています。それぞれの方々の体験について、時間をかけて私なりに理解を深める必要がありましたから。また、もし子供が生まれる前に書いていたら、私自身の理解の仕方や言葉の表現もかなり違っていただろうとも思います。
――二〇一五年は「戦後七十年」にあたる年です。
城戸 時間の経過にともなって、あの戦争のことを具体的に語ってくれる人のお話を聞ける機会はますます貴重になっていくでしょう。だからこそ、ちゃんと語り継がれるべき事柄がそこにはたくさんあると思うのです。私自身も、今思えば、『あの戦争から遠く離れて』を書いているときは、戦争についてしっかり考える姿勢を持てていなかったかもしれません。その後、父以外の戦争体験者の方々の様々な話を聞けたことによって、過去の戦争だけでなく、何が起こるかわからない未来も含め、自分と自分の子供の世代にも直接的に関わることとして戦争というものを考えられるようになった気がします。いろんな人の過去の「選択」の先に今があり、私たちがいるわけです。「戦後七十年」の節目をひとつの契機に、過去の戦争を、今やこれからにつながることとして、世代を超えて考えていけたらと思います。
(きど・ひさえ 著述家)










