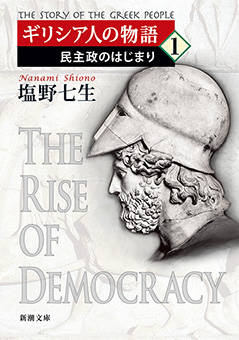書評
2016年1月号掲載
現代政治の源流へ
――塩野七生『ギリシア人の物語Ⅰ 民主政のはじまり』
対象書籍名:『ギリシア人の物語Ⅰ 民主政のはじまり』
対象著者:塩野七生
対象書籍ISBN:978-4-10-118112-7
塩野七生さんの新作が古代ギリシャをめぐる三部作だと知り驚いた。
塩野さんといえば古代ローマ。独特の創作リズムを乱すことなく一五年間かけて完結させた『ローマ人の物語』全一五巻はまさに金字塔だ。並大抵の作家や学者には真似出来ないし、完全に燃え尽きてしまうだろう。私ならもう何もしない。
しかし、この希代の叙述家はそこで止まらない。何と古代ギリシャへと探究心を広げ、このたびの三部作の初巻の刊行と相成った。
塩野さんを駆り立てたのは、まず、ギリシャに対して「失礼」という想いだ。「ギリシア・ローマ時代」と称される割には、『ローマ人の物語』でギリシャを扱ったのは第一巻のごく一部。ローマからギリシャを見るのではなく、ギリシャを内側から捉え直すことにした。古代ローマ、ひいては地中海世界をより真摯に理解しようとする矜持には圧倒的なものを感じる。
もう一つ、塩野さんを誘ったのは、古代ギリシャ、とりわけアテネが世界史における「民主政治の創始者」である点だ。昨今、代議制民主主義の危機が盛んに指摘され、訳知り顔の論客がメディアを賑わせているが、そうした日本の言論状況に対して「拒絶反応」を覚えるようになったという。時局対応型のポジション・トークではなく、ここは一つ腰を据えて、じっくりと古代ギリシャの民主政の実相を探ろうというわけだ。その意味で、本書は、単なる歴史物語とは明らかに一線を画している。
米国研究やソフトパワー研究を専門とする私にとって、今回の三部作は、さらにもう一つの点から、極めて現代的な含蓄に富む。それは、いわゆる「ツキディデスのジレンマ」が、目下、外交・国際関係において改めて注目されているからである。
「ジレンマ」とは、古代ギリシャにおいて、アテネの急速な台頭に恐怖を覚えたスパルタの過剰反応がアテネの恐怖を引き起こし、負のスパイラルへと転じた結果、戦争に至ってしまったという安全保障上のジレンマを指す。
そして、いわばアテネが今日の中国であり、スパルタが米国ではないかというわけである(もっとも、中国の政治体制は民主政とは程遠いが)。米国内の穏健派は過剰反応の罠を戒め、強硬派は宥和主義の愚を難ずる。
新興国の台頭に覇権国家がどう対峙するかは国際秩序の行方を大きく左右する。第一次世界大戦によって米国は一気に頭角を現わしたが、大英帝国が「ジレンマ」に陥ることはなく、国際秩序は概ね維持された。米中関係の今後を読み解くうえでも古代ギリシャを理解することは重要だ。
本巻では、アテネとスパルタの衝突以前、すなわち都市国家(ポリス)の形成・発展、そして度重なるペルシャ帝国との息を飲むような名戦が鮮やかに描かれている。
ローマ人が「長距離走者」なのに対し、ギリシャ人は「短距離走者」であり、かつ「イノヴェーションの塊」だということ。アテネの政体の本質が「リレー競走」なのに対しスパルタは「徒競走」であること等々。人間や社会の本質への鋭い炯眼を交えた塩野さん特有の語り口は健在だ。
都市間の巧妙な駆け引き、戦力や地勢の比較、戦略や戦術分析......どれも抜群に面白いが、私にとってはアテネを中心とする「デロス同盟」とスパルタを盟主とする「ペロポネソス同盟」の話がとりわけ心に響いた。「同盟」という概念そのものを理解するうえで、古代ギリシャの事例はあまりに重要だからである。
例えば、現代米国を代表する国際政治学者であり、日米同盟の理論的支柱の一人であるハーバード大学のジョセフ・ナイ教授の研究の出発点はペロポネソス戦争だった。同教授による新入生向け授業では、同戦争を事例として国際関係におけるリアリズム(現実主義)とリベラリズム(国際協調主義)の優劣が論じられていた。
つまり、古代ギリシャとはまさに現代世界であり、ギリシャ人の苦悩は我々自身のものでもあるのだ。
古代ギリシャという、とてつもなくタイムリーなテーマに切り込んだ塩野さん、あっぱれという他無い。
(わたなべ・やすし 文化人類学者、アメリカ研究)