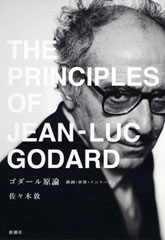書評
2016年2月号掲載
ゴダールの飽くなき闘争
――佐々木敦『ゴダール原論 映画・世界・ソニマージュ』
対象書籍名:『ゴダール原論 映画・世界・ソニマージュ』
対象著者:佐々木敦
対象書籍ISBN:978-4-10-332892-6
私は佐々木敦の書くものを好きだ、信頼もしている、その理由まで私は考えたことがなかったが今回この『ゴダール原論』を読んでわかった、彼が書くと書かれた対象がとても肯定的で活力に満ちたものに感じられるからだ、これは大変なことだ、彼は"批評家"ということになっているが肩書きはどうでもいい、というかこの肩書きは一般の批評家・批評文によって矮小化される。
一般に批評というのは「わかった」ことを書く、しかし批評が対象とする作品は批評家がそれに心を動かされたから書くのだから作品は批評より大きい、自分より大きい相手を「わかる」ということはそれを語る行為の前提において矛盾する。今回この本でいかんなく展開される佐々木敦の思考はわかることに向かうなんてセコいことでない、聖書や教典を丸ごと飲み込もうとしてひたすらそれに付き従う使徒のようにゴダールの映像と音と言葉を見、聴き、読みつづける、だからゴダールは書かれるにつれて大きくなり活力をさらに充填され、どんどん混沌となる。
この本を読みながら私はこんなにもゴダールの映像と音と言葉を真っ正面から受け止めることに感動した、読者は『さらば、愛の言葉よ』をもはや観ている必要はない、観ていても佐々木敦のように隅々まで観ることはとうていできない。私は佐々木さんとまったく逆のベクトルでここ二十年、あるいはゴダールに出会った最初からゴダールと接してきた、私はゴダールが映画の中で引用する哲学や文学の言葉たちをゴダールはわざと未消化なまま投げ出す、あるいは映画に放り込んでいると思っていた、そのように未消化なものを放り込むことで作品化されない、作品としてお行儀良くなる以前の思考が映画とともに観る者の中で励起される、だから私はもう最近はゴダールを観てもただただ勝手に自由を感じ、元気になった。
映像はほとんど全篇、こんな画面はゴダール以外には映画にならない、しかしゴダールでは映画になっている、映画のボーダーとは何なのか? そもそも映画にボーダーなんてものはあるのか? あると思い込んでいるだけだったんじゃないか? ボーダーがあると思うことでしかし作る側も観る側も守られる、守られる必要などないことに気がつけばボーダーなどなくなる、何が映画なのか? 映画を映画たらしめるものは何なのか? そんなものは最初からないんだ、とゴダールは言ってると私は勝手に感じた、もちろんこの"映画"は私にはそのまま小説となる、もっと広く書くことにもなる、そのまま考えることにもなる。
私の感じたこれらを佐々木敦はベクトルは逆なのだがすべて言葉にしようとしているとも感じた。しかしそれでもひじょうに重要な違いが私と佐々木敦にある、私は『さらば、愛の言葉よ』を観ているあいだほとんど冒頭から終わりまで、人間の近代の歴史に対するゴダールの失望を感じた、ゴダールは世界は結局こんなものになった、とずうっと言いつづけていると感じた、しかし佐々木さんは『さらば、愛の言葉よ』の全篇を、3D映画の起源にまでさかのぼる数々の資料も動員して精緻に読み込みこの全体を飽くことなくつづいていたゴダールの闘争と見ている、これは冒頭に戻るのだが「映画にできることはもう限られている」というここ二、三十年広く流布する芸術観に私ははからずも着いていた、佐々木敦はそれに着かないということだ。私はゴダールを仰ぎ見ていると思いつつ矮小化していた、映画に引用される言葉にそのつど元気づけられたりインスピレーションを与えられたとしても私はもうゴダールの映画の一つ一つの違いや進みを無視していた。
〈2〉であること、〈ワン・プラス・ワン(プラス・ワン・......)〉のこと、〈3〉であること、三位一体......、私はそこまで考えるか! と、これはこじつけではないかと思うこともあったが、ゴダール自身がかりにそこまで考えていなかったとしても(私はそう思ってきたのだ)、ゴダールの撮影や編集時点でのそのつどはそれらを意識の外での演算として遂行していたことは否定するのも不自然だ、作家というのはわりと無頓着にそれらをやってしまうわけだが作家の行為のそのつどは言語化可能な範囲の意図と別のシステムにおいてそれをそのつど、狙ったところに球を投げたり蹴ったりできる技は本人はいちいち言語化できないように作家はそういうことをする、そこに踏み込み、言葉にするのが批評なのだから佐々木敦はほとんど一人でそれをしている、すごいことだ。
(ほさか・かずし 作家)