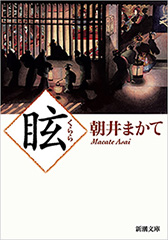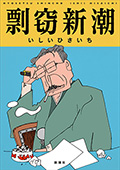書評
2016年4月号掲載
『眩』刊行記念特集
もの作る者は闇を駆ける
――朝井まかて『眩』
対象書籍名:『眩』
対象著者:朝井まかて
対象書籍ISBN:978-4-10-121631-7
くらっときた。
なぜか、と言えば、人生の疾走感があるからだ。
女がひた走る。『冨嶽三十六景』で世間をうならせた絵師、葛飾北斎の娘、
――お栄
である。父親が絵師なら、娘も絵筆をとる。物の道理なのかもしれない。絵師としての名は、
葛飾応為
これまでも応為を描いた作品はある。だが、女絵師と言えば、静かな佇まいで筆をとり、胸の裡に情念の焔がゆらめく、となりがちだ。しかし、本作のお栄は違う。まわりの勧めで南沢等明という絵師に嫁いだが、口うるさくされると、
――ああ......面倒臭ぇ
と本音が口をつく。
(そうさ、あたしは北斎の娘さ。なのにその才を受け継がずにのたくっている)
北斎になりたいのか。そうかもしれない。いや、違う。もっと違う北斎だ。つまりはわたしになりたいんだ。そのわたしに、まだ手が届かない。じれったい。
だから、お栄は亭主に愛想尽かしをする。
「あたしはね、区々たる事に構ってる暇はないんだよ」
ここまで、きっぱり、区々たる事と言われたら、男は成仏するしかないだろう。ちなみに実際の応為も、
――妾は筆一枝あらば衣食を得ること難からず何ぞ区々たる家計を事とせんや
と喝破した。そんなお栄が、ちょいと惹かれるのが、善次郎こと絵師の渓斎英泉だ。元は武士で浮世絵を描くようになった男だ。無頼の趣があり、淫靡で退廃的な美人画では他の追随を許さない。お栄にしても美人画を描けば、北斎から認められた腕前だ。英泉も、お栄のことを、
――画ヲ善ス 父ニ従テ今専画師ヲナス 名手ナリ
としている。だが、ふたりとも飽き足りないものがある。いつか越えてやる、と口にはしないが、見つめているのは、〈親父どの〉北斎の大きな背中なのか。
お栄にとって口うるさい母親の小兎、北斎の晩年を悩ます孫の時太郎、絵師の一家は倒けつ転びつ、すり傷だらけになりながら、時代の坂を駆けていく。
描かれるのは絵師に限らない、物を作り出す人間の生きる覚悟だ。不出来な作品を世に出せないという弟子たちに北斎は言う。
――たとえ三流の玄人でも、一流の素人に勝る。なぜだかわかるか。こうして恥をしのぶからだ。己が満足できねぇもんでも、歯ぁ食いしばって世間の目に晒す。
それが玄人なのだ。『南総里見八犬伝』の著者、滝沢馬琴は、病に倒れた喧嘩相手の北斎を見舞って「無様よのう」と悪態をつく。自分なら死ぬまで書くぞ、と。
――たとえ右腕が動かずとも、いやこの目が見えぬ仕儀に至りても、儂は必ずや戯作を続ける。まだ何も書いてはおらぬのだ。己の思うままに書けたことなど、ただの一度もござらぬ。その方もさようではなかったのか。
悪罵は才能を認めた相手が起たぬことへの憤りであり、奮起をうながす激励でもあった。お栄もおのれの道をひた走り、やがて『吉原格子先之図』を描いた。夜の吉原、灯りの光が格子戸を漏れて、往来の影と交差する。人生の闇は深く、それでもひとの営みのけなげさは美しい。お栄のたどりついた世界を垣間見れば、読者もまた、
くらっ
とするに違いない。
作者の朝井まかてさんとは二度ほど、会食したことがある。本作を読みながら、まかてさんの地声を聞く気がした。お栄の懸命さ、歯切れのいい爽快さは、まかてさんのものだ。
ところで、言い忘れたことがひとつだけある。
傑作です。
(はむろ・りん 作家)