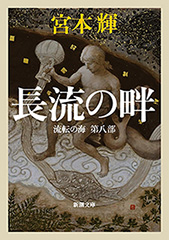書評
2016年7月号掲載
『長流の畔』「流転の海」第八部 刊行記念特集
「死と失敗と挫折」を乗り越えて行く人間の姿
――宮本輝『長流の畔』「流転の海」第八部
対象書籍名:『長流の畔』「流転の海」第八部
対象著者:宮本輝
対象書籍ISBN:978-4-10-130757-2
『流転の海』第八部『長流の畔』までを完成するのに宮本輝は三十五年の歳月をかけた。『流転の海』は何もかもが廃墟と化した敗戦後の日本を舞台に、関西の庶民の生活が再現され、庶民の視点で歴史が語られる作品である。
宮本輝は一九四七年に神戸市で生まれた。愛媛県生れの父熊市は大阪に出て自動車部品を中国に輸出する仕事についた。母雪恵は茶屋の仲居をしている時、熊市と出会い結婚した。父は性的に放縦で、暴力をひめた、反道徳的な、恐るべき男である。母はすべてを受け容れてくれるタイプの女である。
小説のなかの熊吾は熊市、房江は母雪恵がモデルであり、二人の息子伸仁のモデルは輝自身である。そしてこの小説は作家一家の戦後史であり現代史となっている。
一九五二年、熊吾は大阪の中之島で事業を再開した。三階建てのビルで中華料理店、雀荘、テントパッチ工業の三つの商売をはじめた。その事業が中華料理店の食中毒事件、共同経営者の杉野信哉の脳溢血、うつ病の症状をともなった妻の更年期障害と不幸が続出して破綻する。心機一転を図って大阪を離れ、富山に移り新しい事業を開始しようとするがうまくいかない。そして数々の経験を積んできた熊吾は、一九六四年の東京オリンピック景気にわく街をあわただしく駆け回っていた。彼は中古車を販売する大阪中古車センターと松坂板金塗装の店を経営していたが、社員に運転資金を横領され事業の危機に見舞われていた。
熊吾は新聞で南ベトナムの僧侶が焼身自殺したのを見て、自分のなかで何かが狂いはじめたことを自覚した。彼は戦場で指揮官の命令である満州の集落を焼いた。彼は生きている農民はいないと信じて焼いたが、銃剣で喉を刺された老人はまだ生きていることを知った。自分の「狂い」にはこうした無意識化の「何か」が影響しているのではないか。
俺が犯した失敗は、まだ若い博美の体に再び手を出したことだったと熊吾は思っていた。もう六十六歳になる俺が博美の体に執着し、厄介なヤクザ者と別れさせるために七十万円もの金を使った。そして博美のことを妻に知られてしまった。
「俺は、男の機能も糖尿病とともに萎えたとばかり思っていたが、博美の体は別格で、いつも若いころと同じくらいに漲らせてくれる」。熊吾のなかの男の業は消えていなかった。
高校生の伸仁は、若い女に狂い借金のために駆け回る父の生き方に反撥する。また母が自殺未遂をしたことで自分を捨てたと抗議する。
城崎の満月を見に行くのを楽しみに生きてきた房江は、夫のあとをつけて、夫が若い女の家に行き、「お父ちゃん、おかえり」と言って迎えられているのを見てショックを受けた。そこで房江の堪忍袋の緒が切れた。房江は夫と愛人がこもる部屋に乗りこんだ。慌てて阻止しようとする夫を突き飛ばし、ここで女と野垂れ死にすればいいと言い置いて帰ってきた。
その後、房江は夫と女を罵倒した自分が、激しく嫉妬しているのを感じた。嫉妬はやがて寂しさを伴った悲しみへ、さらにあきらめへと変ってゆく。夫へのあきらめばかりではない。自分の人生へのあきらめだった。夫は去り、息子は自立した。私は一人だ。房江の孤独を救える人はいない。
この孤独のなかで、房江は睡眠薬自殺を図る。何かの意思が働いたのか、房江の自殺は未遂に終わる。
「累々たる死と失敗と挫折」を経験して人は老いてゆく。その「死と失敗と挫折」を繰り返しつつそれを乗り越えて行く人間の逞しさを読み取るのが、小説を読む楽しさではなかろうか。
まちがいなく著者の集大成となるはずのこの小説の完成まであと一息である。
(かわにし・まさあき 文芸評論家)