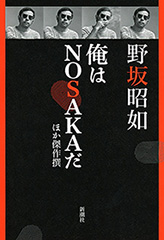書評
2016年9月号掲載
解放へと誘う想像力と音楽性
――野坂昭如『俺はNOSAKAだ ほか傑作撰』
対象書籍名:『俺はNOSAKAだ ほか傑作撰』
対象著者:野坂昭如
対象書籍ISBN:978-4-10-316611-5
この一冊で、野坂昭如の世界が周遊できる。
巻頭の二作目に、「骨餓身峠死人葛(ほねがみとうげほとけかずら)」のタイトルを目にして、背筋に電流が走った。じつは高校三年の時、私はこの小説を読んで、野坂昭如の「書生」になろうとしたのを思い出したからだ。当時の単行本には、巻末の著者紹介に住所までが載っていた。大谷石の立派な門構えの家だった。だが、すぐには呼び鈴を押せない。周囲を何度もめぐり、ついに呼び鈴を押した。だれも出てこない。勢いを得て、長く三度押した。何の応答もなかった。気が済んだのか、私は憑き物が落ちたように「書生」になることを放念した。当時の野坂昭如の執筆量を考えれば、呼び鈴に出るはずがない。いや、編集者を逃れるために呼び鈴のスイッチが切られていたかもしれない。
巻頭の「俺はNOSAKAだ」を読みながら、私は同時に、この小説について書かれた蓮實重彦の「S/Zの悲劇」を思い出していた。そこには、もちろんロラン・バルトの『S/Z』がこだましているが、当時、批評が面白くなりだしていた私には、構造主義や記号学の束縛からどう自由になるかを、具体的に教えられた貴重な批評だった。
小説じたいは、英訳された『エロ事師たち』を映画化したいという契約書にNOZAKAとサインしてしまい、領事館の書類のサイン証明にNOSAKAと書いてしまう食い違いに端を発する。本人が本人であることを、定められた方法で証明しなくてはならなくなるのだが、「俺」にとっては、単に弁護士を立て、制度的に処理すれば済む問題ではない。自分は本当に自分なのか、という問いに行き当たるからだが、すると、いまの自分が本当の自分ではなくなった時点を、「俺」は自分の過去に嗅ぎつけてしまう。それは、家も養父母も失った昭和二十年六月五日午前七時二十分の空襲の朝にほかならない。そのときに目覚め直せば、自分一人で六甲の山に逃げ延びずに、養母を抱え、養父に声かけ、ともに生き延びたかもしれない。アルファベットのサインの一字違いから、選び間違えたような自分の人生を生き直す不可能な試みが鮮やかにあぶり出される。そして、契約の不可能性と同時に人生の選択の可能性の束が見えてくる。フィクションの力であり、いま読んでも紛れもない傑作である。
図らずもこの二作は、私の野坂短篇ベスト2なのだ。三作目は、ホスピスという言葉も聞かない時代に、終末医療を図らずも実践してしまうぼろアパートの住人たちの悲喜劇を描く「死の器」。これを、一種の「徒党もの」と括れば、『とむらい師たち』や『ゲリラの群れ』、『騒動師たち』や『てろてろ』、さらにはデビュー作『エロ事師たち』の奇想天外で痛快な物語世界が見えてくる。
加えて、土地の来歴を濃厚な物語にしながら、そこにその場所のいまを持ち込み、原発誘致後の風景を描いた「乱離骨灰鬼胎草(らんりこっぱいおにばらみ)」など、八〇年代初頭に書かれていながら、歴史の先まで見据えていて、作家の想像力にただ脱帽するしかない。あるいは「俺はNOSAKAだ」の地続きとも言える自分のなかの他者という主題を、特異な警察官の物語に仕立てた「サムボディ・インサイド」、さらには終戦の年の八月十五日に、沖縄の洞穴で死を迎える少年を語る「戦争童話集沖縄篇 石のラジオ」と並べば、本書がどれくらい野坂ワールドのテンコ盛りかが分かる。
小説だけではない。「プレイボーイの子守唄」、「『山椒魚』の改変。大いに異議あり」、「拝啓 大島渚殿 先日の非礼をお詫び申し上げます」、「無敵の大人物田中角栄」と各時代を代表するエッセイが続けば、野坂昭如の生の軌跡が自ずと浮かび上がる趣向だ。これに坪内祐三との対談「文壇酒場と文壇の関係」が加われば、贅沢この上ない編集で、ほかに何をこの一冊に望むというのか。
ところで、「骨餓身峠死人葛」の何が私を小説家修業のための「書生」志願に駆り立てたかと言えば、その文体、とりわけ句読点の打ち方である。中学時代の教師に、志賀直哉を書き写せと言われ、じっさいに書き写して、まるで句読点の位置が自分と違うと落胆していた少年を、「骨餓身峠死人葛」の句読点は解放してくれたのだ。句読点など好きに打てばいい。だからいま、ゼミの学生たちに、「てにをは」がときどき抜けると説明して読ませれば、学生たちはこの小説の文の音楽性に魅了され、物語に奔放な想像力を発見する。それにしても、六〇年代後半から七〇年代前半の、野坂昭如の多産な黄金期の小説をもっと読みたいのは、私だけではないはずである。
(よしかわ・やすひさ 批評家・早稲田大学教授)