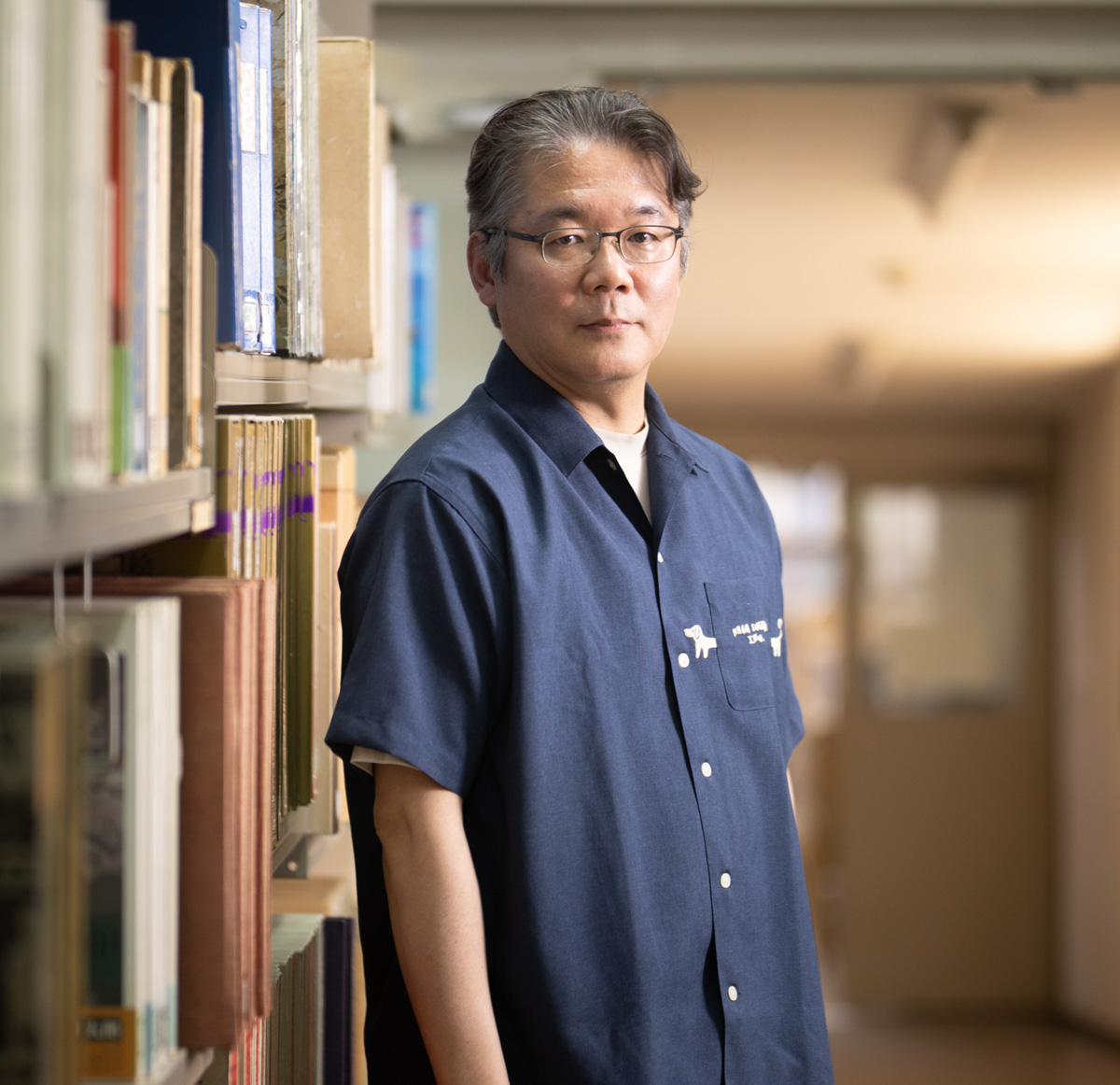インタビュー
2017年10月号掲載
藤原緋沙子『茶筅の旗』刊行記念インタビュー
二十年以上かかった卒業論文
――ライフワークを書き終えて
対象書籍名:『茶筅の旗』
対象著者:藤原緋沙子
対象書籍ISBN:978-4-10-139166-3

――長年構想をあたためていらした『茶筅の旗』、ついに刊行となりました。
藤原 心底ホッとしています。これを書かずに作家生活は終れないと思っていましたから。
構想を得たのはもう三十年近く前。その頃、私は作家を志しつつ、ドラマのシナリオを書いていました。ある時、歴史ものを書くための資料を探しているうち、茶の栽培から生産までを手掛けた宇治の〈御茶師〉に行き当ったんです。戦国時代、茶の湯が政治と強く結びついていたことはよく知られていますし、秀吉と千利休を題材にした小説も山ほどあるけれど、茶を生産する者までもが政治に巻き込まれ、戦場に駆り出されていたことは誰も書いていない。「絶対に私が書かなければ!」と決心したんですね。
――書名は御茶師たちが戦いに際し掲げた旗印に由来します。茶筅の絵が描かれていたことは史実だそうですね。
藤原 本来、戦いから最も遠い場所にある茶の道具が旗印になるというのはなんとも皮肉ですし、象徴的ですよね。
御茶師はただの生産者ではありません。大名家や禁裏との関係が深く、別格の権限を与えられ、苗字帯刀を許される者もいたほど。当主が代替わりしたら大名や旗本と同じように将軍に報告すべしともされていました。
その一方で、為政者から出陣の要請があれば応じざるを得ず、御茶師たちは戦いが起きるたびにどの陣営につくか頭を痛めたといいます。というのも彼らにはトラウマがあって、信長と将軍・足利義昭が争った槇島城の戦いにおいて、茶道の庇護者だった義昭側についたために、信長が勝利するや全員、宇治から追放されるという憂き目に遭っているんですね。後で呼び戻されたり、自力で畑を再開した者もいましたが、その記憶が彼らに凄まじい緊張を強いたのです。まとめ役だった上林家などは、どちらに転んでも家が存続するよう、息子の一人を豊臣方に、もう一人を徳川方に差し向けたほどで、生き残るための処世術は武家並みでした。
――そんな乱世を背景に、主人公の女御茶師・朝比奈綸の成長が描かれます。彼女の茶道の師である古田織部の失脚、そして小堀遠州への秘めた恋と失望が時代の厳しさを物語る。
藤原 女の御茶師がいたという史実はありません。ですが、史料に残るのは男の名前だけでも、その陰にはそれを支えて頑張っていた女たちが必ずいたはずです。
結局、今ある歴史は勝者と強者の歴史なんです。この小説に登場する古田織部にしても、なぜ家康に疎まれ、切腹を命じられたのかは、師匠の利休が秀吉に切腹させられた理由と同様、謎に包まれたまま。もちろん状況から想像することはできますが、敗者や弱者の真実は結局、歴史の中に塗り込められてしまう。私はそれを掘り起こして書きたいのです。
――確かにこの小説には多くの発見があります。
藤原 それは嬉しいですね。私が何より大切にしているのは、読者が「そうだったのか!」と思うような知識を小説に盛り込んで喜んでもらうこと。じつは私が大好きな藤沢周平さんの小説を読んでいて嬉しくなったのが、そういう瞬間なんです。たった一行でも、江戸時代にはこんな風俗があった、こんな言葉があったと知るのがたまらなく楽しい。だから私も安易な書き方に流れず、きちんと読者の期待に応えたい。そのためには歴史をきちんと学ばなければいけないと思い詰めて、立命館大学の史学科に入学したりもしました(笑)。
――失礼ですが、それはおいくつの時ですか。
藤原 四十代後半、もう二十年以上前ですね。社会人入学一期生でした。
――卒論は?
藤原 御茶師ですよ。私はこの小説を書くために史学科に行ったので、入学前から卒論のテーマは決っていたのです。
――えっ、この小説のために大学に!?
藤原 でも、もう一度同じことをやれと言われても絶対無理。特に語学には手こずりました。英語のクラス分けテストで、読み上げられる問題すら聞き取れずに難儀したのを思い出すと今でも笑ってしまう。
ただ、歴史小説、時代小説の場合はどうやって物事を調べていくかが基本ですので、史料のあたり方、見方を大学でしっかり身に付けられたのは本当によかった。だから、この作品は私にとって、二十年以上かけてやっと仕上げた卒業論文でもあるんですよ。
(ふじわら・ひさこ 作家)