書評
2017年10月号掲載
短期集中連載
ナミ戦記――あるリトルマガジンの50年史
①1967〜75
ある日、新潮社のKさんがニヤニヤしながら私のもとにやって来た。
「あのー、うちの『波』が今年で50周年なんですが、そのことをすっかり忘れていたんですよね」
私と同い歳のKさんは昨年6月号から本誌の編集長となった。その号の「編集室だより」に、彼は25年前の入社試験で「『波』に配属されたい」という希望を述べたと書いている。彼の、そして私が「地方都市に住んでいた十代の頃」、つまり1980年代の『波』には小林信彦や筒井康隆、大江健三郎の連載が載っていた。いわば、私たちの「本の世界」を広げてくれた雑誌だったのだ。その大恩ある雑誌の50周年を忘れていたって?
呆れていた私は、「で、ちょっとお願いがあるんですが......」という彼の話にさらに呆れることになる。1967年の創刊号から現在出ているまでの号をぜんぶ読んで、50年をふり返る記事を書いてほしいというのだ。しかも、2カ月半という短い間で!
「ナンダロウさんは今年で50歳で、『波』と同級生でしょう。何かの縁じゃないですか」と気軽に云うKさんに軽く殺意を覚えたが、「あんたも同級生だから、自分でやれば?」と抗えないのが、しがないライターなのだった。
それから2カ月、華やかな〈la kagū〉の裏に建つ、社内でもあまり知られていない「北別館」に通い、その一室に運び込まれた50年分の『波』のページを創刊号から最新の今年9月号までひたすらめくり続けた。ぜんぶで573号、合計ページ数は概算だが5万5200ページに上る。もちろん、全記事を通読できるわけもなく、メモを取りながら、面白そうな記事にざっと目を通すぐらいだったが、それでも10日間通うことになった。
とはいえ、それが苦行であったかと云えば、その逆だ。ページをめくるたびに、「この作家がこんな文章を書いていたのか!」「単行本で読んだアレは本誌に連載されたものだったのか!」など驚き、楽しんだ。あとでいくつか紹介するつもりだが、個人全集に未収録のエッセイや対談をいくつも発見した。また、中高生だった80年代に読んだ号でも、改めて読み直すと気づくこともあった。同世代の読者としてでなく、50年を通覧することではじめて判ることもあるのだ。もっとも、時間があればもっとじっくり読めたのにという悔いも残ったが。
今回から数回にわたって、主要な記事を紹介しながら『波』の50年をたどってみたい。ただし、どうしても私自身の興味が反映されるため、私的なクロニクルであることをお断りしておく。なお、著者名はすべて敬称略とする。
★創刊まで
『波』は67年1月に創刊されたが、これには前身となる雑誌があった。
53年12月に創刊された『Catalogue』で、「新潮社出版案内」というサブタイトルがついている。24ページで、最初は不定期、のちに季刊で発行された。新潮社刊行の全集や単行本を紹介しているという意味では、たしかに出版目録ではあるが、『三島由紀夫作品集』には中村光夫、ジャン・ジュネ『泥棒日記』には三島由紀夫の短評がつくなど読みごたえがある。別のところで書評したものを転載したのだろうか? それとも、本誌のために書いたものだろうか?

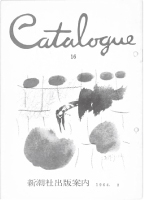
右は16号、左は21号
この『Catalogue』のことは、社史にもほとんど記述がなく、新潮社の社員でも存在を知らない人が多いようだ。資料室に保管されている同誌を眺めていると、思いのほか記事が充実していることに驚く。
翌年3月発行の第2号には、高橋義孝、亀井勝一郎、式場隆三郎の読書についての随筆を掲載。その後もこの形式が続く。三島由紀夫、竹山道雄、阿部知二、武者小路実篤、福田恆存、武田泰淳らが寄稿している。また、表紙裏には川端康成『山の音』の書き出しの原稿を載せている。この形式は初期の『波』にも受け継がれる。
9号(59年1月)からは、作家のゴシップ欄「ペン横丁」や消息欄「昨日今日」、「造本批評」などが新設され、雑誌っぽくなった。
余談だが、17号(64年6月)には、「タイ・アップ」として、田村泰次郎『肉体の門』、山本周五郎『樅ノ木は残った』など新潮社刊行書の映画化、テレビ、ラジオ放送を紹介している。タイアップという言葉がすでにこの時期から使われていたとは知らなかった。
そして、21号(66年7月)になると、24ページの半分以上が、『沈黙』を刊行した遠藤周作へのインタビュー、河盛好蔵「漱石と新潮社」、江藤淳「明治の文人」などの読み物になる。さらに22号(同年10月)には「注目の海外文学」として、大江健三郎によるノーマン・メイラー『大統領のための白書』、開高健による『チャップリン自伝』の書評を掲載。もはや「出版目録」の枠を大きく超えている。同誌が『波』に変わるのは、編集者からの「もっと記事を載せたい」という要請があったからではないだろうか。
『波』創刊号の「出版だより」には、「永らくご愛用いただいてきました『Catalogue』を、本号より『波』と改題しました。刊行は従来どおり年四回の予定です。新潮社と読者の皆さんを結ぶ雑誌として、『新潮社出版総目録』とともにご活用願います」とある。
なお、誌名の由来は説明されておらず、その他の資料でもなぜ『波』にしたのかは判らない。「新潮社」だから『波』という単純な連想から決まったのか。「それじゃ、岩波書店のPR誌みたいじゃないか!」という文句をつける社員はいなかったのか。大らかな時代だ。
ここで駆け足で、日本の出版PR誌の歴史を見ておくと、最も古いPR誌は丸善の『學鐙』だ。1897(明治30)年に『學の燈』として創刊。のちに内田魯庵が編集するようになって、読み物を多く載せた。次が岩波書店の『図書』で1938(昭和13)年に、それ以前のパンフレットを引き継ぐ形で改題された。この点は『波』に似ている。
戦後になると、59年にみすず書房の『みすず』、66年に集英社の『青春と読書』が創刊されている。
紀田順一郎は出版PR誌について、「自社出版物との直接的な関連性を意識した記事ばかりでなく、独立した企画性を発揮するリトルマガジンとしての編集方針」があると指摘している(「出版PR誌の時代 創刊五十年の『図書』とその周辺」、『図書』88年8月号)。『波』の創刊の動機は、まさにこの指摘にあてはまる。
★『波』検定
唐突だが、ここで『波』検定にチャレンジいただきたい。以下の問題にぜんぶ正解できた方は、長年の愛読者か、熱心な文学愛好家です。1問も答えられなかった方も、この短期連載を最後まで読めば、答えが判るようになっているので、ご安心ください。
第1問 日本で最初の出版PR誌は次のどれ?
a・波 b・図書
c・青春と読書 d・學鐙
第2問 『波』創刊号に執筆して以来、最も多く登場した作家は?
a・江藤淳 b・村上春樹
c・大江健三郎 d・三島由紀夫
第3問 『波』に掲載された対談が、冊子として挟み込まれたシリーズは?
a・純文学書下ろし特別作品
b・とんぼの本
c・新潮選書 d・新潮文庫
第4問 以下のうち、『波』連載ではないものを選びなさい。
a・井上ひさし『私家版 日本語文法』
b・山口瞳『居酒屋兆治』
c・筒井康隆『虚航船団』
d・小林信彦『おかしな男 渥美清』
第5問 現在も続いている「表紙の筆蹟」を最初に書いた作家は?
a・遠藤周作 b・川端康成
c・大岡昇平 d・小林秀雄
第6問 82年3月号の新潮文庫フェアで、坂本龍一とのツーショット写真が載せられた女性作家は?
a・瀬戸内寂聴 b・山崎豊子
c・田辺聖子 d・林真理子
第7問 89年5月号に広告が掲載されている、新潮社が発売した意外な商品は?
a・万年筆 b・ワープロ
c・学習机 d・ラジカセ
第8問 毎号書き手の変わるリレー連載。実際にはなかったものは?
a・私の中の日本人 b・私の友人
c・私のペン・ブレイク
d・私の好きな......
第9問 北杜夫が『波』で最後に対談した相手は?
a・阿川弘之 b・井上靖
c・辻佐保子 d・俵万智
第10問 2017年8月号で、黒柳徹子が読んだ弔辞「ここに立つのは私ではなくて」は誰に向けてのもの?
a・永六輔 b・野坂昭如
c・久世光彦 d・野際陽子
★読書人に向けて
前置きが長くなったが、いよいよ『波』の創刊号からめくっていこう。創刊号は24ページ(タイトル下の表紙のうち「波1」がそれ)。現在の5分の1の薄さだ。4号までの表紙は抽象画を使っている(3号に「表紙カット 山口源」とある)。69年春季号までは季刊である。
同誌が創刊された前年の66年、新潮社は創立70周年を迎え、同時に新社屋を落成した。この時期の新潮社の業績はめざましく、「書籍、文庫、雑誌が"三本柱"となって経営基盤を固め、新刊の倉庫に本が滞留することはなく、全国の書店から、追加注文が絶えなかった」(『新潮社一〇〇年』。この部分の執筆は高井有一)。
この年に刊行された文芸作品を挙げると、遠藤周作『沈黙』、吉村昭『戦艦武蔵』、石川達三『金環蝕』、井伏鱒二『黒い雨』と、いまでも読み継がれている名作揃いだ。
『波』創刊号の表紙裏には、前年11月に刊行された北杜夫『白きたおやかな峰』の原稿が載せられ、次のページには「作家の秘密」として北へのインタビューが載っている。
また、エッセイは福田恆存と大江健三郎。後者は「性的なるものと緊張感」というタイトルで、ル・クレジオの『調書』を論じている。「性と文学」というシリーズ名があり、2号では瀬戸内晴美(のちの寂聴)が「解放されない性のために」を書いているが、3号にはその欄は消えている。その代わり、「架空会見記」として、3号で遠藤周作がモーリヤックの作品のヒロインと、4号で開高健がジョージ・オーウェルと「対話」している。なかなかコーナーが固まらない感じだ。
「作家と読者のひととき」は、作家とその読者による座談会。3号で幸田文、4号で有吉佐和子を囲んでいる。どちらも全集や著作集に未収録のはずだ。熱心な読者を相手に、二人ともざっくばらんに作品の裏話を話しているのがいい。『華岡青洲の妻』は、北京に滞在中の有吉に新潮社の編集者が送った手紙がきっかけで生まれたという。ほかの作家でも読みたい形式だが、次号でのリニューアルによって消えてしまったのは残念だ。
当然だが、新潮社の刊行物については多くのページを割いている。
創刊号では「純文学書下ろし特別作品」シリーズが、北杜夫『白きたおやかな峰』で10冊になったことを知らせている。このシリーズは61年に石川達三の『充たされた生活』からはじまった。意欲的な長篇を雑誌連載ではなく書下ろしで世に問うという企画で、執筆中の作家の生活を安定させるために、最低保証部数を1万部と決め、印税を発行部数によるスライド制にした(『新潮社一〇〇年』)。完成までにはさまざまな困難もあったようで、予告とタイトルが変わることはザラで、刊行時期が大幅にずれたり、けっきょく刊行されなかった例もある。『波』の広告には、計画と実際に刊行されたものとのギャップが見えて興味深い。また、67年には新潮選書が創刊されている。
『波』には、自社出版物以外の書評も掲載されている。岩波書店の『図書』にも共通することだが、自社の出版物のいかにもなPRっぽさを嫌い、読書文化を広げようとする姿勢がうかがえる。この点について丸谷才一は、「その社で出した本をそのPR誌で褒めた文章はあやしい、くらいのことを思うに決ってる読者を相手にしているわけでしょう。だから、出版社のPR誌は本質的にものすごい矛盾を抱えているわけですね」と指摘する(丸谷才一・島森路子・三浦雅士「PR誌は出版社のステイタス・シンボル 東京ジャーナリズム大合評1」、『東京人』96年2月号)。
「最近の一冊」という欄では、新潮社刊行の井伏鱒二『黒い雨』を円地文子が、トルーマン・カポーティ『冷血』を柴田翔が評しており、他社の刊行物としては、後藤亮『正宗白鳥』(思潮社)を小林秀雄が、梅棹忠夫『文明の生態史観』(中央公論社)を小松左京が評している。リニューアルした5号からは「書評」と改題、会田雄次、大江健三郎、高坂正堯、司馬遼太郎、武田泰淳、中原佑介の6名が書評委員となった。
★三本柱と表紙の筆蹟
5号(68年春季号)からは64ページとなる。後半16ページは自社の出版案内とし、それ以前の48ページを読み物で埋めた。連載は、三島由紀夫「小説とは何か」、福原麟太郎・吉川幸次郎「往復書簡」、S・N・クレーマー「シュメール人」、遠藤周作「聖書物語」(のち『イエスの生涯』として書籍化)、円地文子「源氏物語私見」の5本。
巻末の中村光夫の短篇小説も連載だ。この連載が終了した際のインタビューで、中村は「『波』という雑誌は一般の批評からお目こぼしにあずかっているので、(略)稽古台にはとてもいいところだ、どんなことでも自由に書ける、それでやってみたわけです」と述べている(「わが小説の〈虚実〉」、『波』70年5・6月号)。
この中村の言は、この号の「編集室だより」で次のように書かれていることと一致する(署名は「宮脇」)。
「連載が多いのは、執筆の先生方に、ここで商業誌ではできぬ仕事をしていただきたいためです。読者がこの雑誌のバックナンバーをいつまでも保存して下さるようなものを掲載してゆきたいと考えています。ほかでは読めない個性のある純度の高いものが、『波』には載っているというイメージを持っていただくようになればさいわいです」
三島の「小説とは何か」は、まさに「ほかでは読めない個性のある純度の高い」小説論だ。自由な読書の中から生み出される知見は、豊饒で愉しい。柳田國男の『遠野物語』の一節に「あ、ここに小説があった」と感じ入るくだりが印象的だった。今回通読して気づいたが、84年1月号から87年12月号に連載された小林信彦「小説世界のロビンソン」は、(著者や編集者が意識していなかったにしろ)80年代版の「小説とは何か」である。
「小説とは何か」は、70年11・12月号の第14回まで掲載された。その回の最後の部分には「死の幸福」という言葉が見える。そして、三島は11月25日に自衛隊市ヶ谷駐屯地で演説したのち、割腹自殺を遂げた。次号の「編集室だより」ではその衝撃が続いていることが告白された。この号からはじまった保田與重郎の連載「方聞記」は、「三島由紀夫の死」を論じている。
表紙を作家の筆跡で飾るようになったのも、5号からだ。トップバッターは川端康成で、字は「風雨」。その後、丹羽文雄、井伏鱒二、小林秀雄、永井龍男、安岡章太郎とリレーされていく。2011年8月号には「500号記念特集 文士たちの筆蹟」として、43人の筆跡が再録されている。

なお、86年7月号(瀬戸内晴美)から99年4月号(坂崎千春)までは、本文ページに「表紙の言葉」として短文を載せている。なぜ、そんな中途半端な期間なのかは不明。表紙の言葉をやめた次の2号は、写真のみで筆跡すらなく、編集長の迷いがうかがえる。
69年7・8月号からは隔月となった。この時期から、長めのインタビューと対談が加わって、連載も含めた『波』の三本柱となる。このあたりで、現在の『波』につながるスタイルが確立したと云えるだろう。さらに、72年3月からは月刊化されている。
70年代の主要な連載はドナルド・キーン「日本文学を読む」(72年1・2月号〜)、江藤淳「なつかしい本の話」(75年7月号〜)、藤原審爾「遺す言葉」(75年8月号〜)、三木卓「昆虫のいる風景」(76年1月号〜)、倉橋由美子「小説論ノート」(77年8月号〜)、五味康祐「人間の死にざま」(77年9月号〜)、井上ひさし「私家版 日本語文法」(78年1月号〜)、阿刀田高「恐怖抄」(79年4月号〜)、灰谷健次郎「わたしの出会った子どもたち」(79年7月号〜)。いずれも完結後は書籍化された。
ひとつのテーマに沿って、複数の著者が書いていくリレー連載もあった。その最初は、71年1・2月号から開始された「私の中の日本人」だ。「筆者の日本観、日本人観を体現していると考えられる具体的な人物を軸に、(略)流動している日本人の魂の在所を探ってもらいたい」(「編集室だより」)という意図があった。辻邦生が「松尾芭蕉」、大岡信が「瀧口修造」、富岡多恵子が「深沢七郎」、森茉莉が「平野レミ」を描くといった組み合わせの妙がある。この連載は77年5月号(小田実「宮崎滔天と堺利彦」)で終了し、2冊にまとまった。
「この企画を考えたのは出版部長の新田敞(ひろし)さんです。『週刊新潮』の創刊に関わり、三島由紀夫、安部公房、司馬遼太郎、山本周五郎ら多くの作家に信頼されていました」と云うのは宮辺尚(現・新潮文芸振興会事務局)さんだ。70年に入社し、2年後に出版部に配属され、月刊化したばかりの『波』を編集した。同誌は、当時もいまも出版部に属している。宮辺さんの時代には、出版部の3人が編集を担当した。新田はその統括者だった。
「これから刊行される本のリストを見ながら、企画を決めていきます。新田さんから教わったのは、『ありきたりのことを考えるな』ということです。『私の中の日本人』のような企画は、著者にとっても編集者にとっても腕の見せどころでしたね」
このリレー連載は、その後、「作家の生活」(78年8月号〜)、「私のペン・ブレイク」(85年1月号〜)、「本のある日々」(90年1月号〜)、「私の好きな......」(96年2月号〜)などと、テーマを変えながら続いていく。お題を意識すれば何を書いてもいいというのは作家にとってありがたいし、編集者としても新刊を出した著者に登場してもらうのにちょうどいい舞台なのだろう。
柱の二本目は、対談。68年春季号の小島信夫・佐々木基一「恋愛小説の可能性」を皮切りに、吉村昭・新田次郎「取材・事実・フィクション」(70年5・6月号)、江藤淳・大江健三郎「漱石とその時代」(同7・8月号)など、ほぼ毎号掲載される。
ところで、「純文学書下ろし特別作品」シリーズを読んだことのある方は、その中に小冊子が挟まっていたことをご記憶だろうか。作者と評論家によるその作品についての対談だが、それらは『波』に掲載されたものを組みなおして冊子にまとめたものだ。69年7・8月号の椎名麟三・野間宏の対談「書下ろし『懲役人の告発』をめぐって」が、椎名の『懲役人の告発』に挟み込まれたのが、最初のようだ。
『波』の対談によく出ているなという印象があるのは、北杜夫、井上ひさし、筒井康隆らだが、ことに山口瞳は対談の名手だ。吉行淳之介との「対談の愉しみ」(74年10月号)で、吉行は気楽に読める対談を雑誌の「勝手口」と位置付けているが、山口には勝手口から相手の家に上がり込んで、胸の内を聞き出してしまうようなうまさがある。高橋義孝との「東京に生れ育って」(76年7月号)、池波正太郎との「縄のれんをくぐると」(82年6月号。『波』に連載された山口の小説『居酒屋兆治』について、池波が連載タイトルの『兆治』のままのほうがよかったと云っているのが、この人らしい)などは、『山口瞳対談集』全5巻(論創社)に収録されている。
最後の柱は、インタビュー。創刊号から北杜夫、小林秀雄、福田恆存、安部公房のインタビューが掲載されているが、各1ページの短いものだった。それが、69年9・10月号の安部公房へのインタビュー「根なし草の文学」では、6ページと大幅に増える。のちには、新刊についてだけに話が絞られるが、この時点では作家の文学観や生活について広く聞くものだった。この談話をまとめるのも『波』の編集者の仕事で、「ワープロもない時代だったので、まとめるのには苦労しました」と宮辺さんは云う。若手の編集者は大いに鍛えられたに違いない。
三本柱以外にも、『波』にはさまざまな記事が載っていた。次回は、70年代後半以降の誌面を覗いていこう。
(次号に続く)







