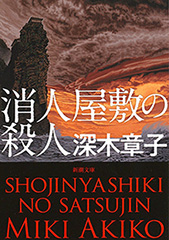書評
2017年11月号掲載
洗練を極めた騙しのテクニック
――深木章子『消人屋敷の殺人』
対象書籍名:『消人屋敷の殺人』
対象著者:深木章子
対象書籍ISBN:978-4-10-102051-8
二○一○年、『鬼畜の家』で第三回ばらのまち福山ミステリー文学新人賞を受賞してデビューした深木章子は、年一~二作ペースで極めて水準の高い本格ミステリを発表し続けている実力派作家だ。執筆活動に入る前は弁護士をしていただけあって、睦木怜弁護士が探偵役を務める『敗者の告白』『ミネルヴァの報復』などの作品では、法律の専門的知識が謎解きに密接に絡んでくるけれども、最新刊の『消人屋敷の殺人』では、同じ本格ミステリながら少々傾向の違う作風を披露している。
舞台となるのは、Q半島の中でも秘境と呼ばれる軽磐(かるいわ)岬の突端、絶壁の上に建てられた武家屋敷「日影荘」。昔からのこの地の有力者・日影一族の棟梁の隠居所として幕末に建てられたが、明治九年、ここで摩訶不思議な出来事が起きた。反政府の謀議のため集まっていた日影一族十数人が、屋敷から忽然と消えたというのだ――八十人ほどの官憲に見張られており、脱出など不可能だったにもかかわらず。
その後、日影家の手を離れたこの屋敷は、改修・補修が繰り返され、今では人気作家・黒碕冬華(くろさきとうか)の執筆用の別荘として使われている。黒碕冬華は男女二人の合作用ペンネームだとされているが、覆面作家である彼らの素性は版元である流星社の文庫編集長と担当編集者しか知らない状態だ。
黒碕冬華の本を読んだ大学生の幸田真由里は、その正体は小説家になるという夢を貫くため家を出た兄の淳也ではないかと考える。兄のパソコンに保存されていた小説の内容が、黒碕冬華の作品とそっくりだったからだ。アパートを借りる際に淳也の連帯保証人となった新城篤史という人物の兄にあたるフリーライターの新城誠に出会い、意見を交換した真由里は、黒碕冬華とは幸田淳也と新城篤史の共同ペンネームだという結論を出す。だが、デビューの三カ月後、淳也と篤史が揃って姿を消したことは解せない。そんな時、真由里のもとに黒碕冬華からの招待状が届き、彼女は誠とともに日影荘へと向かう。日影荘には彼らのほか、大手出版社・文芸評論社の女性編集者もやってきたが、そこに暴風雨が到来し、思いがけない惨事が......。
外界から孤立した屋敷という典型的な「嵐の山荘」シチュエーションのミステリであり、五人の人間が見ている前での家政婦消失など奇怪な出来事が相次ぐけれども、この種の作品としては、なかなか殺人事件が発生しないなどパターン破りな部分が幾つもある。作中人物が指摘するように、犯人が自然災害の発生まで予測できた筈がなく、つまり自力で「嵐の山荘」を作るのは不可能だったことや、もし殺人を目論んでいるのなら被害者候補にわざわざ警戒させるかのように電話線を切断したことなども不可解だ。そうしたさまざまな違和感を押し流すかのように、物語は登場人物たちの疑心暗鬼がエスカレートする中、怒濤の勢いで進行してゆく。
現代的に改修され、インフラも設備されているとはいえ、日影荘は幕末の武家屋敷の面影をとどめている。中盤からは、密閉度が低く、たやすく敵の侵入を許しそうに見えつつ実は住人にとっても逃げ出しやすい......という日本家屋の特色を前提とした頭脳戦が展開される。舞台設定をとことん生かしたストーリーテリングも本書の大きな読みどころだ。
さて、登場人物がひとり、またひとりと退場し、いよいよ真相が明らかになったかに見えたその数ページ後、更に裏に秘められていた別の企みが暴かれる。そこまで読んだ時、私は一瞬何が起こったのか理解できず、「もしかして、とんでもない読み落としをしたのでは......」と肝を冷やした。しかし、それに続く種明かしのくだりで、この大逆転のために著者がいかに細心の注意を払って本書を執筆してきたかが判明する。実は原理だけ取り出せばありふれた仕掛けと言えなくもないけれど、隅々まで巧妙に構築されるとマニアでも騙される好例と言えよう。
本書は、著者が得意技である法律の専門知識を封印しても見事な本格ミステリを書けるということを証明した作品であり、洗練の極みとも言うべきテクニックを堪能できる。心地よく騙されたいひとにお薦めだ。
(せんがい・あきゆき ミステリ評論家)