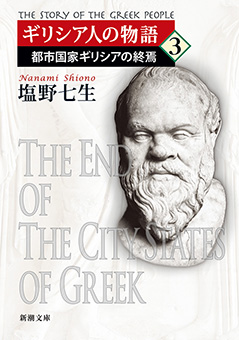書評
2018年1月号掲載
騎兵と歩兵、そして政治と人間
――塩野七生『ギリシア人の物語Ⅲ 新しき力』
対象書籍名:『ギリシア人の物語Ⅲ 新しき力』(新潮文庫版分冊『ギリシア人の物語3―都市国家ギリシアの終焉―(新潮文庫)』『ギリシア人の物語4―新しき力―(新潮文庫)』)
対象著者:塩野七生
対象書籍ISBN:978-4-10-118114-1/978-4-10-118115-8
ともかく面白い本であった。著者の「ストーリーテラー」としての語り口が抜群であり、その魅力に引き込まれて私は大冊を一気に読了した。
さて、私個人はといえば、十二歳のアレクサンダーが大人の誰もが乗りこなせない怪馬ブケファロス(牛の頭の意)を見事に統御し、その馬と最後のヒダスペス会戦(二十九歳)まで共に戦い一度も負けなかったというところに最も感動した。やはり大王の武人としての本質は戦場に機動をもたらす「騎兵」であり、しかも短命ながら極めて運の良い人であったということが、元自衛隊機甲隊員、即ち騎兵の末裔と自負する私を虜にしたのである。
「歩兵戦に対するものとして騎兵戦というものが存在する。敵の肉体に直接打撃を与えつつ逐次にその抵抗力を奪っていくのが歩兵戦の姿とすれば、騎兵戦は敵の神経中枢に一挙に踏み込んで、一瞬のうちに敵を麻痺打倒するのをその理想の姿とする。このような騎兵戦はかつてアレクサンダー、ハンニバル、スキピオ等によって華やかに用いられたが、シーザーの『歩兵の熟練』から始まるローマ軍団の時代には、決戦兵種として用いられず逼塞していた」と英国の軍事評論家リデル=ハートは一九二七年に出版した『近代軍の再建』の中で述べている。そして、その後戦場における歩兵と騎兵の主導権争いには紆余曲折があったものの、連発銃・機関銃・大砲等火力の増大の前に騎馬が機動性を失った現代、騎兵に対抗する手段を踏みにじる装甲モーター(即ち戦車)は騎兵史にとってまことに偉大なものになるだろう、という意味のことを続けている。リデル=ハートの「近代軍の再建」とは同時に「戦場に機動をもたらす騎兵の再建」なのであった。
しかし戦場に機動をもたらす騎兵とは「寡を以て衆に勝つ」きっかけをつくる、即ち相撲の「前捌き」にあたる騎兵のことなのか、それとも「衆を以て寡を圧倒する」、即ち「本腰」にあたる騎兵のことなのかについて彼は明言していない。
私が『近代軍の再建』を読んだ一九六〇年代の日本では「戦車不要論」という風が吹いており、四面楚歌の機甲職種にいた私は生意気にも「日本でも騎兵の再建を」と呟いたのだが、権力ある人々には無視された。その後「戦車不要論」は益々勢いを増し、かつて千二百両あった戦車定数は三百両に削減されている。本腰に使う戦車が無くなった以上、前捌き用の戦車・装甲車を増加し偵察警戒部隊を強化しようと機甲隊の後輩たちが努力し、それが近く実現されると聞く。米軍では三十年も前に空中騎兵と装甲騎兵のコンビが確立されているのに、遅きに失した話だが先ずは一歩前進である。そして逆に、自衛隊の本腰の弱体化が問題となる。
アレクサンダーの騎兵隊の隣にはいつも父フィリッポス二世が錬成した精強な歩兵(人数的には常に主力)がいて、その歩兵との協力の下に騎兵が「寡を以て衆に勝つ」決め手となり得たのである。アレクサンダー自身が優れた歩兵であったことも忘れてはならない。
この騎兵・歩兵の問題の他に、多くのことを私は本書から学んだ。若い頃に悩んだ「海洋国家日本に陸上兵力は要るのか」「自衛隊は国民軍か傭兵か」「兵員補充・募集困難の常態化」「戦費調達の困難性」「持続的兵站の可能性」「国民・地元住民・外国軍との交流・協力の在り方」等々については二千五百年を隔てても変わらぬ難問であることを承知したが、やはり最大の問題は①部隊統率、②国内の統治(政治)、③外国・外国人との協調(外交)だということを教えられた。
米国大統領の安全保障担当補佐官、マクマスター陸軍中将は「ベトナム・アフガン・イラク戦を通じ米国政府は戦争をテクノロジーで解決できると考えてきたがこれが間違いであった。戦争は昔も今も政治的で人間的なものである」と言っている。
自己・自国ファーストの蔓延で、やや分裂ぎみの現世界だが、アレクサンダー・シーザー・ナポレオン(=クラウゼヴィッツ)に通ずるこの正道に戻るべき秋(とき)なのであろう。無論、「哲人王」も「真の民主主義」もあり得ないが、「無政府主義」・「一国平和主義」はもっとあり得ない時代なのである。
著者は都立日比谷高校で私と同じ一年生であったらしい。そのことは後に知ったことで、私は当時の「地中海を夢見る乙女」を全く知らない。当然、進学校の「落ちこぼれ」であった私を著者も知らなかったであろう。アレクサンダーという今に影響を残す歴史上の人物について、本書を通じ軍事・政治・人間に亘る「夢と現実」を語り合えたことは幸運であり光栄であった。感謝の心をこめて。
(とみざわ・ひかる 軍事評論家)