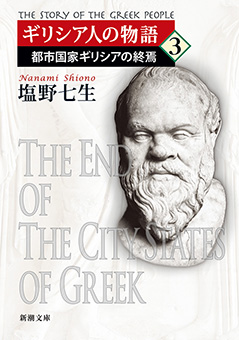インタビュー
2018年2月号掲載
『ギリシア人の物語Ⅲ 新しき力』刊行記念特集 インタビュー 後編
作家は自分を捨ててこそ生きる 後編
聞き手 伊藤幸人(新潮社取締役)
50年もの長きにわたって作家生活を送ってきた塩野七生さん。歴史を書く上でもっとも大切なこととは何だったのか――。また、仕事をともにしてきた、忘れられぬ人々の横顔を語ってもらった。
対象書籍名:『ギリシア人の物語Ⅲ 新しき力』(新潮文庫版分冊『ギリシア人の物語3―都市国家ギリシアの終焉―(新潮文庫)』『ギリシア人の物語4―新しき力―(新潮文庫)』)
対象著者:塩野七生
対象書籍ISBN:978-4-10-118114-1/978-4-10-118115-8

(前篇はこちら)
――今作のあとがきにも書いておられますが、塩野さんは「中央公論」の編集長・粕谷一希さんと花形編集者だった塙嘉彦さんに見出される形でデビューを果たしたわけですが、お二人だけではなく、文藝春秋であれば社長にもなった田中健五さん、そして新潮社でいえば常務・新田敞(ひろし)という、私にとっては仰ぎ見るような大先輩と、塩野さんは仕事をしてきました。
塩野 彼らに加えて新潮社の先代の社長(佐藤亮一)ね。彼らはみんな私の年上なんです。だからちょっと甘ったれて付き合えるような感じがあった。新田さんに「売れない」ってボヤいたら、「だいたい君は売れるように書いているのか」なんて言い返されました。「いや、そういうわけでもないです」としか答えられなかった(笑)。「そのうち売れますよ」なんていなされましたね。粕谷さんにもよくお説教されました。デビュー作である『ルネサンスの女たち』には四人の女が登場するわけですが、その三人目「カテリーナ・スフォルツァ」の原稿を編集部に渡したところ、長いというので粕谷さんが二回に分けて掲載した。それで私が「あれは分断されたら困る」と抗議したら、「『中央公論』は原稿用紙にすれば全部で一千五百枚ぐらいだが、君の一篇は百五十枚もある。君に雑誌の十分の一をやるわけにはいかない。自分を中心にして世界が回っていると思ってはいけないよ」なんて叱られました。はじめはそういう編集者たちと仕事をしていた。そしたら、その人たちが全員なぜか同じ時期に社長になったり、偉くなったりしたものだから、各社とも若いのが担当になったというわけ。その中の一人があなたなんだけれど、困っちゃったわよね。
――そうでしょうね。まだ右も左もわからない若僧でしたから。前回も少し触れましたが、塩野さんとのお付き合いももう三十五年。私が二十八歳の時以来です。少し思い出話をさせて下さい。
編集者との悪戯
塩野 担当になった時、あなたはずいぶん年下でね。そのときに思ったのは、若い叔母さんと甥は何でも話せる仲だというけれど、その線でいくしかないと思いました。いまだにあなたのことを、クン付けで呼んでしまうのはそのせいね。あなたはいまや重役でもあるわけだけれど、まあ一人くらいはクン付けで呼ぶ人がいたっていいじゃないですか。
――親子というほどには離れていないし、弟にしては離れている年齢という間柄です。編集者とはいかにあるべきかをずいぶん教えられたと思います。当時は「新潮45+」という雑誌の編集部にいたのですが、初めて受け持ったのが塩野さんの「サイレント・マイノリティ」という連載コラム(現在は新潮文庫刊)。この連載で私は大ミステイクをしているんです。一九八三年三月のことですが。覚えていらっしゃいますか。
塩野 そんなこともあったわね。
――受け取った原稿に「凡なる一将は、非凡なる二将に優る」という言葉があったんです。ナポレオンの言葉ですが、指揮系統の一本化はそのくらい大事なことなんだと、ナポレオンは言いたかったわけです。ところが私は何を勘違いしたのか、変だなと思ってしまった。
塩野 それで、あなた、直したのよね。私に断らずに。「非凡なる一将は、凡なる二将に優る」と。
――その直後に「非凡なる一将は、凡なる二将に優る」とも書いておられるし、つい何かの書き損じかなと思ってしまったんですね。常識的に考えれば、この方が正しいに違いないと思いこんでしまったのです。国際電話をかければいいんだけれど、通信事情が今ほどよくない時代のことです。塩野さんも国際郵便で原稿を送ってくれていた。ファックスさえもまだない。
塩野 「凡なる頭脳で非凡なる文章を直すな」って怒ったわね(笑)。でも喧嘩は一度もしなかった。
――そうなんです。塩野さんはあまり怒りが長続きしない方なので(笑)、その大失敗をした後にも、いろいろと面白い仕事をしていただきました。まずは中曽根内閣の官房長官だった後藤田正晴氏に二人で会いに行って単独インタビューをしているんですね。後藤田さんは新聞の記者会見には応じるけれど、個別の対談やインタビューには一切応じない人で、ベールに包まれていた。
塩野 たしかイタリアから一時帰国している最中で、連載を休ませてほしいって言ったのよね。そしたらあなたが「それは困る」というから、「じゃあ対談ぐらいならばする」と。で、「じゃ、誰とやりましょう」とあなたが言うから、「うーん、そうね、後藤田さんあたりはどう?」って。
――ますます困ったのを覚えています。なにしろ個別取材には応じない恐い官房長官だというので有名でしたから。「そんな非現実的なこと言わないでください」って。
塩野 そうそう。でも会ってみるとけっこういろいろ話してくれたじゃない。
――後藤田さんがこんなに自分自身のことをあけすけに語ったのは珍しいと思います。
塩野 「新潮45+」ではほかにも対談をしたと思うんですが。
――そうです。当時の市民運動のプリンスだった江田五月氏と共産党の法律顧問だった弁護士の石島泰(ゆたか)氏。
塩野 石島氏の時はね、われわれはちょっとばかり策を練ったわけ。相手は共産党だと。よし、ならば舞台装置はブルジョアでいこうと。
――対談場所としてホテルオークラの部屋を用意しました。
塩野 シャンパンも用意しなさいって言ったんだったわね。
――なぜこの弁護士が注目を浴びたかというと、左派の弁護士にもかかわらず、田中角栄のロッキード裁判を批判したんです。ゴリゴリの共産党シンパが「田中角栄裁判というのは問題だ」と。実際あの裁判は確かに検察が無理をしているところがあった。で、その人に好きなように語らせたんですね。そしたら、しゃべり過ぎちゃったんです。共産党関係者としてはまずいことも、いろいろと。
塩野 そうだったわね。
――もう塩野さんに乗せられて、どんどんしゃべる。で、原稿ができて見せにいったら、ほとんどどこも使うな、ボツだって言い始めた。だけど、それはダメですと。実際にしゃべっているんだから。そんなのダメだと言って、載せました。
塩野 あのときは新田さんが英断を下したんですよね。「いや、このまま載せましょう」って。あれで当時の共産主義者の化けの皮を剥いだわよね(笑)。
仕事仲間に求めること
――私がまだ三十五歳で、編集長として「フォーサイト」という雑誌を創刊することになったときのことです。不安でいっぱいだったんですが、相談すると塩野さんは「あなた、部下を選んではいけない」とおっしゃった。で、その先がすごい。カエサルはまさにルビコンを越えんとするとき、彼がもっとも信頼する子飼いであるはずの第十軍団が来ていなかった。彼らを引き連れてルビコンを渡り、ローマに侵攻しようと考えていたんだけれど、現実には子飼いではない第十三軍団しかいない。しかし、もう時、満ちたりと。それで例の「賽は投げられた」となるわけです。ポンペイウスを中心にした反カエサル包囲網が作られていて、一刻もはやくローマに行かなければならないという状況ですから、カエサルは迷わず第十三軍団とともにルビコンを渡ったというんです。だからあなたも、部下を選んではいけない、と。この壮大な比喩には痺れましたね。塩野さんは若い人間へのアドバイスが本当にお上手です。
塩野 そんなことないですよ。私も楽しく仕事をしているわけだから、私の仕事に協力してくれる人たちにも楽しんでほしいと願っているだけのことです。楽しく、面白がって仕事をしていると、意外に成功しちゃうものですから。私もこうして五十年もこの仕事を続けられたのは、真面目なことばかりやってきたわけではないからかもね。
――相当な悪戯もしてきました。
塩野 編集者たちには悪いなとも思うのよ。なにしろこちらの頭がまだ整理されていないときに、長電話に付き合わせるでしょう? しかも長電話で話していたことが原稿になったときは、まったく違った形になっていることさえある。
――原稿にならないことだってありますしね。
塩野 でもね、対話っていうのはすごいものなんですよ。私があなたに話すわね。そして意が相手に通じる、それだけじゃないんです。自分の中で整理していくわけ、話しながら。司馬遼太郎先生はすごくおしゃべりだったと聞きますけれど、きっとご自分の中で考えを固めていったんじゃないかしら。黒澤明もおしゃべりだった。話しながら整理しているんだと思うんです。
――われわれは時には二時間、三時間と長電話することもありますね。
塩野 編集者はやっぱり原稿を書く上ではもっとも重要な協力者ですから。まだまだ粗の多い草稿を送った時なんかは、あなた方も文句があるでしょうけれど。でもいちいち粗探しをされるとゲンナリしちゃうわけ。だけど、パッと一つだけ何かいいことを言ってくれるだけでね、頑張ろうという気持ちになる。今でも覚えています。中央公論の塙さんの言葉ですが、「われわれは君が書いてる史実の結末を知っている。しかし、それでも読んでるうちに、サスペンスを感じる」と。そういうようなことを言われるとね、なんだか水をつけられたって感じで、お餅をつく手が元気づくのです。私にとっての一番いい編集者はそれです。餅つきの合いの手を入れてくれる人。
完璧な白紙になる
――『ギリシア人の物語』に話を戻しましょうか。
塩野 最近思うことですが、理論的に言えばウィキペディアとAI(人工知能)を組み合わせればローマ史もギリシア史も書けるかもしれません。しかし、実際は書けないでしょう。というのは、ある資料をどう読み込み、解釈するかというのは、やっぱり書く人間次第なんです。なにしろ古代に関していえば資料というのはだいたいもう出揃っていて、上限は決まっている。つまり、決めるのはデータの量ではない。学者が書く歴史よりも作家が書く歴史が面白い理由はね、両者とも勉強することでは同じなんですが、学者たちはその過去のデータに囚われるからです。それに対して作家というのは過去のデータ、つまり資料の一行をどう読み込むかに自分の全精神、生命をかけるわけです。
――学者でも作家でも人工知能でも、取り扱う資料データは一緒ですよね。公開されている情報です。
塩野 ええ。でも集めただけではダメ。読み込む必要がある。そして作家にとって一番面白い対象は人間です。でも学者はそうではない。人間に対して感情移入してはいけないことになっている。歴史の教科書から坂本龍馬だとかハンニバルが消されそうだと聞きますけれど、どうかしていると思います。歴史はやはり人です。
――ハンニバルでいえば、彼は戦地で野営するときに、ほかの兵士たちとともに地べたで眠り、兵士たちがそっと彼に毛布をかけたという話が『ローマ人の物語』に登場します。これは公開資料に書かれていることですよね。学者は注目しないけれども、作家はそこからするどく何かを持ってくる。
塩野 佐藤優さんが言っていたことだと思うんだけれど、インテリジェンスも結局は公開資料がもっとも大事な情報源だって。歴史も同じです。
――大事なのは公開資料をどう読み込むかですね。
塩野 将棋の羽生善治さんがどこかで言っていましたが、われわれの頭脳と人工知能のどこが違うかというと、「汎用性」という言葉を彼は使っていました。つまりデータや資料が、誰にでもアクセスできる状態で、ある。しかし、そこに変なものをつなげたり、思いもよらないものと組み合わせることができるのが、われわれの頭脳だということなんです。歴史を書くときも同じです。大事なのは書く人間がどう公開資料を解釈し、組み合わせるかということです。
――なるほど。
塩野 とはいえ解釈ありきで資料そのものはないがしろにしていいということではありません。解釈を過信してはいけません。歴史や史実に対しては常に謙虚でなくてはいけない。「蟹は自分の甲羅に似せて穴を掘る」という言葉があります。つまり、塩野七生なんてつまらない女なのだから、私に合った穴を掘っていたら、小型の蟹しか入ってこないことになっちゃうでしょう。だから私は、この男を書くということだけ決めたら、あとは白紙なんです。書きたい対象を前にして、私は完璧な白紙になるの。だから、塩野七生のオリジナリティだとか、塩野七生の文体とか、そんなことは知ったことではない。自分の独自性を発揮しなきゃと思うと、本当に苦労すると思います。
――若い作家が陥りがちなところかもしれません。
塩野 現代の美術はパワーがないと私は思っていますが、それは独自性を求め過ぎだからだと思います。私はすべてのものは独自性を求めたときに、純なるパワーが失われると思ってます。少しばかり刺激的な比喩を持ち出しますが、男と恋愛するのが嫌、ベッドインするのが嫌だっていう女性がいますよね。彼女たちの言い分は、そういう関係になると主導権を失って、自分の個性が損なわれるからということなんだと思うんですが、私から言わせたら、そんなことで損なわれるような個性は個性ではない。愛した男の前で白紙になることを畏(おそ)れてはいけません。それにね、「死んで生きる」という考え方があると思うんです。
――死んでこそ、生きるということですか。
塩野 ええ。死んでこそ生きる。私は自分、塩野七生を捨てるわけですよ、書くたびごとに。
――そうすることで対象が生きる。生かす。
塩野 そう。そしてその対象を生かすことによって、私がまた生き返るわけ。塩野七生なんてたいした女ではないけれども、惚れる相手、選ぶ男には少しばかり自信があります。だから、今度の男アレクサンダーも魅力的なはずですよ。
(しおの・ななみ 作家)