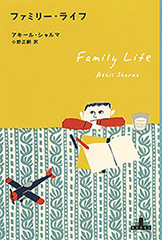書評
2018年2月号掲載
本当に祈るということ
――アキール・シャルマ『ファミリー・ライフ』(新潮クレスト・ブックス)
対象書籍名:『ファミリー・ライフ』(新潮クレスト・ブックス)
対象著者:アキール・シャルマ著/小野正嗣訳
対象書籍ISBN:978-4-10-590143-1
歩道にあるパーキングメーターのそばを通り過ぎるたび、コインを入れるための金属のポールに触れる少年がいる。さりげない一瞬の仕草に気を留める人は、たぶんいないだろう。ましてやそれが少年にとっての祈りであり、神との対話であるということになど、誰も気づいてはいない。
少年は家族とともにインドのデリーからアメリカへ移住してきた。栓をひねればお湯が出る、ボタン一つでエレベーターが動く、郵便受けにカラーのチラシが入る等々、生活のあらゆる局面で出会う豊かさに圧倒され、テレビと図書館の偉大さに感動しつつ、徐々に新しい地に馴染みはじめた頃、事故が起こる。最難関の高校に合格したばかりの兄ビルジュが、プールの底で頭を打ち、寝たきりの状態に陥ったのだ。呼吸のできなかった三分間が、"人々の内にある真実を見通す"ほどに優れていた兄の脳を、取り返しがつかない状態にまで破壊してしまった。以降、両親と弟は、事故の意味を問い続ける人生を歩むことになる。
突然に降りかかってきた現実と格闘する弟の"僕"は、さまざまな感情に翻弄される。事故の当日、母に冷淡な子だと誤解されないよう、「僕はもう泣いたからね」と言う。面倒を起こした兄に腹を立てる。間違った人生を与えられたような疎外感を覚える。友だちにより正しく現実を知ってもらうため、嘘をついて理想の兄をでっちあげる。激しく泣きじゃくってどうしようもできなくなった時は、自分自身から抜け出す。そして自分の不幸が、"僕"の中に戻れるよう、そばで待っているのを感じ取る。
特に印象に残るのは、彼が自ら編み出した神様(のようなもの)と対話する場面だ。神様は形式にこだわらない、大らかで話しやすい雰囲気を持ち、容貌はクラーク・ケントに似ている。それは図らずも、両親にも友だちにも言えない心の内を、初めて言葉にする機会となる。そこで彼は、おそらく本人も意識しないままに、本質的な真理を口にする。
「ビルジュの事故が無駄になるのはいやなんです」
するとこんな答えが返ってくる。
「あの子は忘れられはしない」
信仰の枠を超え、兄を思い、苦悩することがそのまま、彼にとっては祈りになった。"命を得るためにコインが投じられるのを待って"いるパーキングメーターのポールに触れるのも、兄に命を授けてほしいと願う祈りだった。
やがて中学生になり、ヘミングウェイの伝記を読んだ経験から、"僕"と言葉の関わりはより深い意味を持つようになる。作家になりたいと思うのは、兄たちから離れた遠い場所へ自らを運ぶようなもので、それは不誠実ではないかと感じながらも、書くことが自分を変え、守ってくれる事実は誤魔化しようがなかった。
しかも彼が書こうとしたのは、漠然とした自らの内面ではなく、具体的な輪郭を持つ一場面であった。例えば、朝、兄を入浴させる父のパジャマが、ひどく濡れ、下着が見えるまで透明になってゆく様、といったような。
作家になる前から彼は既に、言葉にできない本当に大事な心の内は、外側のささいな一瞬に現れ出るということを知っていたのだ。
小説の後半、父のアルコール依存症がどんどん深刻化する。母の偏狭さも度を増し、両親はすさまじい夫婦喧嘩を繰り返す。しかしこの家族は、決定的にすべてを破壊してしまうところまでは落ちてゆかない。最後の最後で踏みとどまる。その究極の歯止めになっているのが、彼らが皆、ビルジュを愛している事実である。単純だけれども崇高で、最も難しい愛が、彼らを救っている。家族は各々、自分にしかできないやり方で、ビルジュのために祈り続ける。
大学に進学するため"僕"は家を出る。ダイニングルームの介護ベッドに横たわっている兄と別れ、自分の人生を歩みはじめる。投資銀行に就職し、猛烈に働いて高給を稼ぎ、弁護士の女性とリゾート地でバカンスを過ごす。しかし世間的な幸福は彼に喜びをもたらさなかった。小説は、袋小路に迷い込んだかのような一行で終わる。しかしそこには微かな未来が予言されている。彼には書く道がある。文学の放つ光が、彼を照らしている。
(おがわ・ようこ 作家)