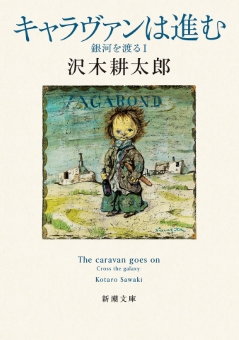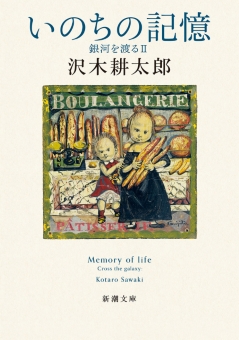書評
2018年10月号掲載
踏切の一瞬
――沢木耕太郎『銀河を渡る 全エッセイ』
対象書籍名:『銀河を渡る 全エッセイ』(新潮文庫版『キャラヴァンは進む―銀河を渡るⅠ―』『いのちの記憶―銀河を渡るⅡ―』)
対象著者:沢木耕太郎
対象書籍ISBN:978-4-10-123536-3/978-4-10-123537-0
将来の夢は、と問われて何も答えられなかった中学二年の頃、沢木耕太郎さんの『一瞬の夏』を読み、初めて何かと出会えたような気がした。誰かと会い、話を聞き、書くこと。自分もそんなふうに生きることが出来たら、と漠然と考えるようになった。
大学三年になり、間接的、断片的にでも沢木さんの仕事に関わりたいと思った。アルバイトとして雑誌「SWITCH」の編集部に入り、日夜働くようになった。
今にして思うと信じ難いことだが、現像された写真を届けたり、原稿を受け取ったりという役回りで沢木さんと会う機会にも恵まれた。
目の前に沢木耕太郎がいる、という体験は凡庸な学生にとって革命だった。生きることの不思議さ、面白さ、可能性を信じる上での立脚点になった。
新聞記者になって十六年。三十八歳の「余儀ない旅」を強いられる自分にとって、今、本稿を書いている瞬間も、世界のどこかで「夢見た旅」を続ける人の鼓動を想像することは励ましであり、どこか支えでもある。
十五年間も待ち望んだ一冊である。1982年の『路上の視野』、1993年の『象が空を』。過去十年を編む全エッセイ集の第三の続編を2003年から待っている間に、四半世紀を括る書物になっていた。沢木さんらしい企みとも思える。
色川武大を悼むためにマカオでバカラのテーブルに座る。衆院議長公邸で旧友と会う。残してきた心を取り戻すためにマラケシュへと向かう。金メダルを得た直後の野口みずきに高橋尚子について聞く。モハメッド・アリの拳を眼前で見つめる。冬の夜の帰路で今川焼を頬張る。自前の御伽話で寝かしつけていた娘から、長い時を経た後でモーニングコールを頼まれる。ハワイで完璧な休日を過ごす――。
旅する地球の広さという横軸に、二十五年分も積まれた歳月という縦軸が交差し、沢木耕太郎の世界は拡大し続けている。移動する視線と肉体による守備範囲は無限で、一介の記者である私について書かれた一編すら存在する。当時二十六歳の若造が犯した痛恨の失敗を沢木さんは救ってくれた。大胆にも程がある私の依頼を優しく受け入れることによって。
高倉健らへの惜別の終章「深い海の底に」は永い余韻を残す。幼馴染であり、あの『一瞬の夏』を並走したカメラマンである内藤利朗さんへの弔辞には、生きる上で極めて大切なことが綴られていると思う。
本書のタイトルを聞いて、思い出した光景がある。
2005年夏の夜、東京・自由が丘の路上でのこと。同年2月に出版された写文集『カシアス』の刊行を祝う食事会が終わった後、沢木さん、内藤利朗さん、担当編集者であるSWITCH編集長の新井敏記さん、アシスタントやセールスで携わった数名の女性編集者、さらには無関係のはずの私で駅向こうのバーに向かって歩いていた。
踏切の警報音が鳴る。まだ線路まで微妙な距離が残されている。十人いたら八人はステイを選択する局面だったが、沢木さんは背後を振り返り、我々に「走ろう」と告げた。
微かなワインの酔いの中で、それぞれに走った。沢木さんも、内藤さんも、新井さんも、そして私も。
踏切を渡り終えた後で、少し息を切らした女性編集者は「も~! 沢木さん!」と笑いながら言った。みんな声を上げて笑った。行動する彼は悪戯好きの少年のような表情を浮かべていた。
何気ない一瞬だったが、私の心はなぜか震えていた。今、俺の目の前にいる人に憧れて俺は歩み始め、憧れながらこれからも歩み続けていくんだな、と。前を行く背中を追いながら、ずっと考えていた。
今も鮮明な映像が浮かぶ。踏切へと駆け出した沢木さんの足取りは、急ぎもせず焦りもしていなかった。大丈夫だよ、平気だよ、とでも伝えるように。悠々として力感のない、銀河を渡るようなステップだった。
(きたの・あらた 報知新聞記者)