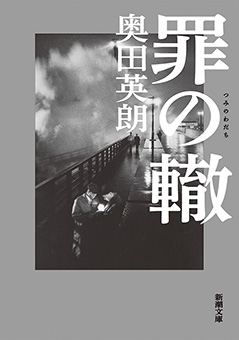書評
2019年9月号掲載
見事に再現された東京五輪前年の東京
奥田英朗『罪の轍』
対象書籍名:『罪の轍』
対象著者:奥田英朗
対象書籍ISBN:978-4-10-134473-7
米屋でプラッシーを飲む。おお、これぞ1960年代の東京だ。本文には「プラッシーというオレンジジュースをもらい」という説明になっている。そうか、いまの人たちには、オレンジジュースだという注釈が必要なのか。
当時、プラッシーは、なぜか米穀店で売られていた。米は米穀店から届けてもらっていた。御用聞きが注文を取りにくる。このときついでにプラッシーの配達を頼むのだ。小学生だった私は、これを飲むのが楽しみだった。
米屋でプラッシーという一節だけで、この小説が、当時を見事に再現していることがわかる。
山谷で酒を飲んでいた客が、貧血で倒れる。売血で得た金で酒を飲みに来ていたのだ。そうそう、当時、輸血用の血液の多くは、血液を売りに来る人から買っていた。「売血」と言った。金のない日雇い労働者は、売血で手っ取り早く現金を手に入れていた。血液を頻繁に売っていると、次第に薄くなり、「黄色い血」と呼ばれて社会問題になった。輸血による肝炎が問題になり始めたのも、この頃だった。
警察が山谷の簡易宿泊施設の捜査を始めると、活動家の学生たちが駆け付けて、警察の捜査に抗議する。当時はしばしば山谷で労働者や活動家と警察の衝突が起きていたっけ。
著者の奥田さんは、なぜこんなことが書けるのか。舌を巻きながら、それ以上に懐かしさを覚えながら一気に読んだ。
オリンピックを翌年に控え、当時の東京は建設ラッシュに沸いていた。しかし、地方は発展から取り残されていた。
殺人事件の捜査で警視庁の刑事は北海道へ向かう。上野駅から急行「十和田」に乗って青森へ。そこから青函連絡船で北海道へ。学生時代、私もまた急行「十和田」の固い椅子に座って北へ向かった。
どうも懐古趣味が露呈してしまう書評になっているが、そんな時代背景の下、北海道・礼文島の漁師手伝いの青年が、島にいられなくなり、島外に逃げ出す。
それからしばらくして、東京の南千住で殺人事件が発生。警視庁捜査一課五係の刑事が、捜査中、北国なまりを話す青年の話を聞きつける。
いまから約四〇年前、私はNHK社会部の警視庁捜査一課担当記者として、五係の刑事たちも取材していた。殺人事件の捜査は組織的に展開することになっていたが、刑事たちは、自分が聞き出した有力なネタは、容易には仲間に開陳しない。自分の手柄にしようとするのだ。
警察内部の縄張り争いも激しかった。時代遅れになりつつある刑事たちの群像もまた、見事に描写されている。「刑事たちが、こんな風に張り合うものか」と疑ってはならない。小説の舞台になった昭和三八年よりずっと後の昭和五六年に私が捜査一課担当になったときも、刑事たちの気風は同じようなものだった。
刑事の聞き込みで浮かび上った不審な青年。捜査を進めるうちに、小学生誘拐事件が勃発する。果たして不審な青年は、誘拐事件に関与しているのだろうか。
この誘拐事件にはモデルがある。「吉展(よしのぶ)ちゃん誘拐事件」だ。児童が誘拐され、身代金を要求する電話が被害者宅にかかってくる。当時は、まだ電話の逆探知ができなかった。犯人の声を録音して分析するしかなかった。
この事件で、初めて報道協定が結ばれた。それ以前の誘拐事件で、新聞が警察の捜査を逐一報道したため、犯人が追い詰められ、子どもを殺害したことがあったからだ。報道機関は協定を結んで、事件を報道せずに警察の捜査に協力する。その代わり警察は、捜査状況を報道機関に説明するという仕組みだ。私も社会部時代、二件の誘拐事件を取材したことがある。記者と刑事の争いの描写もリアルだ。
礼文島を逃げ出した青年は、どんな過去を背負っていたのか。刑事たちの執念の捜査で、その全貌が明らかになるとき、読者は言葉を失うだろう。
来年は二度目の東京オリンピック。最初のときの日本そして東京はどんな様子だったのか。かつての貧しさを知る者として、一読を勧めたい。
(いけがみ・あきら ジャーナリスト)