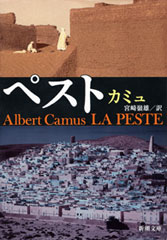書評
2020年4月号掲載
コロナ・ウィルスと寓意小説
カミュ『ペスト』(新潮文庫)
対象書籍名:『ペスト』(新潮文庫)
対象著者:カミュ/宮崎嶺雄訳
対象書籍ISBN:978-4-10-211403-2
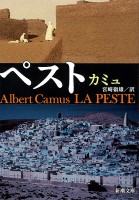
アルベール・カミュの『ペスト』が売れている。Amazonでも品切れで(調べたのは三月初旬)、入荷は月末三十日。原因はいま騒がれているコロナ・ウィルスだろう。じつは筆者、一月下旬に武漢封鎖のニュースに接したとき、最寄駅近くの大型書店へ行って、新潮文庫の棚に『ペスト』があるのを確かめてみた。ドラッグ・ストアから消えたマスクと違って、文学にまでは影響がとどかないのか、と感じた。一週間ほどして、書店に立ち寄った際、文庫の棚の前を通ったとき、カミュの並びから『ペスト』が消えていた。『異邦人』は二冊も残っていたのに。
本稿の依頼を受けたのは、それからしばらくして。読み返そうと文庫を探したが、あるはずの書棚になく、その折、Amazonも月末まで品切れと分かり、かろうじて中古の文庫版を注文したのだ。とどいたのは、学生時代のものとは違って、一冊本で、活字も大きくなっていた。
アルジェリアの港町オランが、一九四*年、とつぜんペスト禍に見舞われ、十か月ほどに及ぶ都市封鎖を経験する。そのなかでの、災禍との戦いのプロセスが、医師・リウーの目から語られている。学生時代、鮮烈な読後感を残した『異邦人』に比べ、生意気にも、『ペスト』は方法論的に後退したと感じたが、読み返して、印象は一変していた。短篇向きの、実存主義が好む「状況」は繰り返しがきかないのだが、それを『ペスト』は刻々と変化する事態として取り入れても劣化させず、しかも長篇でしか出せない物語の起伏と醍醐味を差し出していて、目から鱗だった。
『ペスト』の読後感が変わったのには、いまわれわれを取り巻く「状況」も関係しているだろう。病原菌とウィルスではまったく違うが、都市封鎖という小説のなかの出来事は、武漢どころか、日本の玄関口でも見ることができた。ダイヤモンド・プリンセス号の船内封鎖の推移を毎日テレビで追いながら、刻々と、見ているこちら側も日本という国に封鎖されていくという実感をもたずにはいられなかった。状況の細部は違うのに、『ペスト』の、「それは自宅への流刑であった」という一行がわれわれの感覚を言い当てているように感じられた。
小説に即して言えば、冒頭からの、まるでランダムに起こるかのようにネズミの死骸の増加を語るカミュの筆の乾いたタッチに怖さを感じた。菌を媒介するこの小動物から、ウィルスをまき散らしているかもしれないと恐怖に思う他人のセキやクシャミの飛沫を連想するからか。
オラン市内を走る満員電車の描写にも、「すべての乗客は、できうるかぎりの範囲で背を向け合って、互いに伝染を避けようとしている」とあって、深くうなずいていた。コロナ・ウィルスが報道されるようになって、電車のなかで、どうしてもマスクをしていない乗客を避けようとしてしまう自分がいる。それこそ、背中を向けてしまうことだってある。風邪やインフルの流行時には、むしろマスクの人を避けていたのに。
夏の海水浴が禁止されたことを語るくだりに、ペストが「あらゆる喜びを追い払ってしまった」というひと言を見つけ、ライブの中止やら、Jリーグやプロ野球の試合延期を連想してしまう。その意味でも、われわれは「自宅への流刑」を余儀なくされているのだが、おそらく、そうした寓意の先には、オリンピックやパラリンピックの延期や中止までもが見えてくる。政府もジャーナリズムもはっきり言わないが、そうしたことについても、ペストを疑うリウーの要請した「保健委員会」で知事や当局は消極的だし、「新聞」は「何ごとがあろうとも楽観主義」を貫く、と『ペスト』には書かれていて、なぜなら市民も(われわれ国民も)それを望まないからだ。
そもそもペストじたい戦争の寓意として書かれている、と言われているが、いまのコロナ・ウィルスがペストから引き継ぐ寓意の連鎖の先に見えるのは、占領下の一地域の孤立ではなく、ウィルスを敵とした全世界を巻き込んだ全面戦争ではないだろうか。
われわれの"いま"と重ねて『ペスト』を読むことは邪道かもしれないが、小説の面白みはたしかに倍加される。寓意に充ちた『ペスト』の力もそこにあって、『ペスト』が売れだしていることじたい、この小説が「自宅への流刑」に必要なアイテムになる、と人びとが気づきはじめているからだろうか。
(よしかわ・やすひさ フランス文学者)