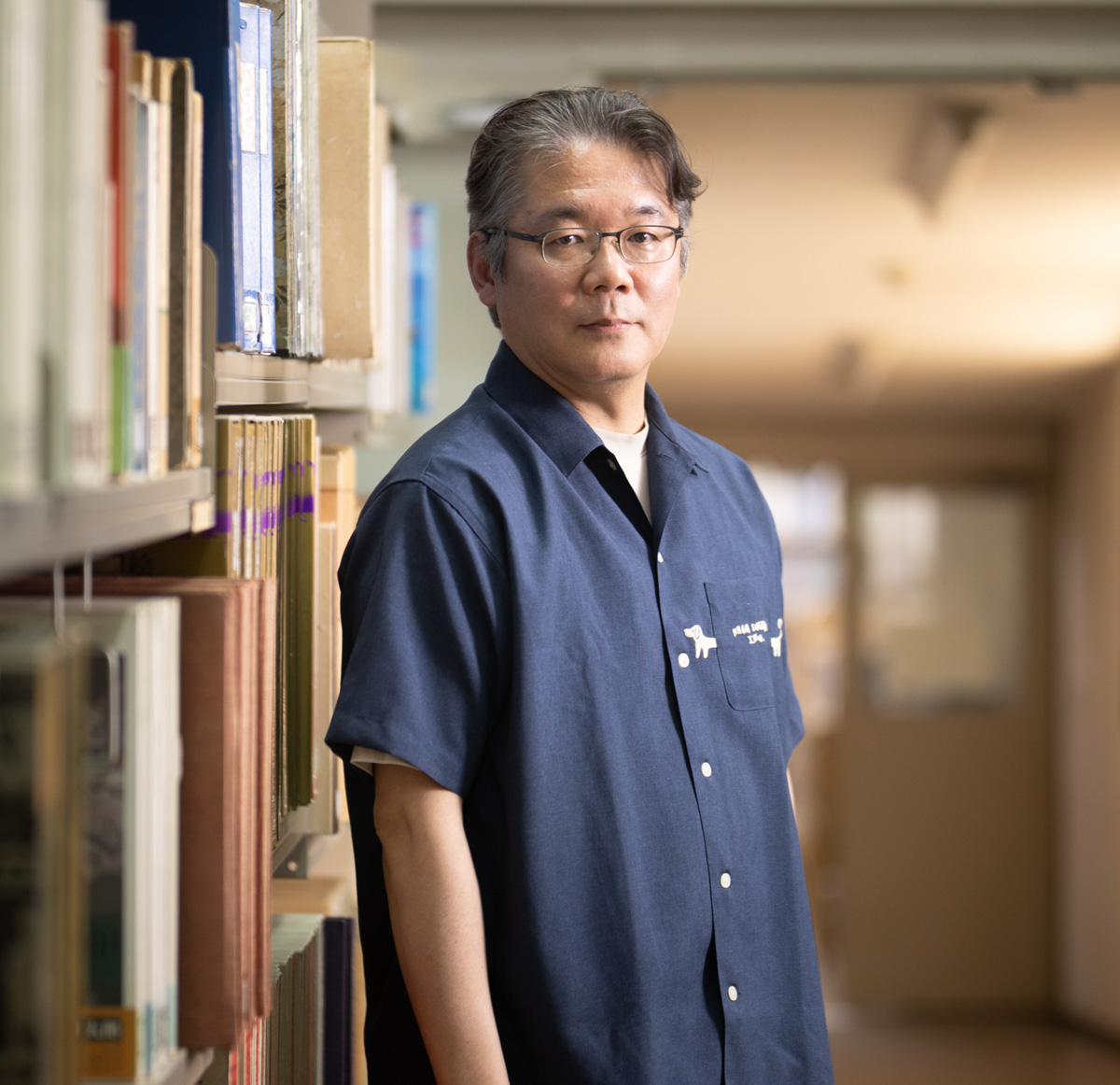インタビュー
2020年5月号掲載
『銀花の蔵』刊行記念インタビュー
血縁関係に縛られない家族のかたち
『オブリヴィオン』が「本の雑誌が選ぶ 2017年度ベスト10」第一位に輝くなど、人気を広げている実力派の著者。自身にとって挑戦作という新作について語っていただきました。
対象書籍名:『銀花の蔵』
対象著者:遠田潤子
対象書籍ISBN:978-4-10-104351-7

――遠田さんといえば、過酷な運命に翻弄される人間たちのドラマを描く、骨太な作家というイメージです。本作では醤油蔵を家業とする旧家で育った少女・山尾銀花(やまおぎんか)の半生を描かれますが、物語が生まれたきっかけを伺えますか?
遠田 とにかく、"蔵物"を書いてみたかったんです。母の実家は能登の山奥なのですが、貴重品をしまっている小さな蔵がありました。残念なことに結局一度も中に入らせてはもらえなかったんですが、ずっと「蔵っていいなあ」と惹かれていて。あと、宮尾登美子さんの『藏』を昔楽しく読んだ記憶も影響しています。『藏』で描かれていたのは酒蔵だったので、同じではなく、自分なら味噌蔵か醤油蔵か、と考えて。醤油の方が何となく書きやすそうだな、と。
――どこかNHKの朝ドラを彷彿とさせるような大河小説で、これまでのテイストとは結構違っていますよね。
遠田 今まではミステリ風味の作品に寄せたりしていたのですが、同じようなものばかり書いていてはいけないので、意識的に新しいものを書こうとしたというのはあります。読者の方にどう受け取られるかは、ちょっと心配ですが。
――銀花たちが移り住んだ雀醤油の蔵には、座敷童が出るという言い伝えがある設定ですよね。
遠田 蔵と旧家を書こうと決めて、他にもアクセントとして何か、と思った時に座敷童のアイディアが浮かんだんです。今も関西の片田舎に住んでいますし、母親の実家の印象も強くて、田園風景やどこか民俗っぽいものに親近感があるんですよね。ファンタジーノベル大賞の出身ですし、元々、幻想的なモチーフが好きなんだと思います。
――山尾家には秘密がいっぱいで、銀花は幼い頃から家族関係に悩まされています。遠田さんが繰り返し、複雑な家族の問題を描き続けるのには何か理由があるのでしょうか。
遠田 私は元々家族とか、家というものが苦手でした。ごく普通の家庭に育ったと思いますが、勝手に家族というものに窮屈さを感じていて。家族というより、共同体と言った方がいいかもしれませんが......。家が象徴する共同体に拒否感があって、だからこそ家族を描こうとすると、ドロドロと言われるような展開になるのかもしれません。
――成長した銀花は苦労しながらも、幸せな家庭を築いていきます。その健気な姿にぐっと来てしまいました。
遠田 銀花が築く家庭には私の理想が投影されています。それは、誰かに強制された関係ではなく、自分の選択によって結びついている家族です。そこに血の繋がりは関係ありません。あくまでお互いの好意で繋がっている関係。銀花は血縁とは関係のないところで、自ら選んで家族を築いた。だからこそ、きちんと幸せになれたのだと思います。
――銀花の祖母である多鶴子(たづこ)はそれと対照的な描かれ方をしています。自分にも他人にも厳しい性格ですが、銀花もその生涯に亘って大きな影響を受けていますよね。
遠田 多鶴子は家父長制の下で生きて、戦争を経験した人です。不本意な人生を送りながらも、蔵を切り盛りしようという根性がある。でも、銀花とはまた別のベクトルを向いています。山尾家の三世代の女性には時代と共に変わる女の生き方を象徴させたようなところもあります。
――特に、料理に対する向き合い方にそれぞれの特徴が出ているように感じます。
遠田 料理というのは、家庭を維持する衣食住の中で唯一、人間の三大欲求の一つである食欲に関わっていて、人を表す時にその特徴が出る部分だと思うんです。人を書こうとすれば、セックスを描くか、食を描くかというくらい。作中でも各世代の女性にとって料理をすることは意味合いが違っています。多鶴子はあくまで実用的に料理をし、銀花の母である美乃里(みのり)はとにかく夫を喜ばせるために料理する。銀花はそんな母親を否定できませんが、世間の謳う自立した女性像とのギャップを感じたりもしています。
――銀花自身の価値観も成長していくのに共感しました。美味しそうな食事シーンが目白押しですが、特にラスト近くで銀花が開く食事会は読んでいてお腹が空きました。
遠田 それは良かったです(笑)。あのシーンは、銀花が肩肘張らずに、家族のために料理するということへ向き合い、たどり着いた心境を表しています。銀花にとって、自分で選択して繋がった家族のために料理をして、みんなが食べる姿を見ることはとても贅沢な行為なんです。
――話は少し変わりますが、デビュー直後にお話しした際に、「いつかドストエフスキーみたいな作品を書きたい」と仰有っていましたよね。
遠田 そんなお話をしましたっけ? その時のことは覚えていないんですが、大好きで目標としている作家です。
――十年経った今、お書きになって来た作品を考えると、腑に落ちた思いがします。
遠田 それは嬉しいです! まだ全然満足のいく作品は書けていませんが、少しでも近づけているとしたら、書いて来て良かったです。これからも精進したいと思います。
(とおだ・じゅんこ 作家)