対談・鼎談
2020年6月号掲載
『組曲 わすれこうじ』刊行記念 往復書簡
「書く」べき何かと、「読む」を超えた欲望
黒田夏子⇔川上未映子
7年の歳月をかけた黒田さんの最新作をめぐって、予定されていた川上さんとの対談は取り止めに。
急遽、誌上でのやりとりとなった往復書簡をお届けする。
対象書籍名:『組曲 わすれこうじ』
対象著者:黒田夏子
対象書籍ISBN:978-4-10-353311-5
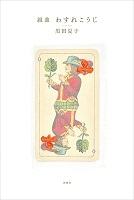
黒田夏子さま 川上未映子
ご無沙汰しております。大変な日々が続きますがお元気でいらっしゃいますでしょうか。『組曲 わすれこうじ』を拝読しました。それは幸せな時間を過ごしたと言うよりほとんど恍惚の体験で、なぜ黒田さんの文章を読むとこのような状態になるのか、この恍惚の原因は何なのだろうと思いを巡らせています。わたしは「abさんご」を人生の最期に残る意識のどこかに、最後に映す文章になればいいと思うほどに愛していますが、そう、黒田さんの文章を読むという体験には映すという比喩がいちばん遠くないように思うのです。祝いや呪いが言葉や音律を伴いながらも、常にそれらではないものを目的とし表現するように、黒田さんの文章世界は存在しています。
今作ではものや心理や時間のすべての描写――ここでなされていることを描写と呼んでよいのかすらためらわれますが、たとえばトランプ、写真、夕日、応酬、小箱、記憶のなかで手繰りよせられては散逸する記憶のようなものたち――それらは意味としてつかまれたあと独特の瞬間をおいて読者のなかで像を結び、そしてそのすぐそばから解体され、あとにはとうてい名指しすることのできないものが残るのです。「身がわり書き」に「......その澄んだ打音と天からの赤と,大おけの湯に身を沈めていくときの,おかすともおかされるともつかない素肌のそよめきとが分かちがたく合体した一しゅんの気遠さ,そういうことを書きたいのだが......」とありますが、まさに『組曲 わすれこうじ』は、その意思とそれを実現する唯一無二の文体だけで生成した一冊だと思います。黒田さんは、黒田さんに書かれるべき/書かれた「何か」は、書かれはじめることによって生まれてくる/生まれてきたものだと思われますか。それとも、あらかじめ世界の側に、黒田さんによって書かれるべき/書かれた「何か」があると思われますか。
川上未映子さま 黒田夏子
ひさしぶりにお話しできる機会をとてもたのしみにしておりましたのに、おもいもかけない時節にまわりあわせてしまって叶わず、でもこんな最中に拙作を読んでくださっての過褒のおたより、おもはゆいながらほんとうにありがとうございました。
かぞえれば七ねんもの昔、まだ早稲田文学新人賞直後の時点で"川上未映子の読書爆発"欄(共同通信社)での『abさんご』評も、しんそこありがたい口切りでした。「要約や伝聞がほぼ意味をなさない、その本が開かれてるときにしかその本が存在していないと言いたくなるような読書」「わたしはきっと、この匂い、この色、この感触のするところからやってきて、そして戻ってゆくのだ、そしてそこには、まだ生まれてもいない者たちが息づいて、いずれ誰もがそのどちらでもない者になってゆくのだ」という受けとめかたをしていただけてじつに幸いでした。
ところで今回のおたずねの機微にきちんとおへんじできるかどうかはまことにこころもとないのですが、しごくあっさり言うなら「書かれはじめることによって生まれてくる/きた」というほうです。むろんなんらかの目あてやきっかけがないと書きはじめませんが、「何か」は「あらかじめ世界の側に」あるわけではなく、一語一語一文一文を組み立てていく途上でだけあらわれてくるとかんじています。なにしろ或る一つの個体の意識は一しゅん一しゅんの偶然の集積でありつつ、三次元に在るかぎりはそのかさなりの順を決して逆行させられず、それでいて絶えまなく変わりつづけているというやっかいな代物であり、世界とはまた輪をかけての偶然と変転との巨塊で、その双方がそれぞれまったくかってに動きつづけているのですから、その一回的な遭遇のあわいにだけたちあらわれたかに見えたようなものを書きことばで捕らえこみたいなどという野望はどだい無理なのです。それなのになぜそんな野望が生じるかというと、個体の認識欲にはどうしても感情だの執着だのがからまりついてしまうからで、ただしそんな無理とわかりながらの欲求があるおかげで書きことばの組み立てのくふうはいくらかでも進んでいき、ことばがことばを拓いていって、ときとして目ざしたものを超えた獲物を招んでしまうことがないではないとかんじています。
いっぽうで、練達の仏師は、仏像が木材の中にすでに在って、じぶんはただそれをそこなわずにほりだすだけだと言ったとかの逸話を読みかじったことがありますが、それは「あらかじめある」というほうのかんじかたなのかもしれません。
では、いままさに旺盛な筆力でつぎつぎと書き進めていらっしゃる未映子さんごじしんは、どんなふうに実感なさっているのでしょうか、ぜひうかがってみたいものです。
黒田夏子さま 川上未映子
ご返信をありがとうございました。黒田さんの文章がどのようにして発生してゆくのか、それを黒田さんが言葉でどのようにとらえ、お感じになっているのかを知ることができて幸せです。ご質問いただいたわたしの場合は、詩と小説の作法に分けられそうです。たとえば詩を書くときは言葉が書かれる最中がただ連続し、それが結果的にひとつのまとまりを作りますが、小説の場合は、あらかじめ世界や認識の中にあって揺らいであるだろうものを、多くの人が想起しやすいべつのものに翻訳しているというような実感があります。けれどこのなかにも詩的な衝突や見過ごしや出会いがしらの産物もあるので、小説を書くときは混合、詩の作成は色々なものが遮断された密室で言葉自身によって行われる作業のようなものと喩えられるかもしれません。
翻訳といえば、黒田さんの文章を読んでいるとき、妙なことが起きもするのです。同時代に生きている作家による現代の日本語で書かれている作品であるにもかかわらず、どうしてか「翻訳したい」という欲望を抱いてしまうのです。
これは先のお手紙にお伝えした恍惚と深く関係すると思うのですが、ただ読むのでは満足できなくなり、内部に入りこんで見分けがつかなくなるまで完全に混ざりあい、その証拠として内側から生まれなおすような何かになりたい――そんな焦りとも衝動ともつかない熱に駆られます。黒田さんには、感動でも感心でもない、なんらかの「欲望」を感じてしまうような作品はありますか? もしあるとすれば、それはどういった欲望になると思われますか?
川上未映子さま 黒田夏子
こんどのおたよりでは、まず、未映子さんはずっと詩と小説とを並行して書きつづけていらっしゃるのだとの改めての感慨がありました。たしかに、おなじ書きことばではあっても、あつかいかた、普遍への梯子のかけかたがちがうのでした。しょうじきのところ私のほうは、詩とは詩作とはと見きわめる遥か手まえで、とにかくじぶんは散文のほうだと早々にしぼってしまい、それでいて、おっしゃるような"混合"であることの垣の低さにつけいって、けっかとしてなにもかもを散文作品の中に持ちこんでいるところがあります。詩であれば跳躍の昂揚をそのままさらしてすんでも、散文には未映子さんのおっしゃる"翻訳"作業に似た一工程が必然らしいのに、双方を混在させたことでついそのきわどさをあそびすぎるかとも自戒しました。
「感動でも感心でもない、なんらかの"欲望"を感じてしまうような作品」はあるかとのおたずねにも、おへんじはたいへんむずかしいながら、さまざまな感慨をそそられました。これはまさに未映子さんならではのしなやかな読みかたから出てきたことばで、ぶしょうな私にはとうていおよばない境地です。むろん「感動でも感心でもない」ひたすら感嘆するばかり圧倒されるばかりの作品にもいろいろと出遭ってきまして、ふつうのいみでの熱中没入しての読書体験というのはわかるつもりですが、その作品をまたくりかえし読みたいといういじょうの"欲望"はおもいつけないです。そういえば未映子さんは「早稲田文学」(2017年増刊号)に樋口一葉『大つごもり』の"翻訳"を載せていらして、その後さらに一葉作品全現代語訳をなさるらしいとのうわさもありますが本当でしょうか。もし本当なら未映子さんの"翻訳"という語には、そうした実践にさえつながる独特のふくみがあるわけで、そのような読みかたは、読むことじたいが大仕事になります。あるいは私の怠惰が、そんなあまりに疲れる読みかたを避けていたいのかもしれません。
でも、じぶんがそんなふうなのに、今回の小著もそんな大変な読みかたをしていただけたとしたらあまりに申しわけなく、すこしななめのおへんじ代わりになるかならないかわかりませんが、おわりにすこしななめの所(ジャンル)からのせめてものおみやげをどうかご笑納ください。
他の蟹を如何ともせず蟹暮るる
吾が啖ひたる白桃の失せにけり
永田耕衣『驢鳴集』より
(かわかみ・みえこ 作家)
最新の対談・鼎談
-
2026年2月号掲載

内田若希『意味ある敗北とは何か─アドラー心理学で読み解くトップアスリートの言葉─』刊行記念
階段を一段上がるのは勝利のときばかりじゃない

意味ある敗北とは何か―アドラー心理学で読み解くトップアスリートの言葉―
-
2026年1月号掲載

『ひのえうまに生まれて─300年の呪いを解く─』刊行記念鼎談
ひのえうまに生まれて生きる私たち

ひのえうまに生まれて―300年の呪いを解く―
-
2026年1月号掲載

三島由紀夫生誕100年記念対談
私たちの中に生きている三島

三島由紀夫論
-
2025年12月号掲載

『池上彰が話す前に考えていること』刊行記念対談
池上さんと村上さんが話す前に考えていること

池上彰が話す前に考えていること




