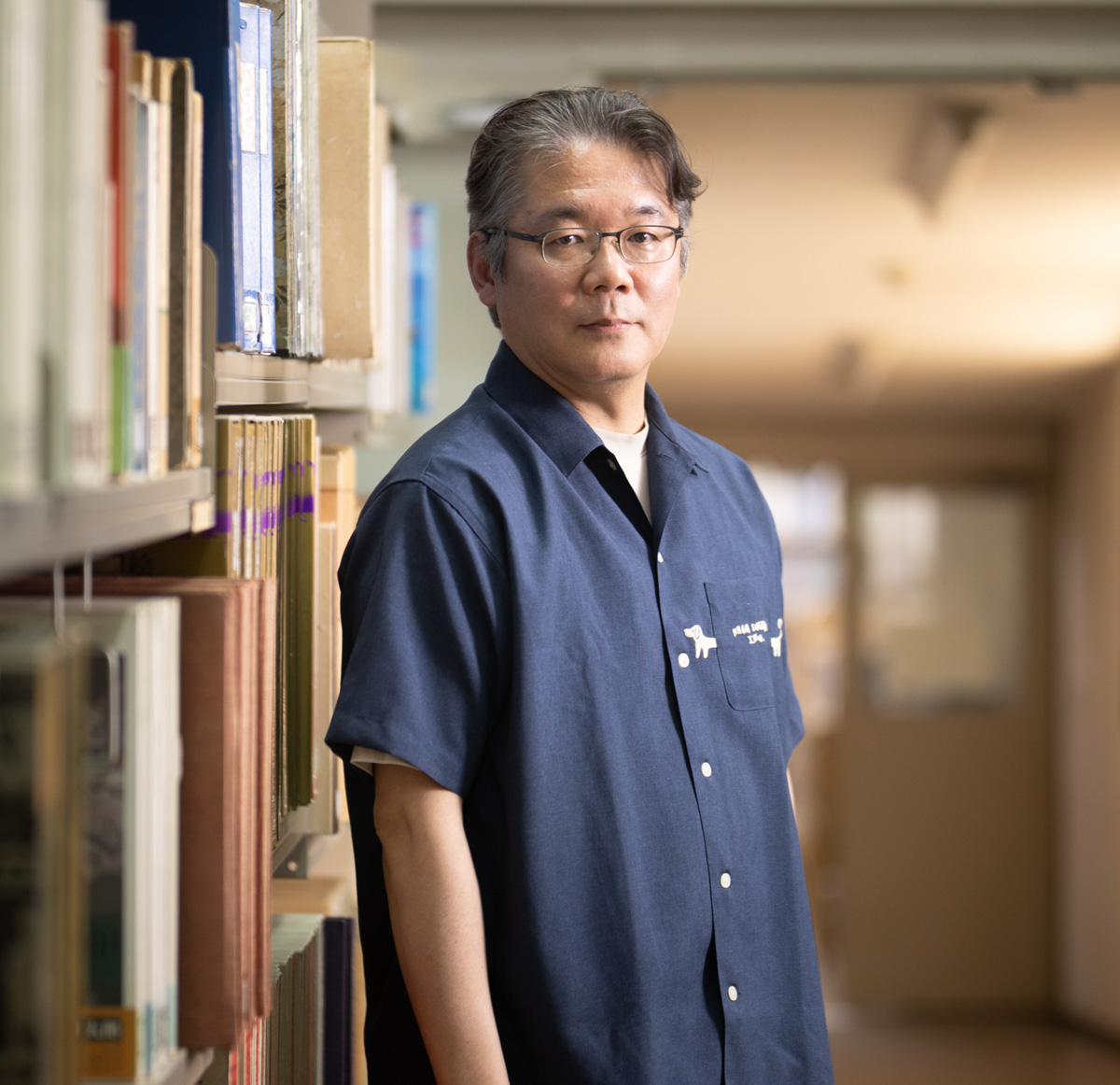インタビュー
2020年12月号掲載
短期集中連載『小説 イタリア・ルネサンス』をめぐって(三)
ローマの魅惑――「寛容の精神」の底流にあるもの
現在刊行中の歴史小説『小説 イタリア・ルネサンス』は第3巻に進み、物語はフィレンツェからローマへ。
同様に転居した過去をもつ塩野七生さんにとって、ローマとはいかなる都市なのか?
その魅力を語ってもらった。ふたたびロックダウンに入ったイタリアからの特別寄稿。
対象書籍名:『小説 イタリア・ルネサンス3
対象著者:塩野七生
対象書籍ISBN:978-4-10-118123-3

この第三巻では、三十代後半という青年期の後半に入った主人公のローマでの日常が語られます。その彼に、ローマが何をもたらしたか、も含めて。
フィレンツェやヴェネツィアは、中世とルネサンスの都市と言ってもよい。しかし、ローマはちがいます。ローマとは、イタリア内の他の都市とちがうだけでなく、世界中の他の都市ともちがう町なのです。
では、何がちがうのか。それを、ローマを訪れた時代は別でもベストセラー作家という点では共通していた、二人の文人の感想で見てみましょう。
『若きウェルテルの悩み』で一躍ヨーロッパ文壇の寵児になったドイツ人のゲーテは、ローマに入ったその日にこう書いています。この日から、自分にとって真の「生」が始まった、と。三十七歳の若さが爆発した一句ですよね。
その八十年以上も後にローマを訪れた『トム・ソーヤーの冒険』の著者マーク・トウェインは、いかにもユーモア作家らしい一文を日記に残している。「今朝はすこぶる気分が良い。なぜなら昨日、ミケランジェロはとっくの昔に死んでいることがわかったので」。笑っちゃうけど、同感もします。ローマには、どこに行ってもミケランジェロの爪痕が残っているのだから。しかし、もう死んじゃった人ならば、これ以上創作される危険だけはない。だから創作者としては、気分が良くなるのも当り前でしょう。
というわけでローマという都市は、感受性の豊かな旅人には常に何かを感じさせてしまう都市でもあるのですが、このことは訪れた時代に関係ないみたい。
それで、今回はラファエッロについて話します。
中部イタリアの小都市ウルビーノで生れ、そこで画家修業を始めていた彼は、フィレンツェに行ってレオナルド・ダ・ヴィンチの絵を見たことで、彼にとっての真の人生が始まる。そして、その後に滞在したローマで、彼の芸術は花開く。しかしそれは、優美な聖母子像の画家としてだけではなかった。ヴァティカン内にある「ラファエッロの部屋(スタンツェ)」を埋める壁画の数々が、この若い芸術家が、もっと広く世界を見ていたことを示しています。人間の「知」の源泉になった古代の哲学者の群像である「アテネの学堂」を描いたのだから。
この有名な絵画が、当時のローマ法王庁を満たしていた開けた精神(オープン・スピリット)の具像化という評価は正しいでしょう。でも私には、この絵は法王か高位聖職者の誰かがラファエッロに描けと命じたから実現したのではなく、ラファエッロ自身も心から納得して描いたのだと思えてならないのです。
なぜなら、現代の遺跡保存委員会のような組織があの時代のローマにもあったとしたら、その組織のトップはラファエッロであっただろうから。法王レオーネ十世にあてた、ラファエッロ自筆の手紙が遺っています。そこには、発掘の作業中に出てくる古代の傑作が金持ちたちに買い占められている現状は嘆かわしく、より多くの人に観賞されるためにもローマ法王庁が積極的に購入に乗り出すべき、と書かれている。手紙を受けとった法王レオーネはメディチ家出身だからその方面への理解があり、ラファエッロの嘆願はただちに実行された。後世に生きるわれわれが、ヴァティカンを初めとするローマの数多くの美術館で古代の傑作を観賞できるのは、ラファエッロのおかげでもあるのです。私の彼への愛が、ルネサンス最高の画家の一人という以上であるのも当り前。三十七歳という若さで死んでしまったけれど、彼もまた、ローマの魅惑を感じとった一人でもあったのだから。
それに加えてもう一つ、彼の絵を前にするたびに感じることがあります。それは、ラファエッロが持っていた、過去に何ごとかを成した人たちに対する正直で素直で深い敬意の念。「アテネの学堂」でも、プラトンはレオナルドの姿に、アリストテレスはミケランジェロの姿にしている。
しかし、そのラファエッロを見るたびに思ってしまうこともある。ほんとうの意味の謙虚とは、自らに確固たる自信を持っているからこそ実行できる生き方である、ということ。ローマがいつの時代でも寛容であったのも、それゆえでしょうか。
(しおの・ななみ 作家)