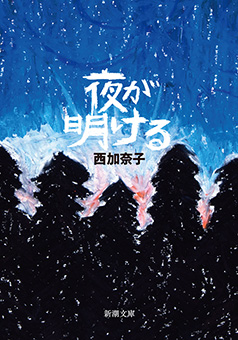書評
2021年11月号掲載
心の貧困に抗う
西加奈子『夜が明ける』
対象書籍名:『夜が明ける』
対象著者:西加奈子
対象書籍ISBN:978-4-10-134958-9
冷たい闇に取り込まれていくような物語を読み進めていく中で、この小説が掘り起こそうとしている問題の大きさに圧倒された。
『夜が明ける』には、作中を通してずっと貧困の問題が横たわっている。本作の主人公である「俺」は、高校生までは貧しさとは無縁だったものの、亡くなった父親の借金を背負ったのをきっかけに、大学進学を奨学金に頼らざるを得なくなる。社会人としてテレビ制作会社で働き始めてからも、仕事は激務で朝帰りが常なのに残業手当はつかず、家賃や光熱費、毎月の奨学金の返済に加えて、実家にもお金を送らなければならないため、生活は一向に楽にならない。
もう一人の主人公と言える親友のアキは、そもそもが母子家庭で、子どもの頃から貧困状態にある。見た目こそなんとか清潔に保っているが、一日三食は食べられず、身を削りながら働く母親からの愛情は歪んだもので、自分はここにいていいんだという自己肯定感を持つことができない。児童相談所に保護され、家と施設を行き来するようになってからも、暮らしが上向くことはなく、生活保護を受けることを勧められるが、それすらも自分にはふさわしくないと拒んでしまう。
この小説を読んでいると、経済的な貧困が人間の精神を侵食し、やがて心まで貧困化させていくのだということを実感させられる。貧困化した心は、絶えず本人から可能性や希望を吸い取り、諦めを促して、自分に価値を感じられなくしてしまう。
俺はテレビ制作会社に、アキは小さな劇団に入ってから、幾度となく理不尽な目に遭い、心身をすり減らしていく。その理不尽さは、男社会や、やりがい搾取、パワハラ・セクハラなどが混ざり合った劣悪な職場環境から生まれたもので、それでも二人は文句を言わず、与えられた仕事をこなし続ける。体の不調を我慢し、いくら頑張っても報われない虚しさにとりつかれ、身近な人を恨んだり、自分を責め続けたりしているのに、他に行き場所がないからそこを離れられない。
でも、こうした心の貧困の問題に苦しんでいるのは、彼らだけではないと思う。程度の違いこそあれ、決して余裕があるわけではない暮らしの中で、多くの人が似たような苦しみを抱えながら生きている。心の貧困化は、もはやこの国を(あるいは世界を)覆い尽くす闇なのだ。だからこそ、ぼくらは、その終わりのない闇を耐え忍びながら必死に生きようとする彼らのことを、祈るような気持ちで見守りたくなる。二人の中に、今もなお傷つき続けている自分を見つけて、この苦しみから抜け出す方法はないのだろうかと考えてしまう。
個人的には、本作の主人公が男性であることに大きな意味を感じた。一般的に男性は「強くなければならない」という性規範を内面化しやすく、つらいことがあっても一人で抱え込んでしまうため、心の貧困化から抜け出せないことが多い。しかも、そうして追いつめられた男性たちの怒りや苛立ちは、大抵自分よりも弱いところに向かうのだ。女性や子どもなどの、社会的に不利な立場にある人たちを同じ人間として扱わないだけでなく、ときには守るべき家族を見捨てて、母子家庭を生み、新たな貧困を作り出してしまう。
事実、俺とアキの父親は、親としての責任を放棄することで二人を貧困へと追いやった。父の不在がよく問題になるこの国では、まっとうに生きる男性のロールモデルをイメージするのが難しい。働いて出世するのが良いことのように言われてはいるが、実際にそれを成し遂げるためには、人生の多くの時間を仕事に費やさねばならず、結果として「働けない奴に価値はない」という考えになりがちだ。借金を背負った俺を助けてくれた、一見まともに見える弁護士の男性でさえ、「負けるな」と俺を励ます一方で、自分の引きこもりの息子を負け組だと考えていた。他人を助ける行為自体は立派だが、結局彼がしたことは、勝ち負けがすべてだという競争心を若者に植え付け、自分の息子が戻ってきにくい社会に加担しただけのように思える。
道標のない中で、俺はどうやってまっとうに生きようとするのか。心ある人に助けられ、絶望の淵から戻ってきた彼が最後に踏み出した一歩は、でもたしかに、そこへ向かうための一歩であるように思えた。
心の貧困という、この国を覆い尽くす闇。その巨大で解決の糸口が見えない問題に、この小説は真っ向から向き合っている。その勇気とまっとうさに胸を打たれるのは、ぼくだけではないはずだ。
(しらいわ・げん 作家)