対談・鼎談
2022年8月号掲載
『ぼくらは人間修行中 はんぶん人間、はんぶんおさる。』刊行記念対談
世界が変わる経験
秀島史香 × 二宮敦人
『最後の秘境 東京藝大――天才たちのカオスな日常』の刊行後、著者の二宮敦人さんは学生結婚した奥様(元東京藝大生)との間に、兄弟を授かりました。家庭という“秘境”の日常をつづる本誌連載の書籍化を記念し、愛読者でもあるラジオDJの秀島史香さんとの特別対談が実現しました。
対象書籍名:『ぼくらは人間修行中 はんぶん人間、はんぶんおさる。』
対象著者:二宮敦人
対象書籍ISBN:978-4-10-350293-7

秀島 はじめまして。
二宮 はじめまして。生でお声を聴く機会をいただけて光栄です。
秀島 そんな(笑)。『ぼくらは人間修行中』を娘と一緒に読ませていただき、お目にかかるのを楽しみにしていました。彼女も「かわいいね」って、連発しながら読んでいました。
二宮 娘さんはおいくつですか?
秀島 11歳、小学5年生です。ちんたんは?
二宮 今年4月に小学校へ入学しまして、ピカピカの1年生です。弟のたっちゃんは2歳になりました。
秀島 4歳違いなんですね。わたしには2歳下の弟がいます。彼が生まれて家にやってきたとき、最初は「わー、赤ちゃんだ」とはしゃいでいたけれど、みんなが「かわいい、かわいい」ってやるものだから、2日後には「うん、もういいから赤ちゃん返してきて」と言ったそうです。女の子で初孫だったからちやほやされて育ちました(笑)。
二宮 面白い。メモしていいですか?
秀島 あ、本当に記録魔なんですね。
二宮 あわよくば原稿に使わせていただければと。
秀島 どうぞどうぞ。
二宮 きょうだいができたら人はどう変わるのか、興味があるんです。自分以外の存在とどう付き合うか。その技術みたいなものを学んでいくのが人間の成長なのではないかという気がしていまして。僕は5歳下の妹がいるんですが、自分の子供時代のことは忘れていたりするので、それを観察させてもらっている感じです。
とはいえ、まだよくわからないんです。たとえば、明らかに兄がおしつけがましいときがあるんですが、なぜか弟はかまわれているうちに楽しくなっちゃっているらしいとか。僕にはわからない文脈が彼らの中にできつつあるのを最近感じています。
秀島 子供ならではのプロレス的なノリというか様式美ですね。
二宮 そうなんです。彼らの回路を言語化したいけれど、なかなかうまくできない。
秀島 いえいえ、驚くほど言語化されていると思いますけど。『人間修行中』を読んでいて、大人は子供たちの行動を不思議だなあと思いがちだけれど、子供から見たら大人の立ち居振る舞いが不思議だよね、という視点の逆転にもハッとさせられました。
二宮 人間は、通ってきた道を忘れてしまう、いつも今しか見えていないということなんでしょうねえ。改めて見ると、子供の方が大人よりすごいと思わされることがたくさんあります。
世の中の優しさに気づく
二宮 秀島さんはお母さんになることでお仕事に変化はありました?
秀島 はい。まず妊娠中はわりとぎりぎりまでお仕事をしていて、マイクや車のハンドルとの距離が遠くなりました(笑)。そういうからだの変化も含めて、リスナーさんからいただく近況報告を自分の体験に照らし合わせて考えられるので、返すコメントにより実感をこめられるようになった気がします。たとえば「どんどんお腹が大きくなってきました」という妊婦さんからの声に「足の爪が切りにくいですよね」とか、「駅の階段では足元に気を付けてくださいね」とスッと言えるようになったんです。
二宮 秀島さんの『なぜか聴きたくなる人の話し方』には学びがたくさんありましたが、実体験にも裏打ちされていたんですね。僕はベビーカーが来たらさっと道を譲るようになりました。自分で操ってすごく方向転換しにくいというのがわかりましたので。

秀島 実感があると行動に衒(てら)いがなくなるんですよね。娘が生まれたとき住んでいたのは、狭い路地に銭湯があって、おばあちゃんが軒先で朝顔を育てているみたいな町だったんです。娘をベビーカーに乗せて散歩していると、どこからともなくおばあちゃんが集まってきて「かわいいわねえ」と。子どもが運んでくれる社会との接点、ご縁ってありますね。
二宮 バスに乗っているとき、強面のひとがじっとこっちを見ていたかと思ったら、息子にニヤッと笑いかけたりするんです。僕も見ず知らずの子供にそうしてしまう。子供には人間の内面を引き出す力がありますね。
秀島 ベビーカーに赤ちゃんがいるとつい覗き込んじゃうこととか、ありません? で、みんな笑顔になる。お母さんも笑顔。赤ちゃんの力、すごいです。
二宮 世の中はこんなに優しかったんだって気づきますよね。自分もそれに触れていたはずなのに、忘れてしまっている優しさに。
秀島 その優しさを素直に受けられるようになると、場がうまく回っていくんですよね。娘のベビーカー時代、家の最寄りの駅にはエレベーターもエスカレーターも設置されていなかったんです。駅員さんは親切で「いつでも声をかけてくださいね、お運びします」と言ってくださるんですが、忙しい時もあると思って、たいがい抱っこ紐でなんとかやっていたんです。でも、あるとき立ち往生してしまっていたら、私の様子を見ていた男子高校生が「よろしければお持ちしますよ」と運んでくれて感激しました。「今どきの若者、優しいじゃん!」って。
二宮 世の中に優しくしてもらうと、自分も優しくなれますよね。許容範囲が広がるというか。
秀島 わかります。
二宮 世界の見え方が変わってくる。
出会いは高校生のとき
秀島 わたしは仕事一途なところがあって、大好きなラジオの仕事さえできていればハッピーだったんです。
二宮 大学生のときから仕事をされていて。
秀島 はい。でも、いつまでこの仕事をさせてもらえるかわからない。だから、お仕事は毎回、試合に出る、オーディションを受けるというような感覚が今でもあるんです。だから、常に準備をしていないと鈍っちゃうとも思っているのですが、わたしが世話をしないと生命の維持すらできない赤ちゃんが目の前に出現したときに、仕事よりも優先すべきものがあったんだと気づかされました。
二宮 だとすると、出産はかなり勇気が要ったんじゃないですか?
秀島 世界が違って見えるに違いないという確信だけは産む前からあったんですが、その前に実はわたし、もともと結婚願望がなかったんです。仕事だけしていたい、結婚したら家事の負担も増えそう、今でさえ大変なのに絶対無理! みたいな(笑)。
二宮 え、じゃあなんで結婚したんですか?
秀島 夫は友人の同僚だったんですが、わたしとものごとの見方がまったく違うので、いちいち発言が面白い。でも一緒にいて落ち着く。そこがスタートでした。二宮さんと奥様はどこで出会われたんですか。
二宮 僕は漫画家を目指していた時期がありまして、ジャンプに漫画を持ち込んだりしていたんですよ。それがだんだん、小説でお仕事をもらえるようになり、忙しくなってきたので、僕が原作を書いて絵は誰かに描いてもらうという形に変わったんです。その相棒が忙しくなって「自分の代わりに絵のうまい人を紹介するよ」とつないでくれたのが、彼女でした。
秀島 へぇ~。
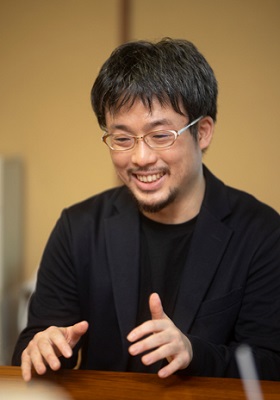
二宮 でも、実際に会ってみたら、当時高校生だったんですよ。僕は大学を出て社会人をしているのに。しかも彼女は東京藝大を目指しているという。え? それって難関大学なんじゃない? 僕の漫画なんか描いている場合じゃないでしょと思って、「大学に合格してまだやる気があったら連絡して」と言って別れたんです。
秀島 奥様は現役で合格を?
二宮 いえ、一浪していますね。それで忘れたころに「受かったよ」と連絡がありました。
秀島 いい話。
二宮 で、じゃあ一緒に漫画を作るかとなったんですが、彼女、絵は確かにうまいんですけど、漫画の絵じゃないんですよね。「わたし、漫画は描けない」とか言い出して、「でも、せっかくだから確定申告のレシート分けとか手伝うよ」と言ってくれて。僕も「じゃあ、お礼に焼肉とかおごるよ」とか、徐々に仲良くなっていった感じです。あとで聞いたら、僕の小説を好きで読んでくれていたらしくて、最初から好感度は高かったらしい(笑)。
妻の家族から気づかされたこと
秀島 『人間修行中』の中に、奥様の実家を初めて訪ねて行ったら、お父さんはひたすらたこやきを焼いたり、家族がそれぞれ好きなことをやりながら一緒の部屋にいたというエピソードがあるじゃないですか。娘もあの話がすごく好きで「ドラマとかと違うけど、結婚の挨拶ってこういう感じなのかなあ」と聞かれました。
二宮 違うと思いますが(笑)。彼女の実家はすごくて、僕は崇拝に近い感情を抱いているんです。お父さんはエアコンとか使いやすい充電器の形とかを考えるプロダクトデザイナーで、目の前のものがどうやってできているかに異様に詳しいんです。お母さんは美容師で、妻も手を動かすのが大好き。いわば具象に強い一家なんです。僕は彼女と彼女の家族に会って、自分から具象がすっぽり抜け落ちていたことに気づきました。
秀島 『最後の秘境 東京藝大』の中でいかにも藝大生然としていた奥様が、『人間修行中』ですっかりお母さんになっていたのも印象的でした。今も毎月連載されているわけですが、誰に向けて書いているんですか。
二宮 とりあげるのは自分が気づいたこと、考えさせられたことですので、それを知らなかった少し前の自分に報告するような気持ちで書いています。
秀島 わたしは子育て話を聞くのが好きなんですが、連載を読んでいると「わかる!」と「へぇ!」が交互に押し寄せてきて、足し算どころか二乗、三乗の相乗効果で面白いんです。これからも娘と一緒に楽しみにしています。
二宮 ありがとうございます。
(にのみや・あつと 作家)
(ひでしま・ふみか ラジオDJ)
最新の対談・鼎談
-
2026年2月号掲載

内田若希『意味ある敗北とは何か─アドラー心理学で読み解くトップアスリートの言葉─』刊行記念
階段を一段上がるのは勝利のときばかりじゃない

意味ある敗北とは何か―アドラー心理学で読み解くトップアスリートの言葉―
-
2026年1月号掲載

『ひのえうまに生まれて─300年の呪いを解く─』刊行記念鼎談
ひのえうまに生まれて生きる私たち

ひのえうまに生まれて―300年の呪いを解く―
-
2026年1月号掲載

三島由紀夫生誕100年記念対談
私たちの中に生きている三島

三島由紀夫論
-
2025年12月号掲載

『池上彰が話す前に考えていること』刊行記念対談
池上さんと村上さんが話す前に考えていること

池上彰が話す前に考えていること




