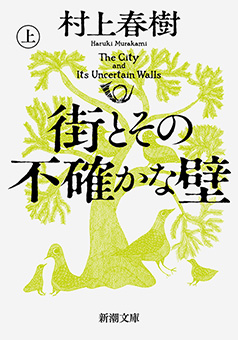書評
2023年5月号掲載
村上春樹『街とその不確かな壁』刊行記念特集
すぐ近くの異界
対象書籍名:『街とその不確かな壁』
対象著者:村上春樹
対象書籍ISBN:978-4-10-100178-4/978-4-10-100179-1
小説にはふたつの世界が存在する。ひとつは私たちになじみ深い現実世界だ。生活があり、人間関係がある。そこで生きる十七歳のぼくに、もうひとつの世界の存在を教えてくれるのは、十六歳のガールフレンドである。彼女は、この現実にいる自分はほんものではなく、そのもうひとつの世界、「高い壁に囲まれた街」に暮らしているのがほんものの自分だと言う。そしてあるとき、彼女は忽然と姿を消す。
四十五歳になった「ぼく」は穴に落ち、気づくとそのもうひとつの世界にいる。そこでは人は影を持たない。時間が存在せず、音楽も映画もなく、図書館には本ではなく古い夢が並んでいて、冬になると街の内外を行き来する単角獣たちは死んでいく。人は夢を見ないし涙を流さない。そして死なない。かつてのガールフレンドは、だから十六歳のまま、その世界で暮らしている。その世界で生きる決意をしたのに、語り手はなぜか現実世界に戻ってしまう。
第二部には、現実世界に生きる意味を見いだせない(見いだせなかった)人たちが登場する。決意と裏腹に現実に帰された「私」もそうだし、「私」がしたしくなるもと図書館長もそうだった。現実世界のルールから外れている少年も登場する。彼らは現実世界でない場所を求めている。
壁に囲まれた世界はいかにも不気味で、黄泉の国を思わせるのだが、そこで暮らす自分が「本当のわたし」だというガールフレンドの言葉を信じるならば、プラトンの説くイデア界みたいなものなのかもしれない。そちらが本質であり、現実世界で私たちが目にするものはそれらの影で、私たち自身が仮の姿である。
あまりに大きな喪失を抱えてしまった場合、人はこちらの世界に生きる意味を見失う。この現実で、心もしくは意識があるかぎり、喪失は埋められない。そのことに耐えられず、生きることを放棄する人もいるけれど、でもたいていの場合、喪失を抱えたままこちら側で生きる。いのちを断つことは、べつの世界にいくことではないと知っているからだ。万が一にもそんな世界があったとして、そこで死者に会えるという保証はない。
しかし小説の「私」や毎日図書館に通う少年は、死すら超越した、もうひとつの世界があると知っている。描かれるその世界は私にとって魅力的な場所ではないが、彼らはそちらのほうが本当かもしれないとも思っている。でも彼らに選ぶ自由は与えられていない。意志によって行き来はできない。
では、それ以外では選ぶ自由はあるのだろうかと私はふと考える。現実に戻された「私」が仕事を辞め、福島の山間の図書館で働くのは、選んでそうしているというより、見えざる何かの導きによってそうなっている。だれかと出会う、呪いのような恋に落ちる、だれかを失う、暮らす場所を変える、そのすべて、じつのところ、選べない。私たちが自由意志で選んでいると思いこんでいるものごとは、本当の世界ですでに決定されていることなのかもしれない。興味深いのは、だれによって決められたのかわからない点だ。この小説に神的存在は登場しない。
『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』には、この壁に囲まれた世界の詳細な地図が付いている。その世界にのみこまれまいと、計算士の「私」はいのちからがら地上へと脱出するし、壁のなかで暮らす「僕」も現実世界を選ぶ。しかしこの小説における「街」は、現実世界のすぐ近くにあり、そこから私たちは逃れられない。いや、私たち自身の奥深くに、すでにあるのかもしれない。そしてそこには、私たちが失った多くのものや人が、時間という概念から解放されて存在している。小説に描かれる街は不気味だが、しかしそう思うと、不思議にやすらかな気持ちにもなる。
この小説の核は1980年に発表された中編小説だとあとがきに書かれていて、私はそのことに驚き続けている。この完璧な壁に囲まれた世界は、作家の内に在り続けている。幾度書いても失われず、年月もそれに手出しができない。この小説を読むということは、確固として存在しているその壁の内側へ、否応なく連れていかれる体験を意味している。帰還できないかもしれなくとも。
(かくた・みつよ 作家)