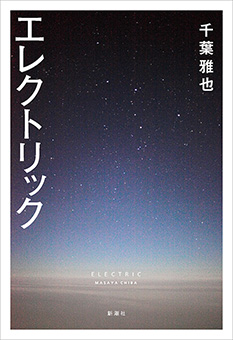書評
2023年6月号掲載
電気と幽霊
千葉雅也『エレクトリック』
対象書籍名:『エレクトリック』
対象著者:千葉雅也
対象書籍ISBN:978-4-10-352973-6
縁あって、栃木県宇都宮市に今年の春まで約三年間住んでいた。埼玉から栃木に引っ越したばかりの時、一番驚かされたのは「雷」の近さだった。「雷都」という呼び名は、落雷の多さばかりを言っているのではないと思う。栃木の雷は、体をすり抜けるように距離が近い。アパートのベランダのすぐ目の前に雷が落ちた。部屋が真白くなった直後、目の前の道路が爆発したような音が鳴った。その時は本当に死んだかと思った。栃木に暮らす前は、雷を遠くの街に落ちる小さな光の線としてしか認識したことがなかった。近年の異常気象ではないかとも思ったが、地元の古い家ほど庭に避雷針が立っていたことが印象深い。
「電球のような真空管は上部にかすかなオレンジの光が灯り、その周りに箱形や筒状のパーツが肩を寄せ合って、小さな都市を成している。真空管アンプは、ビル街に似ている。」
アンプの上に広がる世界は、『エレクトリック』の主人公・志賀達也が暮らす栃木県宇都宮市の風景と重なる。1995年、達也は県内トップの男子校に通う高校二年生で、いずれは大学進学のために上京することを強く望んでいる。それでも、東京駅へと繋がる宇都宮駅には何か不穏なものを感じている。広告業を営む父は、会社存続の手立てとして「ウェスタン・エレクトリック」というヴィンテージのアンプ製作に力を注いでいる。達也は敬意を持って、父の仕事を傍から眺めている。
本作品の語り出しはとてもユニークだ。「ハンドパワー」を語る、1995年にお茶の間を風靡したあのマジシャンの手品から始まる。そうして、この冒頭が物語の展開へと影響を及ぼしているようにも見える。
これは手品の話ではない。この作品のキーワードとなるのは「電気と幽霊」の関係だ。
「『そのシンバル、そこ!』/達也の父はよく、試聴しながら、スピーカーの間に囲まれた空間の、どこかの一点を指差した。(中略)ウェスタンのすごさは、音楽を聴かせるというより、幽霊を見させることにある。」
完璧なアンプは、過去に叩かれたドラムの音を、まるで幽霊のように聴衆の前に出現させる。父と野村が仕上げたウェスタンのアンプは、次第に達也の日常に「あるはずのないもの」を見せるようにすらなる。最高傑作に仕上がった二人のアンプは、幽霊を出現させる媒介としてではなく、まるでそれ自体が幽霊かのように神出鬼没となって現れる。
『エレクトリック』に登場する「電気と幽霊」のモチーフはアンプだけではない。インターネットが自室に引かれたことで、達也はゲイサイトを覗き見るようになる。初めて見る「生きている同性愛の世界」に感動しながらも、実際に達也が眺めているのはコンピューターの画面で、画面の向こう側で言葉や文字を発しているのが人なのか、コンピューターなのか幽霊なのかも分からない。
「雷都」の異名を持つ土地で、子ども時代の暗がりを強調するような雷の光。作品中には、雷光が効果的なタイミングでやってくる。それは登場人物たちの一瞬を切り取る、ストロボの役割も果たしている。
『エレクトリック』は筆者三作目の長篇小説だ。『デッドライン』『オーバーヒート』に続く今作品でまず驚いたのが、主人公が「志賀達也」という名前を与えられたことだった。前二作では主人公の名は「○○」と伏字にされていた。この三部作を地続きなものとして媒介をしているのは、友人Kの存在である。
達也は父との関係の中で、「最も大切な人間は、隣にいるものだ」という気づきを得る。この言葉を、達也は知らず知らずのうちにKに向けているように私には読めた。父と野村の交流を目の前で眺めながら、達也はまるでポケットから取り出すようにKの話を持ち出す。その場にKが存在せずとも、達也の隣にはまるでいつもKが存在しているかのようだ。「そこにはあるはずのないものが存在する」という点において、Kはある意味で幽霊じみている。それは達也にとってKは「完璧」な友人だから、という短絡的な言葉に言い換えていいようにも思えない。Kは何を考えているのか、宇宙空間の闇を覗き込むように静かに考え込む。達也がKを見ている時、Kは達也を見ていない。前二作を読んだ時には思わなかったことだが、今作を読んで、実はこの三部作はKとの関係性をめぐる物語なのではないかとも思った。
アンプの回路図面を見て、達也は便所の個室を思い浮かべる。何気ないシーンだが、Kとの出会い、嫌悪感を抱いているクラスメイトからの吐露、栃木唯一のハッテン場との出会いは全て便所で起きている。その導線を経た達也の体には電流が走り抜ける。まるでアンプの配線を組むが如く、筆者が夢中になって展開の対応関係を結んでいる。父と野村は化け物アンプの作製に成功し、筆者自身も最高傑作のアンプを組むかのように、「あるはずのない」幽霊が自由自在に立ち現れる「完璧な」世界を作り上げたのだろう。
(まーさ・なかむら 詩人)