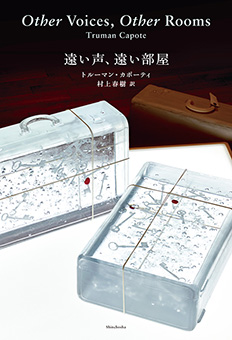書評
2023年8月号掲載
かつての愛読者へのギフト
トルーマン・カポーティ『遠い声、遠い部屋』
対象書籍名:『遠い声、遠い部屋』
対象著者:トルーマン・カポーティ/村上春樹訳
対象書籍ISBN:978-4-10-501409-4
私が河野一郎訳『遠い声 遠い部屋』を手にしたのは、主人公のジョエルと年齢が近かったことから、1990年代半ば頃と記憶している(文庫の奥付は、昭和四十六年発行)。
当時すでに古風に感じた言い回しは、私をアメリカ南部の田舎町へと誘い、圧倒的な瑞々しさと夏の陰影を残した。
今あらすじを拾い上げれば、本作はむしろ陰鬱な過去と未来のない森に閉じ込められた物語でもある。
焼けつくような夏の日、母親を病気でなくした十三歳のジョエルは、顔も知らない父親の招待を受けてランディングの古い屋敷にたどり着く。情緒不安定な義母のミス・エイミーとその従兄弟のランドルフ、いつか雪を見たいと願う使用人のズーとその祖父のジーザス・フィーヴァーが住んでいる。ところが父親だけが一向に姿を現さない。やがて衝撃の事実がランドルフの口から語られる。
物語にはジョエルと同世代の姉妹も登場する。野生児のようなアイダベルと、ツンと澄ましたフローラベルという対照的な姉妹だ。孤独なジョエルは彼女たちとの交流を試みるが、彼らの素朴な冒険心や逃避願望はあっけなく打ち砕かれる。
一見、ひと夏の少年の成長譚だが、じつは私はあらすじの大半を正確に覚えていなかった。完全に理解するには年齢が若かったこともあるが、それ以上に文体が複雑すぎたために、あらゆる出来事がまるで霧の向こうで起きたような印象を長年持っていた。
それが時を経て、『遠い声、遠い部屋』村上春樹訳で新しく出版された。読み始めて驚いた。
出来事はそのままに、少しずつ印象を変えながら、それでいて私が魅了されたカポーティの世界だと懐かしさで胸をいっぱいにして確信したからだ。それはひとえに翻訳者の愛ある慎重さによるものだと私には思えた。小説にかぎらず、愛とは、対象に対する礼節と距離感だと私は考える。その適切さが本文の霧を幾分か取り払い、澱が落ちたようにも思える。分かりやすくなったというよりは、分かりにくさの正体が見えやすくなっている。
たとえばランドルフやエイミーとの会話中、突然、ジョエルの空想上の友人たちが登場する場面がある。
旧訳では、〈しかしジョエルの部屋の壁は厚く、エイミイの声も通らなかった。彼はもう長いあいだ、この遠いはるかな部屋を捜し出すことができずにいた。それはいつでも困難だったが、去年ほどむずかしかったことはなかった。したがって、今こうしてふたたびなつかしい友人たちに会えるのは嬉しかった。〉とある。
一方の新訳では、〈しかしジョエルの部屋の壁はとても分厚かったので、エイミーの声はそれを抜けることができなかった。今まで長い間、彼はその「遥か遠くにある部屋」を見つけることができずにいた。〉となっている。この「 」の役割は極めて重要である。
それは読み手を混乱させるのが、ジョエルの視点にしばしば混ざるイマジナリーフレンドや過去の情景――「遥か遠くにある部屋」だからだ。とはいえ単純化しすぎれば、作品の魅力は半減する。又、作中の言葉を借りるなら、「洪水に流されて窓から入ってきたものが、そこにたまたま居場所を決めたという風に」見える「馬鹿馬鹿しいほど丁寧な装飾」こそがジョエルの内面なのだから。故に、私はこの「 」の適切さに胸打たれた。
今回の新訳で大きく印象を変えたのは、登場人物ではないだろうか。
河野一郎訳では、登場人物がはん濫した比喩と描写に取り込まれて、半ば幻想的な風景のピースのように存在していた。その一人一人を、露骨ではなく喋り方に統一感を持たせて立ち上がらせているのが新訳だと感じた。翻訳者の作家としての力がさりげなく最大限に発揮されて、鮮やかな化学変化を起こしている。
特にジョエルとアイダベルが水辺で体を洗った後に喧嘩するくだりは、この美しい場面を以前にも読んでいたことが不思議なくらいだった。
男の子になりたいアイダベルの台詞が、旧訳の「あんたのせいじゃないわよ」から、「きみのせいじゃない」に変わり、読み手はより矛盾なき瞳を思い浮かべるだろう。アイダベルやズーが女の子であるための不自由や悲劇はそこだけを強調すべきではないが、今の時代には背景となりすぎるよりも、輪郭を持って取り扱われるのがふさわしいように思う。新しい読者はもちろん、今あらためてこの小説は素晴らしいと思える機会に恵まれることは、かつての愛読者にとってギフトである。
(しまもと・りお 作家)