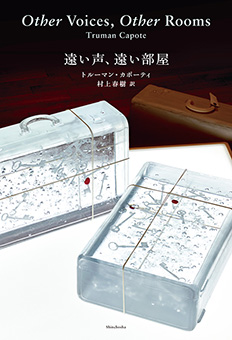書評
2023年9月号掲載
トルーマン・カポーティ あるいは育ちすぎた少年
トルーマン・カポーティ『遠い声、遠い部屋』
対象書籍名:『遠い声、遠い部屋』
対象著者:トルーマン・カポーティ/村上春樹訳
対象書籍ISBN:978-4-10-501409-4
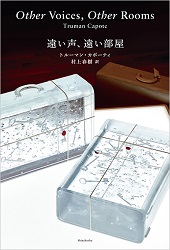
『遠い声、遠い部屋』は1947年のクリスマス・シーズンに、ランダムハウス社から刊行された。初版部数は一万部、これは新人作家の処女作としては異例のことだが、それまでに彼の書いた、そして雑誌掲載されたいくつかの短編小説が世間の話題を呼んでいたことが、そのひとつの理由となっている。彼はその時点で既に、「ミリアム」と「最後の扉を閉めろ」で二度O・ヘンリー賞を獲得していた。まだ二十三歳という若さで。
刊行された彼にとっての最初の長編小説『遠い声、遠い部屋』は、即座に「ニューヨーク・タイムズ」のベストセラー・リストに載り、九週間にわたってそこに留まった。初動で売れた部数は二万六千を超え、これはほぼ同時期に刊行され、全米ベストセラーとなったノーマン・メイラーの『裸者と死者』やアーウィン・ショーの『若き獅子たち』には及ばないものの、大衆向け読み物とは言えない純文芸作品としては、じゅうぶん賞賛に値する数字だった。そして売れ行き以上に、これほど世間(メディア)の熱い注目を浴び、様々な議論を呼び、良くも悪くも話題となった小説は他になかった。
その才気溢れる華麗な文体以上に話題を呼んだのは、ブックカバーに掲載された著者の写真だった〔編集部注:本誌今月号の表紙に掲載〕。美少年、まさにその一言で表すしかない見事なポートレイトだ。スキャンダラスと言ってもいいくらいに、見る者に衝撃を与える写真だ。この写真が出た瞬間から、トルーマン・カポーティは俊英の文芸作家というに留まらず、鮮やかな社会的存在として、ひとつのアイコンとして機能し始めたのだ(そしてそれは結局彼の人生の最後まで機能し続けることになる)。
「どうやったらあんなきれいに写真が撮れるんだろう?」と質問されてカポーティはこう答えている。「写真を撮られるときは、頭の中を美しいことでいっぱいにしなくちゃだめだ。それがコツさ。そうすれば、誰でもきれいになる」
小説『遠い声、遠い部屋』の評判は賛否相半ばした。褒める人は大いに褒め、けなす人は大いにけなした。概ね年配の批評家は酷評し、若い人々はそこにある大胆さを諸手を挙げて歓迎した。まずは悪い評から。ニューヨーク近辺のメディアになぜか酷評が多かった。
「凝りに凝った文体、しばしば病んだ頭の幻想の中に吸い込まれ、方向を見失っていく。それでもピクチャレスクではある。図書館には推薦しかねる」(「ライブラリ・ジャーナル」)
「ジョエル・ノックスの物語は語られる必要がなかった。著者のシステムからそれが取り除かれるという目的を別にすれば」(「ニューヨーク・タイムズ」日曜版ブック・レビュー)
「ミスタ・カポーティは魔女の秘薬を調合すべく、煮沸に煮沸を重ね、結局何ものも得られなかった」(「サタデイ・レビュー」)
「作品は未熟であり、そのテーマは人をぞっとさせるように仕組まれている……ホモセクシュアルという主題の仕掛けは悪趣味で、スパニッシュ・モスのようにだらりと重く垂れ下がっている」(「タイム」)
「才能溢れるマイナーな作家であるカーソン・マッカラーズの、ちゃちな模倣」(「パルティザン・レビュー」)
数少ない好評。
「『遠い声、遠い部屋』は、カポーティを最初から、類い希な才能を持つ作家としてこれまで称揚してきた批評家と読者が決して誤っていなかったことをはっきり証明した」とロイド・モリスは「ニューヨーク・ヘラルド・トリビューン・ウィークリー・ブック・レビュー」に書いた。「最初の長編小説でこれほど興奮させられるものを書いたアメリカの若手作家には、書評家としてもうずいぶん長い間お目にかかっていなかった。カポーティの才能は間違いなく重要であるというだけではなく、成熟し奥が深い」
「彼の文章の強い魔力に屈服しないでいることは不可能だ。ここに描かれたような鋭さと刺激をそなえた情景を、最近のフィクションの中に見いだすことはむずかしい……処女長編小説ということでいえば、本書より構成がしっかりして、よくバランスもとれ、話の筋が通っている作品はいくらもあるだろう。しかしより芸術的に興奮させられ、確かな才能を持ち合わせた新人作家の到来を実感させられる作品は、またとあるまい」(「ニューヨーク・タイムズ」平日版)
ニューヨーク近辺のエリート書評家たちの多くが強い反感を示したのとは対照的に(彼らはそこでほのめかされるホモセクシュアルの要素を嫌った)、地方都市のメディアは概ねこの本を褒めちぎった。「この短い長編小説は、過去十年間の文芸シーンに持ち上がった中では、最高にめざましい現象(フェノメノン)だ」と「シカゴ・トリビューン」は書いた。
「登場人物たちのぶつかり合いは、フォークナーの創成したものに匹敵する物語を作り出している」(「ダラス・ニューズ」)
「見事極まりない文芸的技巧。他のフィクション・ライティングがみんなぐずぐずした凡庸なものに見えてしまう」(「インディアナポリス・タイムズ」)
ところでブックカバーに印刷された著者の経歴(著者自身が書いた)は実にでたらめなものだった。
「(筆者は)三流政治家のためにスピーチライターを務め、リヴァーボートでダンスを踊り、ガラスに花の柄を描くことでひと財産を築き、某映画会社のために脚本下読みの仕事をし、高名なミセス・エイシー・ジョーンズのもとで占い術を習得し、『ニューヨーカー』誌編集部で働き、ダイジェスト・マガジンのために逸話の選択をおこなった」
「『ニューヨーカー』誌編集部で働き」という部分を除けば――それもただの下働きのコピーボーイに過ぎなかったのだが――すべて真っ赤な嘘ばかり、まさにジョエル・ノックス少年が白日夢の中で思い描きそうな華麗な幻想の羅列。カポーティ節、全開である。
個人的な話をさせてもらえれば、僕が最初に読んだカポーティの作品は短編集『夜の樹』だった。高校三年生のときにがんばって原文の英語(ペンギン・ブックス)で読んだ。そしてその文体の鮮烈さに強く打たれた。とりわけ「無頭の鷹」は、僕にとってのひとつの大事な指標となった。それから大学に入って、この『遠い声、遠い部屋』を読んだ(河野一郎訳・新潮社刊)。そして短編小説とは趣を異にするその入り組んだ、むせかえるような小説世界に、否応もなく引き込まれてしまった。僕がこの本を英語ではなく日本語で読んだのは、当時の僕の英語力では、凝りに凝った美しくもややっこしい原文にとてもついていけなかったからだ。
この小説を読んでいると、まるでジェットコースターに乗ってお伽の国を旅しているような感覚に襲われる。不思議な情景、不思議な人物たちが次々に登場し、その像が大写しになり、色合いを変えて微妙に歪み、そして霞んで消えていく。出版された当時の文壇では、これらは「南部文芸特有の誇張されたゴシック趣味だ」と決めつけられたようだが、今読むとそれが、地域性や文芸的流行みたいなものを超えた、あくまで(どこまでも)カポーティ固有のイメージの、華麗なショーケースであったことが理解できる。
旅行者はヌーン・シティに行くうまい方法をなんとか自力で見つけなくてはならない。というのは、その方角に向かうバスも列車も存在しないからだ。
というシンプルな文章で『遠い声、遠い部屋』は始まるわけだが、読み進むにつれてその文体はどんどん華麗になり、幻想的な色彩を強めていく。文章はしばしばきわめて感覚的になり、場合によっては整合性より言葉の響きそのものが大事な意味合いを持つようになってくる。そこに描き出される異様な情景が、普通ではない言葉遣いを筆者に求めているように。メタファーは遥か遠方にまで飛躍し、画像は自在に気ままに屈曲し、予想もしないような単語が唐突に飛び込んできて読者の感覚を鋭く小突く。
「カポーティ・スタイル」と言ってしまえばそれまでだが、そこには処女長編小説にかけるカポーティの強い意気込みと、自己の才能に対する紛れなき自負を読み取ることができるだろう。実際のところ、カポーティはこの小説以降、ここまで感覚・感性に徹した文章を書いてはいない。自分でも「これはちょっとやり過ぎたかな」と思ったのかもしれない。あるいは「こういうタイプの文章ばかり書いていたら、やがては袋小路に迷い込んでしまうだろう」と感じ取ったからかもしれない。いずれにせよ彼は、このあとに書いた長編小説『草の竪琴』においては、よりシンプルで、読者の共感を呼びやすい文章で物語を語っている。「カポーティ節」が派手に炸裂する箇所もところどころ見受けられるものの、そこでは間違いなくある種の方向転換がおこなわれている。
しかしこの『遠い声、遠い部屋』という長編処女作をとりわけ愛する読者は数多い。『遠い声、遠い部屋』には、この作品でしか味わえない、青年(あるいは育ちすぎた少年)カポーティの魅力が溢れかえっているからだ――そう、ところどころ「やり過ぎ」なぐらいに。
言い訳をするのではないが、そのようなわけで本書の翻訳は難儀をきわめた。とくに後半の華麗な、感覚的な文章の絡み合いは、まさに密集したイバラの藪のような様相を呈しており、時として無力な翻訳者を呆然とその場に立ち尽くさせた。それでもなんとか原文の醸し出す芳醇な空気と、繊細にして大胆なリズムを再現すべく、力を振り絞りベストを尽くした。まさに怖いもの知らずの、若き日のカポーティの世界を堪能し、愉しんでいただければと思う。
(『遠い声、遠い部屋』 「訳者あとがき」より)
(むらかみ・はるき 作家)