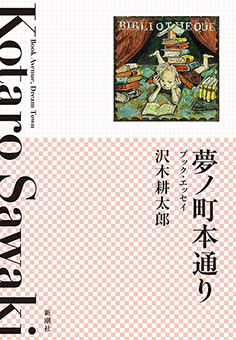書評
2023年10月号掲載
本は待ってくれている
沢木耕太郎『夢ノ町本通り―ブック・エッセイ―』
対象書籍名:『夢ノ町本通り―ブック・エッセイ―』
対象著者:沢木耕太郎
対象書籍ISBN:978-4-10-327524-4
私が最近聞いて、びっくりした話がある。ある記者の人が、高校生に取材がてら、読書の楽しさを話した。まずゲームの話題で引きつけ、それにつなげて自身の読書体験や、最近読んで面白かった本などの話が終わって質疑応答になったとき、一人の男子高校生が手を挙げた。そして彼は、
「本ってどこで買えるのですか」
と聞いてきたというのだ。
書店はほとんどの人が知っているものだと思っていたのだが、とうとう本をどこで売っているのか知らない若者が出てきた。昔はどこの町内にも個人の新刊書店、古書店、貸本屋があり、読書に興味がない人でも、書店の場所は知っていたが、今はそういう環境ではなくなってしまった。
『夢ノ町本通り』は、本にまつわる全エッセイ集になっている。冒頭の同名のエッセイには、町の商店街から書店がなくなっていく様が描かれていて、沢木さんとほぼ同じ光景を見て育ったであろう私は、深く同意したと同時に、一抹の寂しさを感じながら読んでいた。二十一年前に書かれた、「最強の『あとがき』」というエッセイにはこう書いてある。
「先日、地下鉄に乗っていたら、前の席に座った五十前後と思われるサラリーマン風の男性が、おもむろにバッグから本を取り出して読みはじめた。その年代の男性が地下鉄で本を読むこと自体は少しも珍しいことではない」
その本が『ハリー・ポッターと賢者の石』だったことで、沢木さんは、彼のような年代の人も読むから、ベストセラーになるのだと感心する。
しかし今は、五十代の男性が電車に乗り、バッグから本を出して読むのは珍しいことになってしまった。電車に乗ると、老若男女、ほとんどの人がスマホに目を落としている。スマホで本を読む人もいるらしいから、誰も本を読んでいないとはいえないのだが、紙の本を手にしている人が少なくなったのは事実である。
そんな世の中でこのような本に関する本が出版されるのは、本好きにとってはとても喜ばしい。とはいえ沢木さんが紹介している本のうち、私も読んでいた本は十冊ほどで、ちょっと悲しい思いをしたのだが、それと同時に彼の読書の範囲の広さ、量の多さに驚かされた。
山本周五郎の作品について、ページが割かれているのだけれど、私は三十六年前に、『日本婦道記』を読んだきりだ。山本周五郎完全読破を目指していた女性が、
「最初に読むのだったら、これがいい」
と勧めてくれたのだ。面白く読んだものの、当時の私は現代アメリカ文学のほうに興味があり、以降、山本周五郎作品を手に取ることはなかった。彼女は若くして亡くなったのだけれど、久しぶりに『日本婦道記』のタイトルを目にして、彼女を思い出した。
また、本にまつわる話のなかで、沢木さんが蔵書を預けていた地方にあった倉庫が、東日本大震災時に何らかのアクシデントが発生し、数千冊の蔵書が行方不明になったくだりを読んで、思わず「ひゃあ」と声が出てしまった。そのなかには失って悔いが残る本もあったはずなのだが彼は、意図したことではなかったが、本を減らすことができたと書いている。あれだけの旅をしてきた方だから、様々なアクシデントに対して、肯定的なのは当然なのかもしれないけれど、読んでいるこちらのほうがため息をついてしまった。そして私が学生時代に溺れるように読みふけっていた、植草甚一さんが亡くなった後、その膨大な蔵書の一部が沢木さんに渡っていたことを知り、「おおっ」と感激した。本に関する本を読んでいるときは、少しでも自分の好みと接点があると、なぜかうれしくなるのである。
新刊書店と古書店がある、望みどおりの商店街があったとして、自分はどうしたいのだろうかと、沢木さんは書いている。
「たぶん、『夢ノ町本通り』は、夢に見ているだけで終わるような気がする。そして、その通りは、私の夢の中にだけあればいいのだろうと思ったりもする」
あればよいけれどなくてもよい。私も書店が減っていく状況は悲しいけれど、それはそれで仕方ないだろうと思う。それはすぐに入手できる術が自分の身近になかったとしても、自分が必要としている本には、いつか必ず出会えると信じているからかもしれない。子ども、青年、壮年、中年、老年と歳を重ね、本を読んできた環境も自分自身も変化するけれど、本は自分を待っていてくれる。こんなにありがたいことがあるだろうか。
三十六年前に読んだ『日本婦道記』、今回この本で紹介されているなかで再読したい、新しく読みたいと思った本たち。世の中の本を巡るあれこれは、明るい話ばかりではないけれど、これからも自分のお金で本を買い、老眼、疲れ目とうまく折り合いをつけながら、本を読み続けていこうと、気持ちの後押しをしてくれる本だった。
(むれ・ようこ 作家)