書評
2023年12月号掲載
池波正太郎 生誕100年企画 SHOTARO IKENAMI 100TH ANNIVERSARY
84冊! 新潮文庫の池波正太郎を全部読む 後編
〆切厳守。年賀状は前年春に印刷。遅刻した者は徹底的に無視――。巨匠の超ストイックな素顔に「一気読みライター」の〆切は!?
最終回はエッセイとアウトロー&幕末&現代小説!
対象著者:池波正太郎
×月×日
S社のKさん、Hさんと待ち合わせて、京橋の試写室でアクタン・アリム・クバト監督『父は憶えている』を観る。キルギスの映画を観るのははじめて。
出稼ぎに行ったロシアから帰ってきた父ザールクは、記憶と言葉を失っていた。不在の間に、妻は別の男と再婚し、村の中にはゴミが放置されている。父をどう扱えばいいのか困惑する家族をよそに、ザールクは黙々とゴミを片付ける。孫娘だけがそれに寄り添う。
判らないところも多い映画だが、観終わって、
(この風景の中にもっといたい)
という印象を残す。いい映画だ。Hさんが「人が集まるシーンで、やたらとパンを勧めるのが面白かったですね」と話す。
東京駅近くまで来ると、先日閉店した〔八重洲ブックセンター〕一帯の再開発がすすんでいた。
山手線に乗り、秋葉原駅から歩いて、〔神田まつや〕へ。六時過ぎだが、ほぼ席は埋まっている。親子煮、わさび漬けなどをつまみに、ビールと酒をのむ。
通常は海老天が二本の〔天種〕を「三本にしてもらえますか?」とKさんが頼んだ瞬間、おばさんが持っていたおぼんをひっくり返し、私の肩に当たる。「すいませんねえ」と、何度も肩をなでられた。
念願の蕎麦がきを食べたあと、季節限定のなめこせいろ。気がつけば、最後の二組になっていた。
――と、最終回は『池波正太郎の銀座日記〔全〕』の下手な真似ではじめてみました。
実際、この日はKさんの提案で、〔池波あるき〕をやってみたのだ。
『父は憶えている』はキルギス映画だが、池波は『銀座日記』で、大好きなフランス映画をはじめ、イタリア、スペイン、ユーゴスラヴィア、中国などの映画を観たことを記している。
「すぐれた映画とか、すぐれた文学とか、すぐれた芝居とかというのを観るのは、つまり自分が知らない人生というものをいくつも見るということだ。もっと違った、もっと多くのさまざまな人生を知りたい……そういう本能的な欲求が人間にはある」と、池波は語っている(『映画を見ると得をする』)。
映画を観たあとは、行きつけの店で軽く酒を飲み、食事をする。〔まつや〕については、「うまいといえば〔まつや〕で出すものは何でもうまい」と、池波は絶賛している(『むかしの味』)。1884年(明治17)創業の老舗だ。
〔まつや〕のある神田須田町には、あんこう料理の〔いせ源〕、鳥すきやきの〔ぼたん〕もある。この三店は西原理恵子・神足裕司『恨ミシュラン』で、老舗のバミューダ・トライアングルなどと評されていた。
この界隈に名店が多いのは、近くに万世橋駅があったことが大きいと、常盤新平は解説する(『池波正太郎の江戸東京を歩く』ベスト新書)。1919年(大正8)に神田駅が開業する前は、万世橋駅が中央線のターミナルとしての機能を持っていたのだ。
池波は〔まつや〕での過ごし方を、「時分どきを外して入り、ゆっくりと酒をのみながら、テレビの日本シリーズなどをたのしむ」と書く(『むかしの味』)。
池波にならって、私が食べたのが〔蕎麦がき〕だ。
現在、普通に食べている麺の形をした蕎麦は〔蕎麦切り〕といい、江戸時代の元禄期以降に普及したものだ。それから半世紀以上あとの時代を舞台とする『剣客商売』で、秋山小兵衛が蕎麦屋で食べているのは蕎麦切りだ。
蕎麦がきは、蕎麦粉に熱湯を加え、かき混ぜてねばりを出したもので、この店では手桶に入って出てくる。箸で切って口に入れると、蕎麦の香りが広がる。酒の肴には最高だ。
閉店前になると、潮が引くようにテーブルが空いていく。居残っていた私たちは、「そろそろ……」と促されて店を出る。気づかいの人だった池波ならあり得ないことだ。
しかも、池波なら、これから帰宅して仕事にかかるのだ。当方はいい気分で帰って寝るだけ。こんなところは、とても真似できないのだった。
遅刻する奴は無礼者
締め切りには絶対に遅れない、年賀状は前年の春に印刷するなど、池波の几帳面さを示すエピソードは多い。
戦争を体験したことで、人間の予測が当てにならないことを痛感したため、甘い期待をせずに、最悪の場合を想定しながら仕事をするのだと、池波は語っている(『男の作法』)。
池波は同じ東京出身の山口瞳との対談で、人と会う場合には、約束の時間よりも二十分前、三十分前に行くと話し、山口も賛同している。そして、「約束の時間に、もう堂々と遅れてくる。それが何度も何度もだ。あの神経、山口さん、わかりますか」と憤る(「われら頑固者にあらず」『江戸の味を食べたくなって』)。
この時、池波の頭に浮かんでいたのは、誰だったのだろう?
講談社で池波を担当し、「仕掛人・藤枝梅安」シリーズの「彦次郎」に名前を使われた大村彦次郎は、こう書く。
〈池波さんは律義なだけに、時間にはやかましかった。「小説現代」の新人賞選考会では、委員の野坂さんや五木さんが定刻によく遅刻した。野坂さんはひたすら頭を下げ、五木さんはしきりと弁明した。(略)いっぽう池波さんは紅潮した頬っぺたをふくらませて、時間に几帳面な山口瞳、結城昌治の両委員のほうにばかり顔を向けて話しかけた。歳下の井上ひさし、長部日出雄さんと好きな映画の座談会をしたときも、井上さんが遅れて、そのときは終始長部さんに向かって話しつづけ、井上さんを無視した〉(『文壇うたかた物語』ちくま文庫)
井上ひさし、長部日出雄との座談会とは、『オール讀物』1975五年10月号に掲載された「昔も今も映画ばかり」のこと。誌面を読むと、池波と井上は普通に対話していて、まとめ役の編集者の苦労が偲ばれる。
なお、この件を教えてくれたのは、井上ひさしの蔵書をもとにした山形県川西町の〔遅筆堂文庫〕で、井上の研究をしているその名も井上恒(ひさし)さんだ。
井上ひさしは食への関心が薄く、故郷の川西町に帰省した際も、たぬきそばばかり食べていたという。東京育ちの池波に対して、井上は田舎で育った。改行を活かした文体を持つ池波に対して、井上の一文は長く、粘り強い。そして、「遅筆堂」を自称するほど原稿が遅く、しばしば雑誌に穴を開けた。
多作だったこと以外は、池波と井上は真逆だったと云えるだろう。
井上の遅刻仲間の野坂昭如や五木寛之も東京以外の出身だ。彼らは原稿が遅れると、神楽坂の「新潮社クラブ」に缶詰めとなった。一方、つねに自宅で執筆した池波は、クラブに泊まったことはないはずだ。
池波は、自分と同じような几帳面さを他人に求める時、癇癪を起こす。「押しかけ書生」の佐藤隆介は、約束の五分前に到着した若い編集者に、池波が「無礼者!」と怒鳴りつける場面を書いている(『素顔の池波正太郎』)。
うーん、正直、ついていけない。先の山口瞳との対談でも、地方出身の成り上がり者への侮蔑を隠さない。そこに、田舎者の私は反発してしまう。生身の作家に、『剣客商売』の秋山小兵衛のような包容力を求めることが間違いだとは思うけど。
裸の顔をさらけ出す
池波はエッセイの名手と呼ばれ、新潮文庫にも十冊が入っている。生前に刊行されなかったものは、朝日文庫や講談社文庫にまとまっている。その量は膨大だ(内容的な重複も多いが)。
池波の小説は読まないが、エッセイは愛読するという人は結構多いようだ。
ただ、自身は小説に比べて、随筆は難しいと述べる。
〈小説ならば、その生の材料を、どのようにも料理ができる。
だが、随筆はあくまでも、つくらず飾らず、自分の全人格を、ありのままに出しきって書くものだとおもうし、私の場合は、ことさらに、それでないと一枚もペンがすすまない。(略)根本は自分の裸の顔をさらけ出さねばならぬ〉(『日曜日の万年筆』)
思い切って、「自分の裸の顔」をさらけ出したのが、『青春忘れもの』だ。『小説新潮』で連載が始まった頃、池波はまだ四十代半ばで、自伝を書くには若すぎると一度は断ったという。
両親の離婚により祖父母の家で育てられた少年時代から、株式仲買い店などで働き、大人の世界を覚える。そして戦争を経て、東京都の職員として働きながら、戯曲を書く。それがきっかけで長谷川伸の弟子となり、小説を書きはじめるまでを振り返る。
歌舞伎や映画に没頭し、洋食屋でカツレツにかじりつく姿が生き生きと語られる。これらのエピソードはのちに『食卓の情景』をはじめとする、多くのエッセイとして改めて書かれることになる。
『青春忘れもの』で最後に描かれるのは、青春時代を共に過ごした〔蟇(がま)ちゃん〕こと井上留吉との再会だ。知人から消息を聞き、新潟を訪れた池波は、二十数年ぶりに井上と会うが、「井上の胸の底には、私に語りたくても語りきれぬ何かがあるようであった」。井上のその後も印象深い。
同作は連載完結後、新潮社からではなく、毎日新聞社から刊行され、のちに中公文庫に入った。その後、新潮文庫から刊行された際、連載担当だった川野黎子は解説で、「この一篇が当然在るべき場所に納まったことが、当事者であった私にとっては実に嬉しい」と記す。
池波のエッセイ集には、食に関するもの(『食卓の情景』『散歩のとき何か食べたくなって』『むかしの味』『江戸の味を食べたくなって』)、映画に関するもの(『映画を見ると得をする』)、食や映画を含む生活について書いたもの(『日曜日の万年筆』『池波正太郎の銀座日記〔全〕』)などがある。
また、『男の作法』は、語り下ろしで男の生き方を説いたもの。山口瞳の『礼儀作法入門』と並び、新潮文庫のロングセラーになっているようだ。
『江戸切絵図散歩』は、時代小説を書くために必携の「切絵図」とともに、江戸の名残りをとどめる街をめぐるもの。カラーで収録された切絵図が美しい。写真にうつる街並みや建物の中には、いまは失われてしまったものも多いはずだ。
人はひとりでは生きられない
小説については、前編で『剣客商売』と江戸もの、中編で『真田太平記』と戦国もの、忍者ものを見てきた。
今回、紹介するのは、アウトローものだ。
このジャンルで有名なのは、なんといっても「仕掛人・藤枝梅安」シリーズ(講談社文庫)だ。梅安と彦次郎は金で殺しを請け負う〔仕掛人〕だ。
池波はこのシリーズで「『人間は、よいことをしながら悪いことをし、悪いことをしながらよいことをしている』という主題を強調し、血なまぐさい殺しの仕事をはなれたときの、彼らの日常生活を書きこんだ」としている(『殺しの四人 仕掛人・藤枝梅安(一)』あとがき)。
殺しなどの悪を描くことで、矛盾の多い人間の生き方が露になるというのは、ほかの作品にも共通している。
『雲霧仁左衛門』前・後編は、八代将軍・吉宗の治世における、盗賊一味の活躍を描くもの。
頭領である雲霧仁左衛門は、次のように描かれる。
〈中肉中背の均整のとれた体躯を、りゅうとした羽織・袴につつみ、立派な小刀をたばさみ、一分もすかさぬ武士の風体であった〉
犯さず、殺さず、貧しき者からは盗まずという「盗(つと)め」の掟を守り、一味の誰もお縄にかからずに、大きな盗みを成功させてきた。彼の元には、片腕と頼む木鼠(きねずみ)の吉五郎、目的となる家への引き込み役を務めるお千代らがいる。
盗賊であることにプライドを持つ雲霧は、「金が天下の世の中」に反感を抱いている。そして、十万両の盗みを最後にこの世界から引退しようとする。
そんな雲霧を追うのが、火付盗賊改方の役人たちだ。長官の安部式部を筆頭に、与力の山田藤兵衛らが一味の捕縛に情熱を注ぐ。
江戸から尾張、また江戸へと動く舞台や、登場人物の思わぬ動きが次の展開を生み出すストーリーの妙に、あっという間に二巻を読み終えてしまう。
痛快な味のある同作に比べると、ダークな感触を持つのが『闇の狩人』上下だ。盗賊の小頭・雲津(くもつ)の弥平次は、湯治場で若い浪人を刺客から救う。浪人は記憶を失っており、弥平次は彼を弥太郎と名付ける。姿を消した弥太郎は、その後、香師(やし)の元締・五名(ごみょう)の清右衛門の命に従って人を殺す〔仕掛人〕となる。
弥平次は盗賊の跡目争いに巻き込まれる。一方、清右衛門も自らが手にした地位を守ろうとする。
〈元締ともなれば、これを取り巻くすべての人の眼が、とたんにちがってくる。
威勢と権力が、どれほどの魔力をもっているかを、清右衛門は、はじめて知った〉
その魔力が無益な殺しを生み出すのだ。弥平次はこう自嘲する。
〈どうして、おれたちの世界は、いざとなると胸と胸が通じ合わねえのだろう。もめごとが起きれば、かならず血がながれる〉
好きな女と平穏に暮らしたくても、いちど足を突っ込んだら、相手を抹殺するか、自分が死ぬしか道はない。それは、記憶を失った弥太郎も同じだ。
『闇は知っている』の主人公・山崎小五郎は、寺の坊主だった時、興奮から女の首を絞めて故郷を出奔する。彼は殺し屋となり、「人の血にぬりつぶされて生きて」いく。
任務に失敗した小五郎が、それを命じた元締を殺害する場面は、鮮やかで恐ろしい。そして、最後に迎える彼自身の死も、一瞬のうちに終わる。
『闇の狩人』『闇は知っている』に、香具師の元締として登場する羽沢の嘉兵衛、五名の清右衛門、芝の治助、白金の徳蔵の名は、梅安シリーズでもおなじみだ。
羽沢の嘉兵衛は、『江戸の暗黒街』収録の「おみよは見た」にも登場。同書には「男の毒」「女毒」「殺」など、梅安シリーズにつながる短編が収録されている。
なお、同書解説で南原幹雄は、「香具師=殺し屋」というイメージは池波の創作で、「香具師は露店で売り買いをおこなうれっきとした商人」だと説明している。
歌舞伎や講談でおなじみの幡随院(ばんずいいん)長兵衛の活躍を描くのが、『侠客』上下だ。
浅草の舟川戸(のちの花川戸)で〔人いれ宿〕を営む長兵衛は、〔旗本奴〕の理不尽から町の人を守り〔町奴〕と呼ばれる。歌舞伎では、長兵衛は旗本の水野十郎左衛門の家に呼び出され殺害されるが、この小説では、長兵衛と水野は若い頃から互いを認めあった仲であり、水野はむしろ、他の旗本から長兵衛を守ろうとする人物として描かれる。
ほかにも、盗賊・夜兎(ようさぎ)の角右衛門と火付盗賊改方・長谷川平蔵が出てくる「看板」(『谷中・首ふり坂』)、凶状持ちの手越(てごし)の平八を主人公とする「さいころ蟲」「あばれ狼」「盗賊の宿」(いずれも『あばれ狼』)がある。
池波は、これらの作品で倫理が通用しない闇の世界を描くことで、「人はひとりでは生きられない」というメッセージを伝えようとしたのではないか。
幕末を生き抜く男たち
池波は戦国時代や江戸時代を多く書いたが、幕末を舞台とした作品も意外と多い。
1959年には「賊将」(『賊将』)を発表。主人公は薩摩藩の中村半次郎。「人斬り」の異名を持ち、西郷隆盛の右腕として活躍する。倒幕後には桐野利秋と改名し、陸軍少将になるが、征韓論争に敗れた西郷に従って下野。西南戦争で散った。
池波はこの人物が好きだったようで、同年には新国劇のために戯曲「賊将」を書き、のちに『人斬り半次郎』幕末編・賊将編という長編に発展させた。そこでは、自分の力を存分にふるい、動乱の世でのし上がろうとする半次郎の姿が描かれる。
同作のあと、『幕末新選組』『幕末遊撃隊』『西郷隆盛』など、幕末を舞台にした作品を立て続けに刊行。それが、1968年に「鬼平犯科帳」シリーズが開始されると、江戸時代のみに集中していったようだ。
『幕末遊撃隊』は、幕府が組織する遊撃隊の一員となり、五稜郭の戦いで死んだ剣士・伊庭八郎を描くもの。伊庭は時世の移り変わりに反して戦うことに、自分の存在を賭けようとする。
同作には上野広小路の〔鳥八十(とりやそ)〕という料亭が登場するが、池波は資料をもとにそこで出す献立を考えて、知り合いの料理人に見せたところ、「いいじゃありませんか。おかしくありませんよ」という答えをもらったという(「新選組異聞」『戦国と幕末』角川文庫)。そこまでやるか! と驚いた。
ほかにも、『近藤勇白書』(角川文庫)や、架空の旗本が主人公で中村半次郎も出てくる『その男』全三巻(文春文庫)があり、時代が下ると、日露戦争時の乃木希典を描いた短編「将軍」(『賊将』)などがある。
新しい芸を二つ三つ
最後に、現代小説について。この分野は池波にとって、出発点であると同時に到達点だった。
1954年、池波は師の長谷川伸のすすめにより、小説を書きはじめる。その最初の作品「厨房(キッチン)にて」(『夢の階段』)は、長谷川が主宰する同人誌『大衆文芸』に発表された。
同作の舞台は、日本に住むアメリカ人パイロットの邸宅。妻とともに住み込みで働く圭吉に、弟が母の遺品である写真を見せる。そこには、戦争中に出会った下士官が写っていた。
横浜の部隊にいた圭吉が、外出禁止を破って東京の自宅を訪れるエピソードは実体験で、自伝『青春忘れもの』に書かれている。
また、「娘のくれた太陽」(『夢の階段』)の主人公・長太郎も税務事務所の徴収員であり、池波の体験が色濃く反映されている。
吉村昭は池波との対談で、「母」という短編を「とてもすばらしい小説だ」と褒めている(「対談 東京の町と人情」『新年の二つの別れ』朝日文庫)。独立心が強い母の肖像を描いたものだが、池波自身は「どこをほめてくれるんだかわかんないな」と答えている。同作は『完本池波正太郎大成』第二十八巻(講談社)に収録されているが、この巻の月報でも、吉村は同作の印象を記している(「池波さんと『母』」)。
池波は1960年代前半までに「禿頭記」「機長スタントン」「踏切は知っている」(いずれも『夢の階段』)などの現代ものの短編を書いた。また、「牧野富太郎」(『武士(おとこ)の紋章』)は、同名の戯曲を書くために本人に取材したエピソードが描かれており、晩年の牧野博士の姿を伝えている。
現代ものの長編としては、『青空の街』(集英社文庫)がある。建設会社社長の息子・弘が、自分の生きる道を求めて試行錯誤する様を描く。長い作品だが飽きずに読める。ただ、ほとんどの登場人物が底抜けの善人で、明朗な話に終始するところが、いま読まれていない理由かもしれない。
池波はその後、時代小説に集中し、現代ものから離れる。
しかし、六十代に入り、ふたたび現代ものに帰ってくる。それが、本誌『波』1987年1月号から連載した『原っぱ』だ。
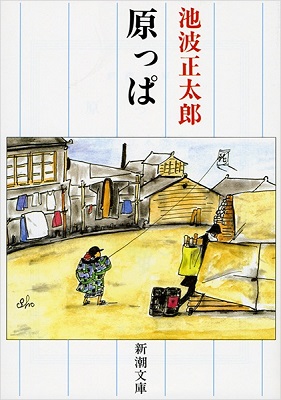
〈劇作家時代をふくめて、物を書く仕事を四十年近くもつづけて来た私だが、そんなことをすべて忘れて、先ず、初心に返りたいと念願しているのだ〉
六十を超えたことでかえって気持ちが自由になり、現代小説にチャレンジしたいと考えたと、池波は書く。その一方で、いつ病魔に見舞われるかは判らず、「老年にゆるされた平安は、一瞬のものにすぎない」という覚悟も示す。連載開始の半年以上前に、その決意を示すところが、いかにもこの人らしい。
満を持してはじまった『原っぱ』は、それまで池波が忌避してきた私小説の色合いが濃い作品だ。
六十歳を過ぎ、劇作家を引退した牧野のもとに、俳優の市川扇十郎が電話をかけ、牧野の作品を再演したいと申し出る。いちどは断った牧野だが、周囲の人々のすすめに、ふたたび情熱を取り戻す。
同作のもうひとつの主題は、過去との再会だ。
牧野は地下鉄駅の地下道で暮らす浮浪者が、尋常小学校の時の佐土原先生であることに気づく。牧野は当時のことを想起する。先生は牧野に「苦学の道はいくらもある。おもしろいぞ苦学も」と語る。
牧野は地下道の先生に酒を届けるが、先生は姿を消す。
また、小学校の同級生だった田村は、地元で喫茶店を営んでいる。周りは地上げが進み、ついに彼の店も閉めることになった。近くにあった原っぱは、マンションが建とうとしている。この地を離れる田村は、新しい土地で「旅をしているつもりで暮せばいいんだ」と話す。
「ねえ、これから、東京は、どうなって行くのだろう?」「東京なんて、もう無いのも同然だよ」と、二人は言葉を交わす。
その一方で、孫の高男は牧野の仕事に興味を持ち、来年の芝居を観に行きたいという。距離を置いていた女優の娘との関係も修復しそうだ。
「おじいちゃん、書いてね」という言葉に励まされるように、牧野は原稿用紙に向かう。
同書の解説で川本三郎は、「『原っぱ』は、牧野と娘、孫の関係を描いた家族小説であり、牧野の周辺の俳優たちや友人・職人たちを描いた江戸市井(しせい)小説ならぬ、東京市井小説である」と評する。
同作より五年前、池波は「ドンレミイの雨」(『江戸の味を食べたくなって』)という短編を書いている。
フランスを旅行中の「私」は、ドンレミイ村で以前、パリで会った男を発見する。
パリの旧中央市場跡(レアール)に〔B・O・F〕という酒場があり、セトル・ジャンという老亭主が切り盛りしていた。すっかり気に入った「私」は翌年もその酒場を訪れるが、周りには大きな地下街ができ、店は閉まっていた。その後、若い男が店を引き継いだと聞く。それが、ドンレミイで会った男だったのだ。
「私」は再度パリを訪れるが、〔B・O・F〕は消えていた。そして、ドンレミイの男は、カフェの席に座ったまま涙を流している――。
〔B・O・F〕もセトル・ジャンも実在し、池波はエッセイで何度となくその名前を出している。
そして、『原っぱ』の続編として、『波』1990年3月号から連載がはじまったのが「居酒屋B・O・F」だ。
芝居の脚本を書き進める牧野のもとに、以前のフランス旅行の同行者から、郊外の町でセトル・ジャンを見かけた人がいるという手紙が届く。牧野は「ジャンはパリを離れるような老人ではない」とおもう。
池波の死去により、この一回が絶筆となってしまったが、続けられていたら、どんな物語になっただろうか?
誰も知らない町への旅
池波は1990年3月、急性白血病で入院し、5月3日に亡くなる。六十七歳だった。大正の終わり頃、関東大震災の年に生まれ、平成のはじめに亡くなったわけだ。
葬儀で、山口瞳は「旅する人よ」からはじまる弔辞を読んだ。
山口は『原っぱ』を、池波の東京に対する別れの挨拶だと指摘する。そして、次のように弔辞を終える。長いが引用する。
〈池波正太郎という小説家は“旅する人”であったのです。池波さんは、大好きなパリやヨーロッパの田舎町に何度も旅行しました。戦国時代にも旅したことがありましたし、むろん、御自分の町である江戸には長逗留(ながとうりゅう)しました。大正や昭和の東京の町も歩きました。戦後の東京だって、結構面白がって旅していたと私は思っています。
いま、池波さんは、私たちの誰もが知らない、住み心地のいい懐しい感じのする町に旅しているのだと私は思っています。池波さん、ゆっくりと楽しい旅を続けてください〉(山口正介『正太郎の粋 瞳の洒脱』講談社文庫)
八十四冊を一気読みしたいま、さらに多くの池波作品を読みたくなっている。次は『鬼平犯科帳』か、それとも『仕掛人・藤枝梅安』か。(了)
(なんだろう・あやしげ 編集者/ライター)








