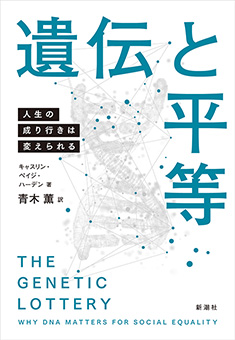対談・鼎談
2024年1月号掲載
『遺伝と平等 人生の成り行きは変えられる』刊行記念対談
遺伝学と社会学がつながるとき
青木薫(サイエンス翻訳家) × 大澤真幸(社会学者)
アメリカで話題沸騰!
親ガチャを乗り越えるために今こそ、私たちができること。
対象書籍名:『遺伝と平等 人生の成り行きは変えられる』
対象著者:キャスリン・ペイジ・ハーデン/青木薫訳
対象書籍ISBN:978-4-10-507351-0

遺伝学に起こっている「革命」
大澤 青木さんの訳されたものは以前から読んできました。翻訳が的確で、内容も重要なものが多いので、選択眼も含めて信頼しています。特に青木さんの日本語はすばらしいので、感心してきました。本を読む快楽、これをいつも、青木さんの翻訳作品には感じます。
青木 ありがとうございます。
大澤 『遺伝と平等』も読ませて頂きました。タイトルの通り、遺伝学の最先端を解説した第I部と、その知見でどんな社会をつくるかという第II部に分かれますね。
青木 はい。第I部は、最新の遺伝学、特に遺伝統計学の進展についてです。中でも、ゲノム全体を量的なアプローチで調べていく、「GWAS」という最新のゲノムワイド関連解析により精度が上がり、目や髪の色、身長の高さだけでなく、性格や能力にまで対象が及ぶ段階に入り、GWAS革命とまで呼ばれるようになった。この新展開が一般にはまだほとんど紹介されておらず、専門書となるといきなり難しい。
大澤 この本は違いますね。著者のハーデンは噛み砕いて易しく、わかりやすい喩えを使って、でも高度な内容を妥協せずに説明している。
青木 性格や能力といった社会的に非常にデリケートな領域でも遺伝との関連性が可視化されると、それ見たことか、人間には優劣がある、全員が生きるに値するのか、と短絡的に結論づけられてしまうリスクも、もちろん生じます。
大澤 そうする人が必ず出てきますね。優生学的な考え方ですね。
青木 それを否定するあまり、「遺伝なんて関係ない」「どんな人でも才能を開花できる社会をつくるべきだ」という反応をする人もいる――ハーデンはこの立場を、ゲノムの違いに目をつぶる、という意味で「ゲノムブラインド」と称します。でも、ハーデンは、どちらの側でもないんです。人類には優劣があるという優生学的な考え方はとんでもないけれど、一方で、それを見ないことにするのもダメだと。
大澤 はっきりと書いていますね。
青木 第II部は、サイエンステクノロジーの発展がこれだけ多岐にわたるなか、それなら私たちはどんな社会をつくりたいのかを問うています。つくりたい社会にしていくために、科学の知見をどう利用していくか、ということです。専門的で複雑な遺伝の話を、自分のスタンスを明確に打ち出しながら、ここまでわかりやすく説明しているという点で、類書がないと思います。そのスタンスとは、公正、フェアであること。「公正としての正義」という立場ですね。
大澤 そのフェアネスが難しい。そもそも、この本を翻訳しようと思ったきっかけはどこにあったんですか?
青木 それはやはり子育てだと思います。ハーデンも二人のお子さんを育てていますが、私も二人育てています。そして、親を同じくする子供でさえ、生まれたときからこうも違うか、という経験をしている。
でも保育園時代には、「どんな子供も生まれた時は同じだけの可能性を持っている」というスローガンをよく聞きました。もちろん、そうであってほしいですよ。でも、現実にはひとりひとり違う。大きく違う可能性を持って生まれてくる。
実際の違いを無視していたら、それぞれに必要なサポートや手助けだってしてやれませんよね。それでいいわけないでしょ、とハーデンに背中を押された気がしました。
誰もが大量に引く「遺伝くじ」
大澤 この本の原題は「The Genetic Lottery」、「遺伝くじ」ですよね。私たちは誕生時に、すでにいろんなくじを引かされています。
青木 20世紀後半の日本に生まれるか、戦下のアフガニスタンか、多くのくじの結果を合わせると、「自己責任」などと言える部分はほとんど残らない。くじの結果はその人の手柄でも落ち度でもない、とハーデンは繰り返し言います。ですが、それはひとつの解釈です。同じ科学の成果を見て、「人間には生まれもった優劣がある」という優生学的な解釈をする人もいる。
大澤 科学は、どうすべきかは教えてくれませんからね。
青木 ただ、大澤さんなら科学と社会の関係、ハーデンの抱く危機感を解読してくださる気がしています。
実は、この本を翻訳している間に、何度も大澤先生を思い浮かべました(笑)。数多いご著書の中でも『社会学史』(講談社現代新書)という一冊で、社会学というのが、近接の学問はもちろん、社会や人間全般に関わるもので、社会史全体をとらえておくことは全ての学問にとって大事だと教えてもらいました。平易な言葉で大きな教養が頭に入ってくる喜びもある本ですよね。
大澤 そうでしたか。ありがとうございます。社会秩序がいかにして可能かというのは、社会学の分野の、固有の主題です。この主題とともに社会学は成立したとも言える。ですが、その歴史はたかだか二百年。哲学や自然科学の歴史を考えると、若い学問です。
青木 未来の社会秩序はいかに可能か、訳しながら何度も考えました。
大澤 人間を特別にとらえる宗教的な世界観は、何らかの意味で人間仕様につくられていますが、自然科学は、基本的には人間中心主義を超え、離れることで成立します。人間という主体をどう組み込むかという問題は、社会科学や哲学の援軍を必要とする。だからこの本は、社会科学的な問題と自然科学的な問題の、理想の結婚と言えますよね。
青木 そうなると思います。社会を考える上で必要な情報がある。ただ、勘違いしやすいところですが、科学が教えてくれる自然界の膨大な情報に対して、私たちがニュートラルに情報を選べるかというと難しく、なにかしら主観や意図が混じりこんでくるんですよね。
大澤 そう、そして、とくに遺伝学は、社会や政治との付き合いに一度失敗しているから、お互いに距離をとりすぎているのかもしれない。本来は正しく使われれば、「良き社会」に大きく貢献するはずです。
とはいえ、「良き社会」を考え始めるとたいてい、ロクなことにならない。哲学者の市井三郎が『歴史の進歩とはなにか』(岩波新書)で喝破したように、「進歩」に見えたのにマイナスだった、ということが一般的です。人間の価値観だってゆらいで一定とはいえません。合意が簡単には生まれない世界では、「中途半端な良き社会」になると不幸な人がむしろ増える。経済的に豊かなら幸せなはずなのに予想外に不幸だったり、「自己責任」の強調が弊害をもたらしたり、社会主義が典型ですが、自己破綻を起こしがちです。
青木 まったくその通りです。
大澤 でも、市井は、ひとつだけ、進歩を意味する消極的な条件があるとしていて、僕も賛成です。不条理な――つまり自分の責任によらない偶然の――不幸や苦痛がより少ないこと。ぼくらはみな、あなたの責任ではないことであなたが不幸になることが、できるだけ少なくなるように願っている。
青木 遺伝学の成果がそういう社会の実現に役立ってほしいです。
大澤 偶発的な災害の被災者を救いたいように、遺伝のことで不幸になる人がいたらできるだけ助けたい。くじに外れただけで不幸になる人を救うことができる社会の方が良いのではないか。
遺伝学にもビッグデータの時代
青木 おっしゃる仕組みについては、具体的に方向性が見えてきたといえますね。ただ、「ChatGPT」でも「GWAS」でも、データ学習の量がブレイクスルーを迎えていますよね。子どもたちの時代はどうなるのかと心配になってきます。
大澤 心配になる人もいるだろうし、それなら遺伝子を改造したいという人も出てくるかもしれませんが、この本は、希望通りの改造は事実上不可能だということも教えていると思います。
ある種の遺伝病、たとえばハンチントン病など、単一の遺伝子に原因がある場合は別ですが、認知能力やあるいは高身長のようなもっと単純なものも含め、僕らが評価する能力や性質の大半は遺伝が関係しているけれども、それらは多数の遺伝子のものすごく複雑な因果関係の結果です。ある遺伝子を改造すれば、それは予期できない因果関係を通じて、別の能力や性質に否定的な結果を招きかねない。それどころか、ねらっていた能力や性質に対してさえ逆効果ということもありえます。遺伝子への介入を通じた意図的な改造は、事実上、不可能なのです。
しかし、ある能力や性質に遺伝の影響があることが実証できていれば、遺伝子への直接的な介入とは別の方法で、不運を補償し、公正に近づけることができるわけです。
青木 詳しくお聞かせください。
大澤 この本ではっきりしたのは大きく二つだと思います。一つ目は、遺伝は複雑系で、それを下手にいじるとロクなことはないということです。二つ目に、複雑であっても、最終的に遺伝くじが関係していることが明らかならば、その「違い」に対しては、「公正としての正義」の観点からの補償や救済が可能だということです。
青木 「違い」に踏み込んで、有効に行動すべきですね。必要な手助けや公正平等を考えると、ゲノムブラインドは有効とは言えない。科学の使い方という観点で、新しい知見が出た時にどう生かすかは、人間や社会の方に委ねられているということでもあると。
大澤 科学と社会の関係で言うと、現代では科学の方のスピードが速いんですよね。我々がどう対応すべきかを定めるのがどんどん難しくなっている。科学的に可能なものをただ実行しているだけで、気づかぬうちに、これまでの常識や前提が破壊されていく。
ChatGPTのような、大規模言語モデルの場合もそうです。その能力は、開発者の予想すらもはるかに凌駕している。今は、利用してよいものと、現時点では利用を抑制すべきものに分ける必要があるかもしれない。
青木 遺伝でいうと、ゲノムをいじって望む結果が得られるほど、シンプルではないということですね。
そして、遺伝くじの結果のせいでアンフェアな事態が生じるなら、フェアになるように社会的に手助けしたい。
大澤 本書で使われている「公正としての正義」という言い方は政治哲学者のジョン・ロールズの言葉です。ロールズを批判する倫理学者や哲学者はたくさんいますが、人文社会科学系の学問の常として、批判する人が多いものほど、優れています。ロールズは明晰に「正義の原理」を定式化している点で、やはり基礎中の基礎だと思う。例えば累進課税はロールズが提起した「格差原理」という考え方で正当化できます。金持ちが損をするので不公平ですが、一番恵まれない人が得をする政策なので、正義に適っているというわけです。
しかし、所得や資産の不平等より、遺伝が原因の不平等の方がより深刻です。長年その内実がわからなかった。そして、わかっているつもりでなされた措置は、とんでもない不正義や痛ましい結果をもたらした。しかし遺伝統計学の進歩によって、遺伝学は新しい局面に入ったわけです。そのような遺伝学ならば、公正な社会を実現するために活用できるし、活用すべきだというのが、ハーデンが勇気をもって主張したことでしょう。
青木 もちろん正義論はロールズの後に進展がありますが、ハーデンはおそらくそこまで視野に入れている。例えば障害者の問題もそうです。社会科学と自然科学の両輪、重要ですね。
※この対談は、2023年10月20日、東京・代官山蔦屋書店にて行われた(あおき・かおる サイエンス翻訳家/おおさわ・まさち 社会学者)
最新の対談・鼎談
-
2025年6月号掲載

万城目 学『あの子とO』刊行記念
ゴッドファーザーにご挨拶

あの子とO
-
2025年6月号掲載

特別対談
消化器内科医兼小説家の二刀流対談

受け手のいない祈り
-
2025年4月号掲載

西岡壱誠『それでも僕は東大に合格したかった─偏差値35からの大逆転─』、池田 渓『東大なんか入らなきゃよかった』文庫刊行記念
いつか、東京大学で

それでも僕は東大に合格したかった―偏差値35からの大逆転―(新潮文庫)

東大なんか入らなきゃよかった(新潮文庫)
-
2025年3月号掲載

こいしゆうか『くらべて、けみして 校閲部の九重さん2』刊行記念
校閲者たちかく語りき

くらべて、けみして 校閲部の九重さん2