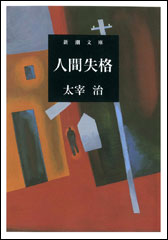書評
2024年3月号掲載
私の好きな新潮文庫
増殖する『人間失格』
対象書籍名:『人間失格(装画:城所昌夫、昭和43年43刷より)』/『人間失格(装画:山下清澄、昭和56年89刷より)』/『人間失格(カバー装幀:唐仁原教久、平成18年156刷より)』
対象著者:太宰治
対象書籍ISBN:978-4-10-100605-5
『人間失格』を初めて買ったのは高校生のときだった。奥付を見ると「昭和四十二年 四十二刷改版」とある。
人間をうまくやれず、それでも人間を諦め切れなかった大庭葉蔵という男の人生が、そこには書かれてあった。こんなに間違っても、他人に迷惑をかけ続けても、人は人に赦されてしまうのか。生きる気力や苦悩する能力をさえ失ってなお、生かされてしまうのか――。失敗の模倣とも呼べる彼の生きざまに、けれど私が見たのは希望だった。そのとき思い悩んでいたことが急にちっぽけに思えた。「お前はこの先もっと絶望していく」と頬をはたかれたようで、なぜか力が湧いた。一冊の本を読む前と後とで人生観が変わる体験をしたのも、これが初めてだった。
しかしある日図書館で、その出来事を友人に話したところ、わかりやすく彼女は引いた。「あんな暗い小説」「女の子が太宰好きとか言わないほうがいい」的なことを言われたように記憶しているけれど、はっきりとは覚えていない。私は私でとてもショックを受けていたのだ。
彼女の座る後方には文庫本の棚があって、一角が赤く染まっていた。当時憧れていた先輩がその前に立っていて、数冊を抜き取った。角川文庫の片岡義男だった。太宰治は伝わらないし、先輩にも手が届かない。手元の背表紙の黒がやけに目について、家に帰る途中、カバーを外してゴミ箱に捨てた。いま思えば、あまりに幼稚な腹いせだったと呆れるけれど、だから一冊目の『人間失格』にはカバーがない。
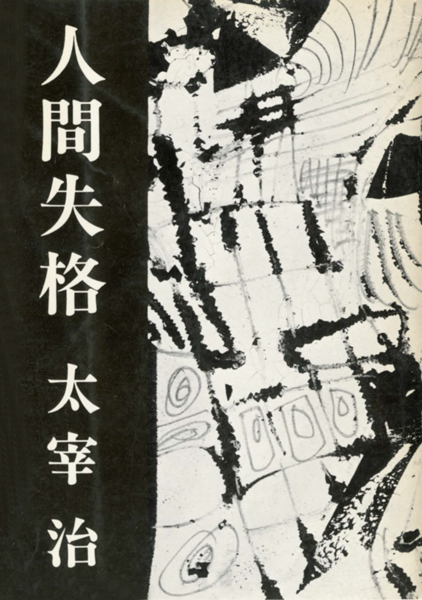
それでも『人間失格』が希望の書であることは揺るがなかった。
私が感じたことは本当だし、誰もそれを否定できない。私は私の感覚に正直でいたい。思いを行動に移したのは、大学進学を機に上京した春だった。太宰治の文庫本を買い揃えて、黒く並んだ背表紙を見ても、もうカバーを外さないと決めた。なぜ太宰が否定的な読み方をされてしまうのか知りたいという好奇心もあって、怖がらずに人と話すようになった。そんなふうにして、他人を、自分自身を知っていった。
『人間失格』が増殖していったのはこの頃からだ。
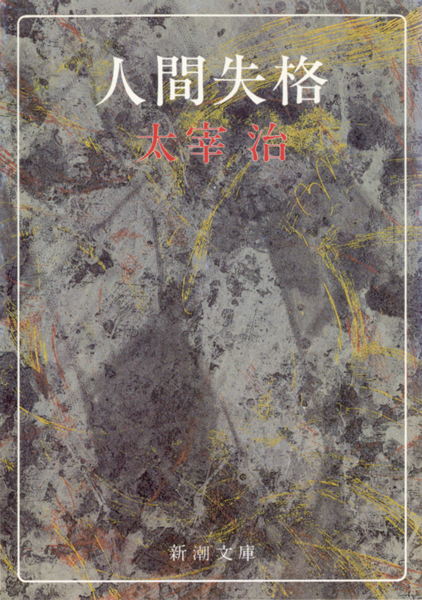
まったくこの小説は、読むたび姿かたちを変えて「なにが見える?」と問いかけてくる、お化けみたいな存在なので、一冊を大事に読み続けるには不向きなのだ。私のように書き込み癖のある者の手にかかれば、全ページ真っ赤になるのなんてすぐで、読んでる「今」必要な視点がぼやけてしまう。それで、必要なたびに新調することにした。どの古本屋にもほぼあって、かつ廉価で買えた新潮文庫は、とてもありがたかった。
仕事で使った『人間失格』を時代順に並べてみれば、思考が深くなっていくのがわかって面白い。例えばある本を開くと、「第一の手記」で父親が東京出張に行くシーンの、「シシマイ」の文字が赤い丸で囲んである。脇には「→P139」の書き込み。自分で仕掛けた謎を自分で解くようで、楽しい。
問題は、私用で使った文庫本だ。恋人にこっぴどく振られたとき、東京に挫折して故郷に逃げ帰ったとき……。予言書を開くように、あるいは答え合わせをするように『人間失格』を読み、余白に思いを綴っていたそれはもはや鍵の必要な日記帳だ。いまの時代、SNSの生前整理が肝要だと言われているけれど、私の最重要課題は、これをどう処分するかにある。
数を買い重ねていれば、版にも好き嫌いが出てくる。一番のお気に入り&冊数が多いのは「昭和六十年 百刷改版」で、この版で読む『人間失格』が最もよく目に馴染んでいる。どこに何が書かれてあるか、見開きが絵のように浮かぶ。
直近で買い求めた文庫本は、「平成十八年 百五十六刷改版」のものだ。見ると、「第三の手記」の最後の一行にツッコミがしてあって、笑ってしまった。
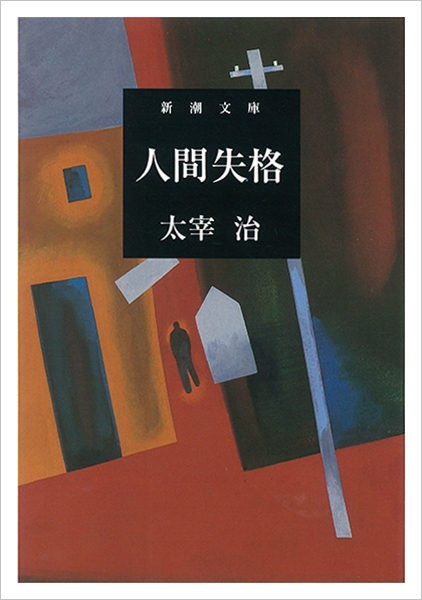
「自分はことし、二十七になります。白髪がめっきりふえたので、たいていの人から、四十以上に見られます。」
このうち「四十以上に見られます。」だけがページをまたいでいることが、気に食わなかったのだろう。その部分を縁取りして、脇に「オイコミ」と書き込んである。文字組みにまで口を出しているではないか。何様のつもりか。ただ、こんな機会も滅多にないので最後に申し上げます。
新潮文庫編集部の皆さま、次回改版の際には、「オイコミ」、ご一考ください。
(きむら・あやこ コトゴトブックス店主)