書評
2024年4月号掲載
私の好きな新潮文庫
冒険家が考える三つの自然との向き合い方
対象書籍名:『無人島に生きる十六人』
『凍』
『楢山節考』
対象著者:須川邦彦/沢木耕太郎/深沢七郎
対象書籍ISBN:978-4-10-110321-1/978-4-10-123517-2/978-4-10-113601-1
冒険家と名乗っていると、強固な意思であらゆる困難に立ち向かっている、などと誤解される。
私が赴く北極や南極は確かに困難に満ち溢れている。しかし、人間の意思は自然には到底敵わない。私たち冒険者は、あくまでも、自然の動きに即して調和する必要がある。圧倒的な自然に対して、様々な形で向き合った三冊を選んだ。
『無人島に生きる十六人』は、明治時代のサバイバルノンフィクション。南太平洋の珊瑚礁で座礁した日本の帆船には、十六人の男たちが乗っていた。珊瑚礁の小島では井戸も掘れず、食べられそうな植物もない。そこから十六人の創意工夫のサバイバル生活が始まる。

遭難記、漂流記と呼ばれる読み物だが、本書は子供たちにも読めるように平易に書かれ、豊かな文章で明るさすら感じられる。人間の強さ、自然に対する無力さ、仲間の大切さ、創意工夫の楽しさ、たくさんの要素が詰まっている。
遠い地で故郷を想い、美しい日没に感動する男たち。なんだか、漂流も悪くないな、なんて勘違いしてしまう感動作だ。
沢木耕太郎が日本を代表する登山家、山野井泰史を取材して書き上げた『凍』は、山岳ノンフィクションの傑作。
2002年、山野井は登山家の妻と二人、ヒマラヤの高峰ギャチュンカン登頂に挑む。山頂直下で妻が体調不良を訴え、山野井は一人で登頂。引き返し妻と合流すると、いつまでも語り継がれるであろう「奇跡の生還劇」が始まる。
下山を試みる二人に襲いかかる度重なる雪崩、高所の低酸素による視力低下、凍傷、決死のビバーク、死の影が明確に二人に迫るが、二人は諦めない。ジリジリと息の詰まる描写はまるで、日本刀の刃先を渡るようだ。
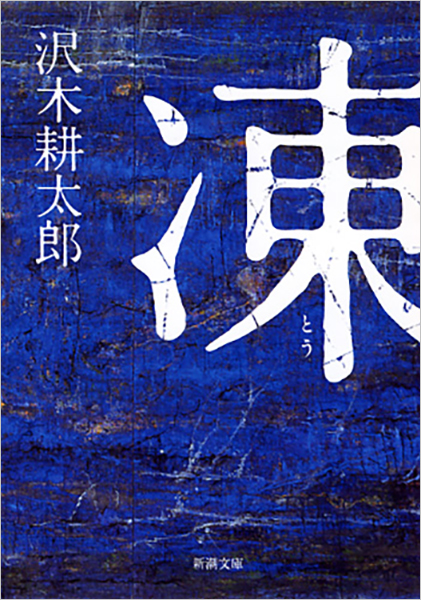
山野井泰史の超人的な登攀能力、危機的状況への冷静な判断力は、冒険者として目を見張るものがある。
そして本書を名著たらしめているのが、沢木耕太郎がまるで山野井の横でその登攀全てを見て体験してきたかのような、圧倒的な臨場感だ。
最後に紹介する『楢山節考』は、一転して趣の異なる作品だと思われるかもしれないが、私にとっては同じ文脈にある。
江戸時代ごろであろうか、信州の山深い集落が舞台。この村では年寄りが七十歳を迎えると「楢山まいり」が行われる。「山へ行く」と言い換えられるその行為は、要は口減らしのための姥捨である。
主人公の老婆おりんは、正月が来る前に、自分が「楢山まいり」をすることをかねてより心待ちにしていた。息子の辰平も、最近になってようやくその気になってきたことに安堵し、楢山まいりの準備をする。
現代の私たちからすれば、この物語の内容は不思議なことだらけだろう。姥捨、楢山まいり、全ては現代の言葉に置き換えれば自殺である。
冒険や探検の世界では、圧倒的な自然の中、人間の意思の力で困難を乗り越えていく、という話が多い。しかし、主人公おりんは意思の力で自然に対抗することはない。
先に紹介した『無人島に生きる十六人』は、漂流という意図しない状況に受動的に対応する物語であり、山野井泰史は高峰から能動的に生還していく物語だ。受動であれ、能動であれ、どちらにも意思が感じられる。
しかし『楢山節考』のおりんは違う。能動でも受動でもない、哲学者の國分功一郎が紹介し広く知られた「中動態」におりんは生きている。
もしおりんが現代に生きていたら、七十歳を機に自殺をすることはないだろう。江戸時代、雪深い山村、そのような意思や選択の余地のない運命が、おりんを山に向かわせる。
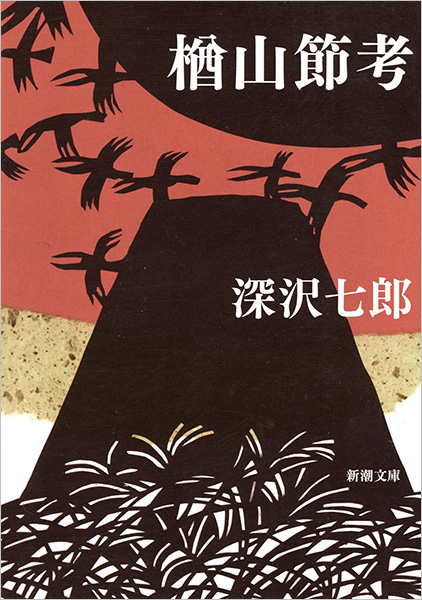
私たち冒険者もまた、心の奥深くに意思の介在しない領域を抱えている。
衝動は意思であろうか。数えきれない人との交わり、意図せず見聞きしたもの、今の私に至るそれらすべてが私を作り、形作られた私に衝動が沸き上がるとき、そこに意思はあるのか。
明治の男たちの前向きな姿勢、山野井泰史の命の燃焼、おりんの気高さ。三者三様に、意思を握りしめることも、手放すことも、人間存在の強さと美しさがそこにある。
(おぎた・やすなが 20年間で16回の北極行を経験した「北極冒険家」。2018年には日本人初の南極点無補給単独徒歩到達に成功。植村直己冒険賞受賞。神奈川県で冒険研究所書店を主宰)









