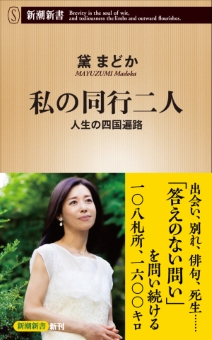書評
2025年2月号掲載
哀しみを生きる力に変換する「場」
黛まどか『私の同行二人―人生の四国遍路―』(新潮新書)
対象書籍名:『私の同行二人―人生の四国遍路―』
対象著者:黛まどか
対象書籍ISBN:978-4-10-611073-3
一昨年の秋、二度目の歩き遍路をした。八十八札所に別格二十札所を加えた百八札所、約千六百キロの道のりだ。最初の遍路(2017年)のときに気が付いたことだが、意外にも身近に「四国遍路をしたことがある」「いつか歩いてみたいと思っている」という人がたくさんいた。
今や四国遍路には世界中から老若男女がやってくる。「人生の転機に」「空っぽになりたくて」……。国や年齢を問わず、現状に“生きづらさ”を感じている人が多いのだと思う。
飛行機や新幹線などでの移動、インターネットによる高速の情報網など、私たちは猛スピードでひた走ることを無意識のうちに強いられている。“生きやすさ”を求めて世の中全体が効率を優先してきた結果、逆に“生きづらい”世の中になっているということではないか。
四国の山と海の辺地を歩き継ぐ遍路は、私たちが自然の一部としての人間であることを折々に自覚させる。生き物としての人間が歩き、他者(自然や人)と出会い、立ち止まり、考え、煩悶し、丸裸になってゆく。“自分”というフレームが消えるとそれまでとは違う思考が表出し、生き方すら変わる。まさに人生のルネッサンスだ。
昔はどこへ行くにも歩いて行った。「歩くこと」がウォーキング、散歩など独立した行為になったのは近代に入ってから。「長く歩くことへの回帰は、肉体のゆっくりした進み方や筋肉や呼吸への負荷を通して、私たちを自然の中に再び組み入れる。(中略)昔からの、深く、宇宙的なリズムが戻ってくる」(『歩行する哲学』ロジェ=ポル・ドロワ)。
振り返れば、サンティアゴ巡礼道、韓国(プサン―ソウル)、熊野古道、四国遍路と四千キロ以上を歩いてきた。歩くリズムは普段閉じていた感覚を開き、日常とは違った思考回路へと導く。歩くことは発想やひらめきの源泉だ。ドロワの言う遠いところにある根源的なものだ。
雨の日は、靴の中までびしょ濡れになり、寒さに耐えながら歩いた。大雨に遭った日、私は大失敗をする。ウエストポーチに入れていた日記帳を判読できないほど濡らしてしまったのだ。その時、私自身が「雨そのもの」になったように感じた。
桜の下では花吹雪を浴びて私も「桜」となり、囀りが降る中では、私の声は完全に鳥の声に紛れていた。自然という「大きな命の連なり」の一部として、花鳥風月と一期一会を果たす……その交歓は、私の俳句であり、且つ生きる喜びでもある。
四国遍路の歩行による円環は、巡礼者を螺旋状に少しずつ高みへと引き上げてゆく。生きづらさや悲しみを抱えて四国へとやって来た遍路たちはやがて桎梏から解き放たれ、自らを赦し、運命との和解を果たしてゆく。辛い経験や哀しみを、生きる力に変換する「場」、それが四国遍路だ。
(まゆずみ・まどか 俳人)