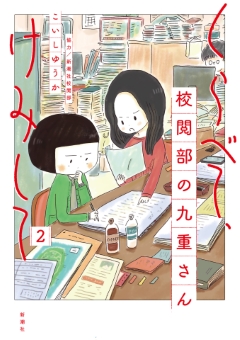対談・鼎談
2025年3月号掲載
こいしゆうか『くらべて、けみして 校閲部の九重さん2』刊行記念
校閲者たちかく語りき
こいしゆうか × 高松恭則 × 勝俣翔多 × 佐藤 瞳
社の垣根を越えて集まりし校閲の猛者3名と、校閲マンガの著者。普段表に出ない裏方たちの本音が漏れる……!
対象書籍名:『くらべて、けみして 校閲部の九重さん2』
対象著者:こいしゆうか
対象書籍ISBN:978-4-10-355392-2

こいし 今日はみなさん集まって下さりありがとうございます。フリー校閲者の佐藤さんは、何を隠そう、差別表現と戦う回(2巻収録の12話と13話)で描いた外校(社外校閲者)の丸山さんのモデルです。モデルというか、佐藤さんそのものです(笑)。佐藤さんからお話を聞いたのはだいぶ前ですが、こんなにインパクトのある若い校閲者の方にお会いしたのは初めてだったので、びっくりして。
佐藤 漫画を拝見して、丸山さんの作画に爆笑してしまいました。私の印象とはいったい……?(笑)と思いましたが、私がお話ししたことが漫画になっていく過程も含め、とても楽しくやりとりさせて頂きました。
こいし キャラとして立たせたいと思い、佐藤さんをデフォルメして描いた結果、ああなりました(笑)。佐藤さんは内容的に危うさを感じるゲラを読んだ時に、編集者や社の校閲担当の方に手紙まで書いたというお話をされていましたよね。それをちゃんと物語として昇華させなければと思っていました。
勝俣 2巻の帯が急に社会派になっているのを見て、おっと思いました(笑)。
こいし 私も、こんなに攻めてる漫画だっけと……(笑)。この回に関しては自分の作風にはないようなシリアスな話だし、簡単には扱えないテーマなので、ネームがとにかく難しかった。でも、佐藤さんに意見を聞く度にとても解像度の高いお返事を毎回もらい、新潮社の校閲部部長からも的確なアドバイスやご意見を頂いてようやく形にできました。
佐藤 丸山さんの回は結構際どいというか、内容的にだいぶ攻めていますよね。実際、使っている言葉自体が差別表現ってわけじゃないけど、結果的に差別として作用し得る物語に対してどうするか、というのは常に難しい問題だし、校閲者として悩むことも多いんです。そういう難しい話を漫画にして頂けて、有難かったです。
こいし あの話をどうまとめるか、あの終わり方で良かったのかどうかは今でも気になる時があります。
佐藤 とてもきれいなお話にしてもらえて、カタルシスがありました。現実にはそんなにうまくいくことってなかなかなくて、一緒に戦ってくれる丹沢君みたいな社員校閲者もほとんどいないし、話をちゃんと聞いて理解してくれるような編集者もそうそういない。だから、こんな世界があればいいのにと思いながら読みました。
高松 佐藤さんが仰ったのと同じように、差別を告発するような意図で書かれた作品で、事実を伝えようとするあまりにそのエピソードの回収ができずに、逆に差別を促しかねないようなゲラが以前、弊社でもありました。その時は編集に伝え、結果的に著者の方がうまく修正して下さったんですね。最終的に判断するのは著者なんですけども、的確な疑問を提示することで作品の質を上げていくのが私たちの仕事だと思います。
こいし どこの出版社にも起こり得る話なんですね。
高松 はい。私は集英社に入る前は新聞社におりまして、新聞なり、本なりにずっと携わってきて思うのは、出版物は現実社会とつながっているということ。コンプライアンス云々が最近やたらと言われるようになりましたけど、抑圧されていた人たちが異議申し立てをすることが見えるようになっただけで、昔からそういう構造はあり、その事実に目を向け、常に頭に置きながら校閲するべきではないかと。
こいし そう言えばこの回を描いたとき、「新潮45」休刊のきっかけとなった記事に対して編集や校閲はどうだったのかということに、この漫画の担当編集さんが興味を持っていましたね。社内で当時の関係者にいろいろ話を聞いたみたいなのですが、記事に対する責任の所在や編集と校閲の役割についてとても考えさせられたと言っていました。
高松 作中でそれらしきセリフが少しだけ出ていますね。
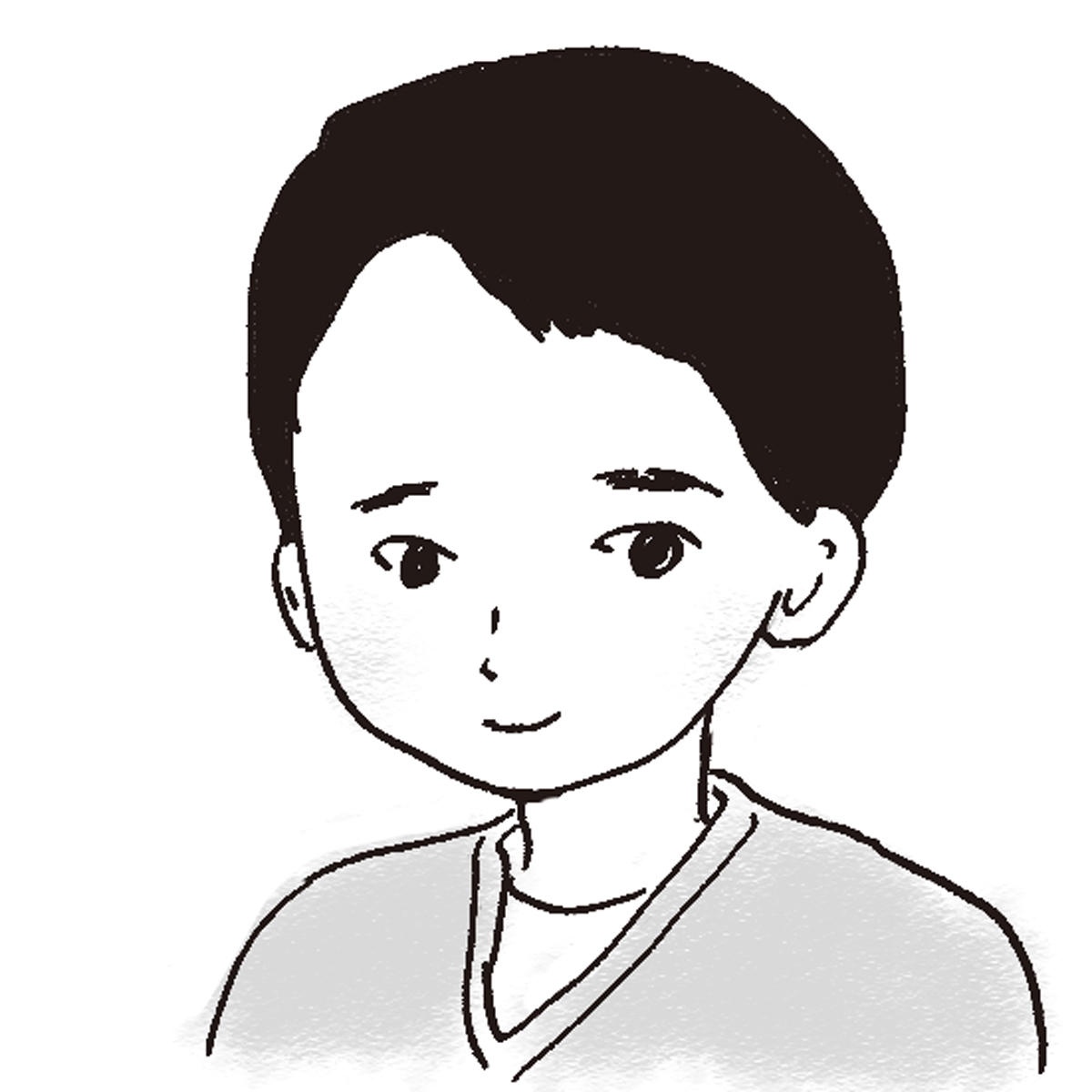
勝俣翔多/1989年生まれ、日刊現代校閲部所属
勝俣 私がいる「日刊ゲンダイ」は夕刊紙という性質上、新聞校閲に近い世界ではあるのですが、それでも今回の2巻の内容はとても勉強になりました。さっきの外校さんの話だったり、校閲と揉める編集者の話だったりを通して、いろいろな立場から校閲という仕事の輪郭を描いていますよね。校正校閲の仕事をしているとどうしても自分だけの世界や部署内とか、社内に閉じこもってしまうところを、外からの視点を入れることで吹き抜ける風のような印象を感じました。
こいし うわ、ありがとうございます。勝俣さんは2巻の最後の回で描いた飲み会で、九重さんの知り合いの大雪くんとして出させて頂きました。あの時は、ネタ集めと称した他社の校閲さんとの飲み会を編集さんが開き、私も「そのまま描きませんから安心して何でも話してください」とか言いつつ、結局ほぼそのまま描いちゃったんですけど大丈夫でしたでしょうか?
勝俣 ガッツリ出てるな~と思いました(笑)。
こいし ですよね!(笑)言い訳をすると、佐藤さんも勝俣さんもそうなのですが、実際にお会いしてお話を聞くと、私の中でも新しいキャラクターが生まれたり、こういう話を描きたいという想像が膨らむんですよ。校閲者さんの声が、この漫画の可能性をいろいろな方向に広げてくれるんです。それで、やっぱりあの場のことを描くのが一番良いと思ってしまったんです。申し訳ないです!
勝俣 いえ、前もって内容の確認もさせて頂きましたし、こちらも楽しく拝読しました。ただ一点だけ、『校閲なんていらない』という本をいつか出したいというセリフがありましたが、あれは自分の言葉ではないということだけ、この場を借りてお伝えさせて下さい! むしろ校閲は必要だと思っていますから(笑)。
こいし そうでしたよね。いつも何人かのお話を交ぜてキャラクターを作っているもので、勝俣さんの知り合いの方が読んだら誤解されちゃいますもんね。本当にごめんなさい!
佐藤 でもあれは漫画のキャラとして見ると、そういうタイトルをぶち上げておいて、その本を読んだら実は校閲は必要だってことが書かれているという仕掛けではないかと、私は思いました。
勝俣 そう読み取ってもらえると、確かに良いですね。
こいし そういうことでお願いします(笑)。
編集者がやりがちなこと
佐藤 勝俣さんが仰っていた「校閲と揉める編集者」の回、念校で大量の赤字を入れようとするハタ迷惑な編集者が出てきますよね。
こいし 叶さんというキャラですね。
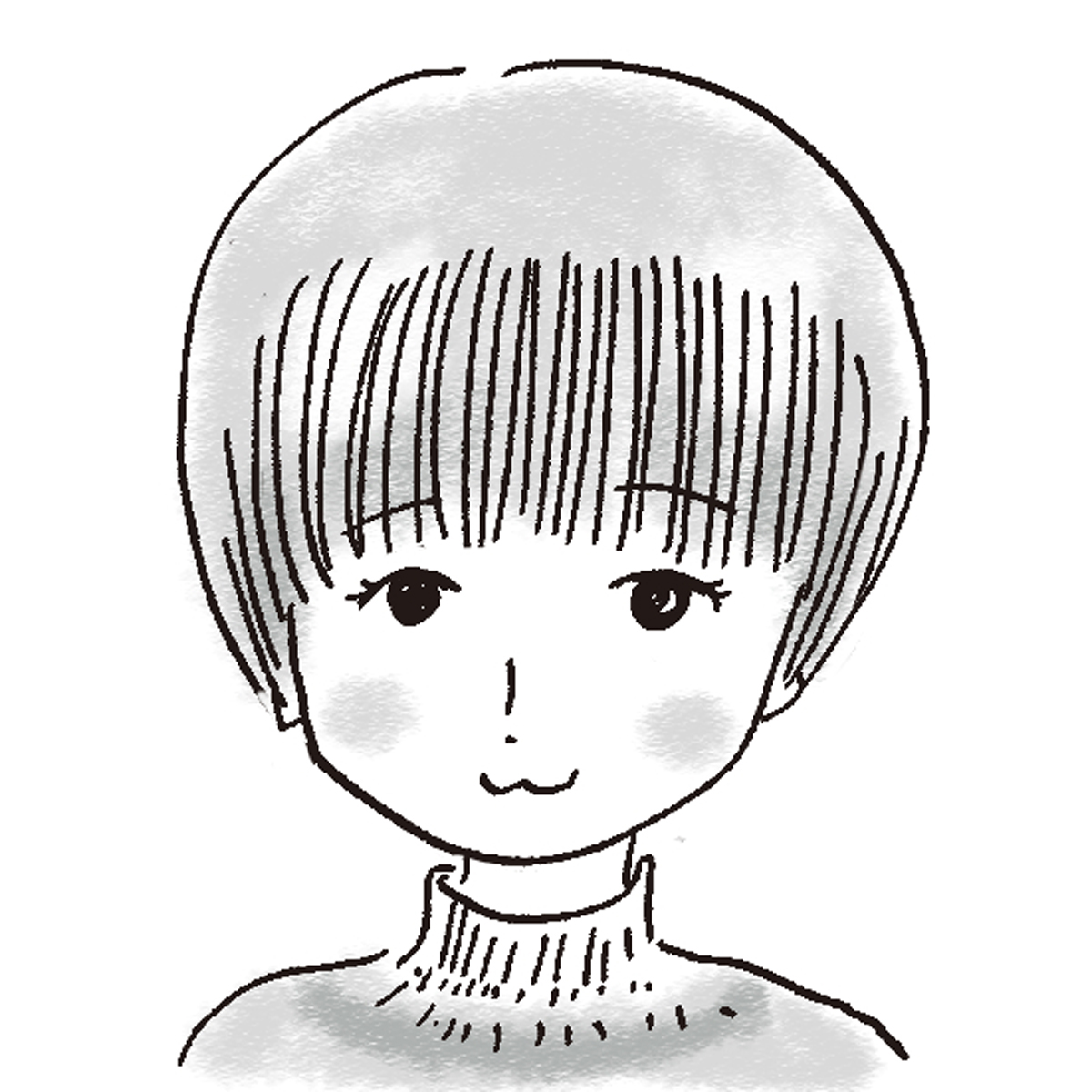
佐藤瞳/1988年生まれ、フリー校閲者
佐藤 新潮社さんに限らず、割と発生しがちな事案だなと思って読みました。初校や再校ならまだしも、赤字や新規原稿を加えるタイミングが遅ければ遅いほど、ちゃんと読んで、調べて、疑問出しをしたり著者に確認をしたりする日数が厳しくなってくる。それをわかっていない編集の方って意外と多いんですよ。
勝俣 漫画でも触れてもらっていますが、夕刊紙は朝9時にその日出す生ネタを責了して印刷に回すので、朝2時間くらいで校閲しなければいけなくて、バタバタしているんです。なのに、朝出社すると、前日に既に何人か読んで校閲が済んでいたはずの記事のゲラが記者の赤字で真っ赤になっていて、それが校閲部員の机にただ置かれていたことがありました。
佐藤 著者さんや記者さんからすると、校了前は“直せる最後のチャンス”だという捉え方になるんでしょうね。
こいし 私も原稿を描く側の立場からすると、その気持ちがわからなくもないのですが、でも何の説明もなくそれをしちゃうのは良くないですよね。
佐藤 紙面や本を作る過程でいろんな事情が発生することはもちろん理解していますので、その都度コミュニケーションを取っていただければこちらとしては問題ありません。でも、それによって校閲や印刷のプロセスが圧迫されて追い詰められることをわかってくれていないまま、無茶な要求だけが来てしまうと、仕事はしっかりしますけども、気持ち的には処理に困ることが多いです。だから、この2巻は全ての編集者に発送したいくらいみなさんに読んでほしいですね。
こいし フセンを貼って、ご一読くださいと……(笑)。
佐藤 そうは言いつつ、この漫画では編集さん側にもちゃんと寄り添っていますよね。“校閲困らせあるある”をしつつ、良い本を作りたい一心で、という編集者の立場や心境も描かれていて、こいしさんは本当に優しいなって思います。
こいし 新潮社さんは校閲と編集が割と対等に近い関係にあるとよく聞くんですよ。他社さんでは編集のほうが強い意見を言えるとか、フリー校閲者との関係はまた違うとか、仕事する者同士お互いに頼るところもあれば、ストレスを感じるところもあると思うんです。その全部を描けるわけではないけども、なるべく一面的な描き方はしたくなくて。これまでいろいろな編集者と仕事をしてきましたが、私だって担当さんと意見がどうしても合わなくて、堪えて漫画を描いたこともありますよ(笑)。でも、良い編集者の方もたくさん知っています。だからそこはフェアに描かなければいけないなと。
社による校閲システムの違い
佐藤 版元ごとの違いということで言えば、私は新潮社さん含め四社からお仕事を頂いていますが、その中でも新潮社さんは社員の方の負担が大きそうだと感じます。
こいし それはどういう意味なんでしょう?
佐藤 一概に比較するのは難しいのですが、例えばB社さんなんかは出入りしている外校が多く、本の付属物や広告、雑誌記事などを分担してどんどん片付けていくシステムが出来上がっているんです。新潮社さんは校閲部員の人数が多く、何でも自分たちでやるという意識が強いせいなのか、社員の人たちが苦労して全部請け負っている印象です。良く言うと一冊に対しての責任感が強いのでしょうが、何というか効率化に踏み切っていないようにも感じます。
こいし 他に新潮社さんならではの特徴というのはありますか?
佐藤 本文のデータを使わせてくれないのは新潮社さんだけです。他社ではルビの初出箇所を探したり、用語を統一したりするのにPDFファイルを使って検索しますが、データを使わないとかなり非効率で大変な作業になるので、結果的に新潮社さんではデータを使える社員校閲者が責任を負ってフォローする形になっているようです。ある意味、外校に期待されている仕事の量とかクオリティが高くないのかもしれません。
こいし 新潮社さん以外の方のお話を聞くにつれ、各社で校閲の制度というか仕組みに特徴があるとわかり、そこに出版社としての本作りに対する姿勢が垣間見えるのがおもしろいなと感じます。どこまで疑問を出すかとか、社によって外校さんに求められることは違うと感じます?
佐藤 そうですね、求められる作業内容やクオリティに濃淡はあると思います。各社、社風というか、体裁までちゃんと見て欲しいところもあれば、そこは緩いところもあり。

高松恭則/1964年生まれ、集英社校閲室部長代理
高松 私どもの会社ですと、校閲室の社員は部長以下9人です。
こいし 集英社さんなのに少ない!
高松 コミックや雑誌は外部に任せる形になっていまして、私どもが目を通しているのは文芸単行本と、学芸単行本の一部です。去年、開高健ノンフィクション賞を受賞した『対馬の海に沈む』などもそうです。
こいし そう考えると、新潮社さんに校閲部員が40人以上いるのは、圧倒的ですね。
高松 そうですね。新潮社は創業者が大日本印刷の校正係だったところから始まっていますので、私からすると眩しい存在なんです。
こいし 集英社の方でもそういう感覚が。
高松 集英社に校閲室ができたのが1997年なので、歴史は浅く、新潮社さんや講談社さんに追いつけ追い越せで、負けたくないという気持ちはあります。
こいし その黎明期から高松さんはいたということですよね。その場合、誰から校閲を教わるのでしょうか?
高松 私は元々新聞社で校閲をしていましたので下地はありました。ただ、新聞記事はある意味パターンがあり、文章としてあまり綺麗なものではないと感じられて仕方なくて……。福永武彦とか立原正秋とかを貪るように読んで、精神の均衡を何とか保っていました。その後集英社に移るのですが、新聞校閲と文芸の校閲は全然違いましたね。100m走のランナーがマラソンに出るような感じで、ペースも掴めなければ勝手も違う。それで、日国(日本国語大辞典)の校正を経験した上司から全て教わりました。夜中の方が静かだし頭も働く、と夕方出社して夜中ずっと仕事するというスタイルの方でした。
こいし 夜会社にいないと教えてもらえない……(笑)。
高松 ですね。……実は、言うべきか悩んだんですけど、先ほど「新潮45」の話が出ましたよね。あの時に新潮社を取り囲む抗議がありましたが、私はその中にいました。
こいし そうなんですか!
高松 子供の時から新潮文庫をずっと好きで読んでいた自分としては、あれは許せないことだったので。夜だったのでサイレントデモ。結構な人が、この会社の前の通り沿いに並んでいて。中に知り合いを見つけて、新潮社の本って昔何読んでた? みたいな話をしたりしました。みんな新潮社が好きなんですよ。
こいし だからこそ、裏切られたという気持ちに。
高松 ただ、その後に出された「新潮」での“差別と想像力”という特集を読んで、私はとても感銘を受けました。今でもその号を持っています。起こってしまったことに対して、同じ会社の雑誌として、言い方は悪いですけど落とし前をつけましたよね。こういうやり方もあるんだなと思いました。考えてみると、新潮社さんを訪れたのはあの日以来です。
時代に合わせた在り方
こいし うわ~、会社に歴史があれば、人にも歴史ありですね。最後にお聞きしたいのですが、最近、校閲者の方が書いたエッセイや、言葉に関する本が増えていますよね。勝俣さんがやっているXの「日刊ゲンダイ 校閲部」のポストもおもしろいし、ためになるんですよね。これからの校閲者の在り方として、裏方から表に出て発信するべきなのでしょうか。
高松 私が集英社に入社した頃は、編集者は黒衣であるべきだと当時の社長が言っていた記憶があります。今は多くの編集者が表に出て、隔世の感ではありますけど、校正校閲の人間が発信するのも時代の流れなのかもしれません。
こいし 21話でも描きましたが、自分が校閲した本の中に名前が載るのはどうなんでしょう?
佐藤 それは嫌です!(笑)その本に間違いや不備が見つかった時の矛先として存在しているという側面もありますから、「この本の校閲者のミスだ」と思われるのは仕方ないし、当然のことでもあります。ただ、そこで個人名を見て「校閲者の佐藤ってやつは何をやっとるんだ」と言われるのは苦しい(笑)。
こいし 確かに、リスクの方が大きいですね。
佐藤 著者の方がご厚意で、あとがきに名前を載せたいと仰ることがたまにあるのですが、「お気持ちだけで充分です」とお断りしています。ただ、良かれと思って事後承諾で載せられてしまうパターンもあって、その時は「あっ……わ、わかりました……」というリアクションになります。
勝俣 自分はSNSをやっている立場からしますと、確かに佐藤さんが仰る通り、紙面の誤植やミスの矛先になるというのは覚悟しています。ただ、それ以上に、校閲者の苦悩みたいなことを発信できたら良いなという思いがありまして。うちの紙面は、今どき使っていいのかと思うような言葉が載ることが多いんですね。それこそ、差別用語だと受け取られかねないものとか、普通の新聞だったら許容しないような表現が使われます。だけど、それが紙面になって世の中に出て行く前に、その表現が妥当かどうかを考え、悩んだ人がいるということを知ってもらいたいのもあって、Xで包み隠さず発信しています。
高松 会社の名前を背負っている身としては、大きなメディアが与える世の中への影響を、今一度しっかり認識しなくてはならないと強く思います。言葉や情報が氾濫し、その真偽が問われる時代だからこそ校閲は、その目を通すことで読者にも著者にも編集者にも安心感を与えるような存在であり続けたいですね。
(こいし・ゆうか 漫画家)
(高松恭則 集英社校閲室)
(勝俣翔多 日刊現代校閲部)
(佐藤瞳 フリー校閲者)
最新の対談・鼎談
-
2026年2月号掲載

内田若希『意味ある敗北とは何か─アドラー心理学で読み解くトップアスリートの言葉─』刊行記念
階段を一段上がるのは勝利のときばかりじゃない
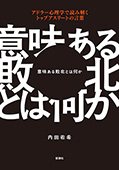
意味ある敗北とは何か―アドラー心理学で読み解くトップアスリートの言葉―
-
2026年1月号掲載

『ひのえうまに生まれて─300年の呪いを解く─』刊行記念鼎談
ひのえうまに生まれて生きる私たち

ひのえうまに生まれて―300年の呪いを解く―
-
2026年1月号掲載

三島由紀夫生誕100年記念対談
私たちの中に生きている三島
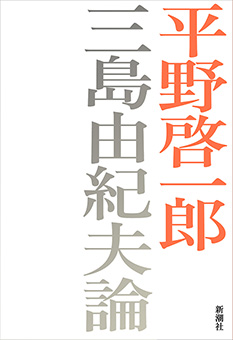
三島由紀夫論
-
2025年12月号掲載

『池上彰が話す前に考えていること』刊行記念対談
池上さんと村上さんが話す前に考えていること
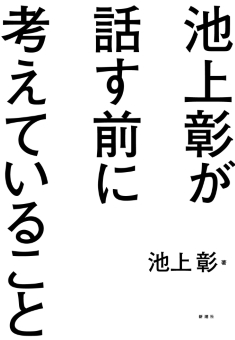
池上彰が話す前に考えていること