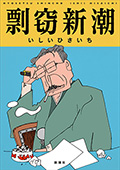書評
2025年3月号掲載
「探偵のいない推理小説」から「謎のない犯罪小説」へ
竹内康浩『謎ときエドガー・アラン・ポー―知られざる未解決殺人事件―』(新潮選書)
対象書籍名:『謎ときエドガー・アラン・ポー―知られざる未解決殺人事件―』
対象著者:竹内康浩
対象書籍ISBN:978-4-10-603923-2
「まえがき」によれば、本書の著者は「エドガー・アラン・ポーの未解決殺人事件を発見し、その謎を解いてしまった気がする」という。この手の「真説」ほど当てにならないものはないが、謎の発見者が「バナナフィッシュにうってつけの日」に埋め込まれた叙述トリックを看破した文学探偵(新潮選書『謎ときサリンジャー―「自殺」したのは誰なのか―』を参照)で、アメリカ探偵作家クラブ賞の評論・評伝部門で初の日本人最終候補になったこともある竹内康浩氏なら話は別である。
百八十年越しの真相が語られるのは、推理小説の始祖ポーが死の五年前に発表した「犯人はお前だ」。「喜劇的推理小説の嚆矢」かつ「推理小説のパロディー」と見なされてきた作品だが、従来の評価に飽き足らない著者は前半の四章を費やしてポーの意図を探り、「マトリョーシカ人形のような入れ子構造」を見いだす。ネタバレになるので詳しく触れられないけれど、巻頭に収録された全文訳の邦題が人口に膾炙した「おまえが犯人だ」の逆になっているのは、物語構造の反転を強調するためだろう。そこからポーの創作原理、すなわち「二項の間に鏡像関係を作り、オリジナルとコピーを入れ替える」という詐欺師めいた手口を察知するくだりはまさに文学探偵の独擅場で、すれっからしの読者でも期待を裏切られることはない。
疑わしい記述として竹内氏は「幻のワインの会話」をめぐる矛盾に注目、これを語り手の捏造と断じている。興味深いのは河合祥一郎氏による2022年の新訳「おまえが犯人だ」(角川文庫『ポー傑作選2 怪奇ミステリー編 モルグ街の殺人』所収)でも、同じ会話が問題視されていることだろう。河合氏は会話の状況から「探偵兼語り手である人物の正体」を推理して、翻訳の文体に反映させたという。竹内説が物語の構造分析を重視するのに対して、河合訳は語り手のキャラクターを前面に押し出したといってもいい。その結果、前者が拾い上げた矛盾や齟齬は、後者では慇懃無礼な執事キャラの語り口に回収され、ユーモア探偵小説としての効果を強調する方向に作用する。ファルス(喜劇)作家としてのポーを念頭においた訳で、同じ作品の解釈でもこれだけ印象が異なるのは珍しい。
だがむしろ筋金入りの推理小説マニアほど、精緻な読みに裏打ちされた竹内説の論理のアクロバットに魅了されるのではないか。先に記した「マトリョーシカ人形のような入れ子構造」は「読者への挑戦」で知られるアメリカ探偵小説の巨匠エラリー・クイーンの作風に先んじているし、本書中にも言及のある平石貴樹氏の論文「『アッシャー家の崩壊』を犯罪小説として読む」(1985年の本格推理長編『だれもがポオを愛していた』所収)で示された操りの図式を受け継いで、さらに深化させているからだ。
後半の四章は基本原理の応用編で「のこぎり山奇談」や「ウィリアム・ウィルソン」、あるいは「黒猫」等の読解を通して鏡像(双子)関係とオリジナル/コピーの反転図式が多角的に跡づけられていく。「のこぎり山」論に当時の最新発明だった銀板写真に関する注釈が挿まれるのは、「複製技術時代の芸術」(W・ベンヤミン)が背負わされた近代の条件と無関係ではないだろう。さらに竹内氏によれば、謎解きを読者に委ねるというアイデアが不発に終わり、失望したポーが「探偵のいない推理小説」から「謎のない犯罪小説」への退行を余儀なくされた可能性もあるという。犯罪の化身として解読不可能な本に擬される「群集の人」の老人と、完全犯罪をなしとげながら理不尽な自白衝動に取り憑かれて破滅する「天邪鬼」の語り手が、「犯人はお前だ」の入れ子構造を腑分けした分身同士だとすると、推理小説史の特異点である「倒叙形式」のルーツもそこらへんの間に潜んでいるのかもしれない。
最後に蛇足ながら、本書を通読して気になった点をひとつ。著者は第六~七章で「モルグ街の殺人」「盗まれた手紙」を取り上げ、名探偵デュパンの「分析=鏡像」とアナロジー(類推)について考察しながら、なぜかシリーズ第二作「マリー・ロジェの謎」を黙殺している。だが本書の趣旨に従うなら、現実の未解決事件に挑んだ「マリー・ロジェ」こそ、詐欺師めいたポーの手口が最も顕在化した作品ではないか。というのも、実在のメアリー・ロジャーズ事件を小説化するに当たって、ポーはニューヨークの事件(実話)よりパリの事件(創作)が先に発生したと主張して、オリジナルとコピーの時系列を強引に入れ替えているからである。これまでデュパンをシリーズ化するための苦肉の策(もしくは推理の不備へのエクスキューズ)と見なされてきた不自然な形式が、実はポーの創作原理の根幹に関わっているとしたら……。
(のりづき・りんたろう 推理作家)