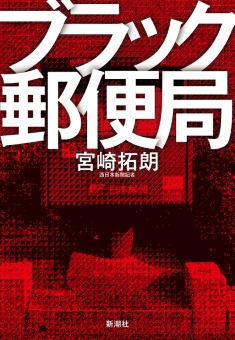書評
2025年3月号掲載
「1000人超の勇気」を基にした調査報道
宮崎拓朗『ブラック郵便局』
対象書籍名:『ブラック郵便局』
対象著者:宮崎拓朗
対象書籍ISBN:978-4-10-356151-4
いったい、これはどういうことか。日本社会を下支えし、地域社会と深く結びついた「郵便局」はどうなってしまったのか。本書を手にした人は、ページをめくりながら悄然とするに違いない。「悲惨」「パワハラ」といった語句では言い尽くせない、おそろしいばかりの現実をこれでもか、これでもかと見せつけられるからだ。
例えば――。
関西地区で渉外を担当する男性社員は「1日5件のアポ入れ」を強いられていた。それができないと、部屋に閉じ込められ、朝から晩まで電話かけを続けなければならない。多い日は1日に50件。「お伝えしたいことがあります」「相続税対策のご提案があります」と口八丁手八丁で相手に迫る。まるで振り込め詐欺のアジトのようでしたと自嘲気味に語るこの男性も、客を騙して保険に加入させていた。
九州の郵便局では、保険営業の成績が振るわないとして、窓口営業部の課長代理だった40代の男性が上司の部長から連日、激しく責められていた。2018年のことである。「なぜ遅れているのか」「ゼロは許さん」「できなかったらどうするんだ」と大声で“指導”される。そして、冬が近づくころ、男性は部長から「今月実績がなかったらどうするのか。覚悟を聞かせろ」と迫られた。
男性は「できなかったら命を絶ちます」と口にし、3日後、職場での出来事を記した遺書を残して自ら死を選んだ。この男性は、ノルマに追われるあまり、息子名義で不必要ながん保険契約を結んでいたことも後に判明。契約書の「お客さま控え」には、部長に脅されて契約したものだから不要ならいつでも解約していいと書き残していたことも明るみに出た。
こうした人物が本書には次々と登場する。組織に追い詰められた挙げ句、自らの資金で販売ノルマを達成する「自爆営業」を繰り返したり、不正に手を染めたり。著者・宮崎拓朗氏は西日本新聞(福岡)で働くジャーナリストだ。事実に忠実な新聞記者らしく、余分な形容詞のない文章は切れ味鋭い。物語の展開も早い。そのためか、日本郵便という株式会社の残酷さ、そこで働く男性たちの怯えと諦めが息もつかせぬスピードで迫ってくる。
救いのない組織の実態を前にして、唯一、希望を感じられるものがあるとしたら、それはこの問題の取材プロセスそのものかもしれない。
取材に6年以上。取材した郵便局関係者は1000人以上になるという。彼らは皆、組織の歪みを正したいと願う「内部告発者」だった。見つかれば、組織の内部で「裏切り者」呼ばわりされ、さらに追い詰められる。そんなリスクを抱えながら、名もなき社員たちは内部告発とそれに基づく報道に一縷の望みを託し、実態を伝え続けたのだ。
当局による「発表」を端緒とせず、「公式見解」に頼らず、報道機関やジャーナリストが自らの問題意識に基づき、かつ自らの責任において報道することを「調査報道」と呼ぶ。調査報道がなければ明らかにならなかった事実は数多い。調査報道の結果、法令が改正されたり、制度が新設されたりすることもある。少し古い話だが、米ワシントン・ポスト紙が1972年に手掛けたウォーターゲート事件報道で、時のニクソン大統領が失脚に追い込まれたケースは、調査報道の破壊力を示した実例としてメディア史に燦然と輝いている。
ウォーターゲート事件には、記者たちが「ディープ・スロート」と呼んだ内部告発者が米国政府内にいたことがわかっている。それに比して言えば、郵便局の闇を追ったこの取材には1000人以上の「ディープ・スロート」がいたと言えよう。彼らの動機はさまざまだった。宮崎氏によると、顧客に寄り添った郵便局を取り戻すためであり、苦しむ同僚を助けるためであり、亡くなった家族の名誉を守るためだったという。
『ブラック郵便局』は近年で最も優れた調査報道の一つだが、それは組織内での身バレのリスクを抱えつつも、勇気を振り絞った1000人以上の力が成し遂げたものでもある。
同時に、今回のケースは調査報道の新たな可能性も示した。新聞社のホームページに記事が掲載されたことで、郵便局不正の問題は西日本新聞の配達エリアを超えて全国に広がった。その報道を見た郵便局の関係者は、九州から遠く離れた場所であっても勇気をもらい、新たな内部告発者となった。記者もメールやSNSを駆使しながら、広く、深く、情報を収集。九州以外へも足を運び、「1000人超の勇気」に応えた。
本書が描く日本郵便の実態は息苦しく、読み進めることがつらくなる。日本郵便と似たような企業・組織は、他にも山のようにあるだろう。そうであっても、内部告発を行う勇気とそれをきちんと受け止めてくれる調査報道があれば、社会は変えることができるかもしれない。本書は、そんな希望の在り処も教えてくれる。
(たかだ・まさゆき 東京都市大学メディア情報学部教授)