書評
2025年3月号掲載
私の好きな新潮文庫
質感、味、匂いを読む
対象書籍名:『カゲロボ』/『どんぐり姉妹』/『すいかの匂い』
対象著者:木皿 泉/よしもとばなな/江國香織
対象書籍ISBN:978-4-10-103961-9/978-4-10-135942-7/978-4-10-133916-0
母が小説家ということもあり、本に囲まれたリビングで日々を過ごしていた。喧嘩をしている時も、ラジオ体操をする朝も、いつも本の背表紙が目に入ってくる。好きなタイトルは声に出してみたりした。いい言葉は声に出すと気持ちがいい。小説も同様に時々声に出して読む。そういった姿を人に見られまいと周囲を警戒していると、妙な動きになりロボットのようだな、とよく思う。そして街に出ると、そんな動きをしている人は稀にいる。
世の中に人間のふりをしたロボットが紛れ込んでいる気がしているのは日頃からだが、この本を読んでさらにその気持ちが強まった。『カゲロボ』だ。作者の木皿泉さんといえば、最も好きなドラマ「すいか」から夢中になった夫婦脚本家である。本作も、見逃してしまいそうな生活の愛おしさがたまらないと思いながらも、背けたくなるような世の中の問題に、いつの間にか目を向けることになる。「かお」という章のふたりの少女のことを想うと涙がでた。生きていることに本物も偽物もないのに、自分が正しいと押し付けるような言葉ひとつで、誰かが死ぬ。
ここぞというときにつくるエビフライの尻尾のこと、お土産の稲荷寿司を待つ時間、くるくる靴下や空豆の黒いスジのこと。些細なことに興味を持ち生活を愛せる人間は、ユニークな生き物で安心するし、不安にもなる。人は何かを取り繕っていると、人間らしくしようとしてしまうのはなぜだろう。気がついてないだけで、人間はロボットになっているのかもしれない。

30歳になったばかりの頃、「このまま私はひとりで生きていくしかないんだ」とファーストフード店で号泣し、友人を困らせていた。彼氏と別れたばかりのヤバい精神状態でハンバーガーなんて食べるもんじゃない。そんな私の前で友人は、「大丈夫、私がいる」と言い、ポテトを食べた。今欲しい、ちょうどいい言葉と行動であった。

『どんぐり姉妹』を読んでいる時、そんな感覚が寄り添ってくれる。そうそう、こんなふたりでいられるならば、別に結婚なんてどうでもいいと思わせてくれた救いの本だ。「こだわってなければ、やがて傷はふさがり、幸せはどこからでもにゅるにゅる出てくる」。
なんてちょうどよく染み入る一節なんだろう。ときおり出てくる料理がおいしそうなのもたまらない。深夜のサムゲタンも、冷たい空気の中で飲むあたたかいお茶の風味も、味わうように読んだ。腹ごしらえをして、時々やさしくない現実に立ち向かえばよし。
小学生の頃、祖母の家に夏休み中ひとりで預けられたことがあった。なんて暇なんだ。好きだと言ったら大量に出された肉や刺身。普段は少しずつしか食べられないご馳走が山盛りだった。そこで気がついたが、ご馳走は少量がベストだ。少ないから、あんなにおいしかったのだ。それから、そうめんには決まってミニトマトがのっていた。ほんとうは苦手だと言い出せなかったミニトマトを軽く噛み、汁が出る前に丸呑みにした。喉を通り抜けていくぬぺっとした皮の感触。『すいかの匂い』は、そんな少女時代に感じたゾッとした感覚を、じわじわと思い出させてくれた。知らないのに知っている、怪談のような夏の日常。無邪気なお葬式遊びや、口の中で鬼灯の実を弄ぶ音。他人の家の匂い、耳鼻科の銀色の器具の冷たさも、自分の記憶とごちゃ混ぜになる。どうかしてしまうほど生々しく描写されているからだろう。漢字やひらがなを巧みに混ぜて表現しているからか、独特のリズムで読み進めてしまう。言葉で作り出す芸術に震えた1冊。
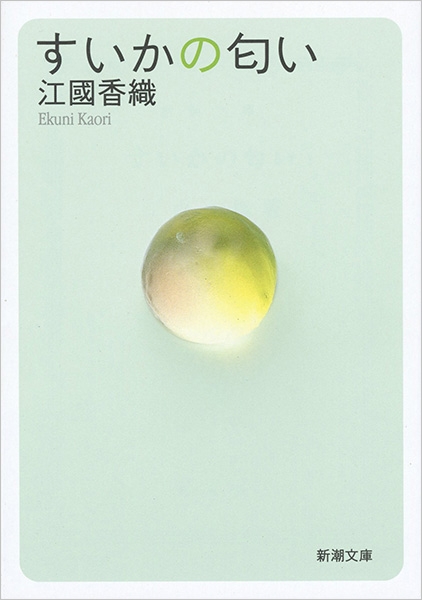
質感、味、匂いを感じるこの3冊は、これからも時折読みかえして生きようと思う。そしていつか映像にできる日が来たらしあわせだ。
(ひがし・かほり 映画監督/グラフィックデザイナー)








