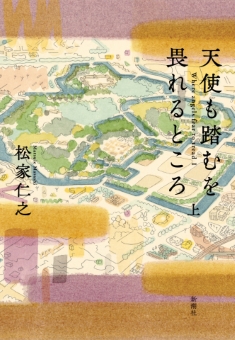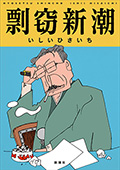書評
2025年4月号掲載
松家仁之『天使も踏むを畏れるところ(上・下)』刊行記念特集
小説のなかに建った新宮殿
対象書籍名:『天使も踏むを畏れるところ(上・下)』
対象著者:松家仁之
対象書籍ISBN:978-4-10-332814-8/978-4-10-332815-5
六十年ほど前、皇居内で着工した七棟からなる新宮殿。その造営をめぐる長大なこの群像劇の、どこまでを実際の出来事ととらえるか。判断は難しい。それだけに面白く、奥深い。
昭和天皇と皇后、ご成婚まもない皇太子夫妻、吉田茂元首相らは実名で登場し、竣工までの日付も史実そのまま。何より、作中で子細に意図を解説されてゆく宮殿が記述通りの平らかな姿で、千代田の濠と杜に囲まれて今もある。だが、主要な登場人物は実名を外され、実録小説と呼ぶのが憚られるのは、そこが虚構と断ることによってのみ、実相に迫ることが可能になる聖域だからだ。エピグラフには十八世紀英国の詩人A・ポープに拠る表題の意がある。どんな神聖な場所でも愚かな者たちを締め出すことはできない、天使が畏れて踏まないところでも、愚かな者たちは踏みこんでくる……。
愚かな者というなら、それはすべての人間を指すだろうが、本作では明らかに優秀過ぎる人物がいる。宮内庁の造営責任者、牧野脩一は敗戦後、皇室典範改正にかかわり、六千人いた職員を一時は千人以下に縮小するなど、天皇制の生き残りをかけて改革に辣腕を揮ったエリート官僚。神仏への関心は乏しいが、苦学する中で却って芸術への関心を、異様に研ぎ澄ませてきたような人物である。牧野の采配は大筋において正道と認められるものの、思いがけぬ局面で分を踏み外すほどの我欲を滑りこませる。その牧野が新宮殿の基本設計者として大抜擢したのが、日本の伝統様式とモダニズムを高度に融合させる俊英、東京芸大助教授の村井俊輔という最善の選択だったのだから、話は複雑である。そして村井俊輔こそ本作の中心人物であり、皇室の儀式から海外の賓客をもてなす広間まで擁する、二万三千平米もの延床面積を預かる村井の技量に、「国民の象徴」たる新たな天皇制のかたちも託されることになる。
村井と牧野の間に立って宮殿建設の進行を担うのが、天皇皇后の住まいである吹上御所の設計者となる建設技官の杉浦恭彦。ヨーロッパへ視察に出た杉浦は、オスロ王宮やストックホルムの市庁舎や図書館を見るうちに、機能だけなら五十年と持たなくとも、芸術であれば百年、二百年残っていくという、前任の尊敬する建築家の教えを実感する。杉浦が古巣、建設省の同期と交わす会話には、オリンピック前に慌ただしく進む首都の高速道路や東海道新幹線、本州四国連絡橋におよぶ国土開発計画が挙がり、高度成長期1960年代の昂揚した世相も呼びこまれる。
大戦中に焼失した明治宮殿の跡地に、九十億円もの国費を投じて新宮殿を建てる――それが宮内庁のオモテにおける大事業だとすれば、対を成すように天皇家を取り巻くオクと呼ばれる者たちも、次代にかかわる重大事を抱えていた。初の民間出身の皇太子妃は、こちらも最善の選択が叶ってご成婚と相成り、その絶大な人気が宮殿建設の機運を後押ししていた。にも関わらず、当の妃の憔悴は楽観できぬほどだった。旧弊で陰湿な者たちの所業に気を揉みながら、「開かれた皇室」をめざして新聞、雑誌に達意の文章を寄せるのが侍従の西尾であり、冷泉家の流れをくむ彼は父の代から天皇の側近を務める。この西尾も時によっては独断で、聖域まで踏み入る覚悟なくしては成せない立場にあった。
村井、杉浦、西尾、加えて藤沢衣子という園芸家――彼女は村井と皇太子妃、二人を私的に力づける数奇な役割を果たすことになるのだが、この四人の視点が入れ替わりながら、百二十五に上るシークエンスを積み重ねて本作は出来上がっていく。どの場面、どの人物の挙動も先のどこかへの布石、呼び水となっていて、物語が撓むことはない。
京都御所の〈簡素な寝殿造の味わいは、モダニズムにも通じる〉と直観した村井は、鉄筋コンクリートの陸屋根の上に威圧感のない穏やかな勾配の銅板屋根を架ける構想を固め、一般参賀のための広場を優先し、君主が北を背に政務するという古来の「天子南面」は継がない。〈オリジナリティなんていうものは、ないんだよ〉。村井は部下と自分に言い聞かせるように言う。〈百年後にもすばらしいと感じられる建築は、あたらしい顔をしているというより、どこかで見たことのあるものが少しずつ集積して、見事にそこに落ち着いている――そういうものじゃないか〉。
抑制の利いた彼の意匠同様、時折、自然光が差すようにふっと会話や思弁に村井という人物が現われる。人間の五感を通した経験はいつまでも記憶に残る、神は細部に宿るという信念をもって、照明や家具調度にまで神経を払おうとする村井の前に、しかし、いつのまにか予算も権限も掌中にした牧野が立ちはだかる。〈千年の伝統をどう継承してゆくか。一建築家の趣味や趣向に委ねるわけにはいかんのだ〉と。
審美と機能をめぐる専門的、局所的な心理戦が下巻では激しく続く。それは国家、官僚機構と個人の創造性の対立であり、国民の象徴とは、伝統とは何かという、同時代のうちには答えの出ない問いがつねにその奥にある。君主不在となったこの国で、それでもともかく戦後、あらたな施主となった国民を納得させる新宮殿を実現しなければならない。それぞれの人生を賭けた真っ直ぐな光のような志を束ねて、叡智をふり絞らなければならなかった。
昭和半ばを生きる彼らは、誰もが私生活を仕事のわずかな余白に追いやりながら、信じ難いほどの耐性を発揮し続ける。それは明治末生まれの村井らの世代がくぐり抜けてきた、関東大震災から太平洋戦争にかけての過酷さによって養われたものかもしれない。
戦争の記憶は経済の復興につれて薄れ、西尾は銀座のバーで憂さを晴らし、杉浦が黒澤明の映画や洋食を楽しむ和やかなひとときも挟まれる。北軽井沢の山荘でしばし憩う、村井と衣子の密やかな恋物語は、不義にしては爽やかな風のように本編を吹き抜け、住宅と人間の関係を考える上で、また、十三年前のこの作者のデビュー作『火山のふもとで』の前日譚としても、重要な読みどころとなっている。
現在、公式資料には宮殿の基本設計者として吉村順三の名が残る。作中の村井の仕事はこの名建築家と重なる部分が多く、吉村は造営半ばにして任を辞している。巻末の主要参考文献リストから、西尾は入江相政、皇太子夫妻を見守る小山内は小泉信三、村井の友人の画家は東山魁夷と推察されよう。そしてなぜ、この小説が書かれなければならなかったのか。志を残して退いた吉村と関係者の名誉回復が目指されたからではなかったかと、踏みこんでみたくもなるのだが……。
さらに作中で伝えられる昭和天皇の生物学研究への熱意、忘れ得ぬほど秀でた皇太子妃の御製を通じて、皇室で自然科学の研究と和歌がかくも深く営まれてきた、その背景にも思いを馳せた。二千二百枚の大長編を閉じる時、歴史に残る昭和の難事業を、しかと見届けた心地がした。
(おざき・まりこ 文芸評論家)