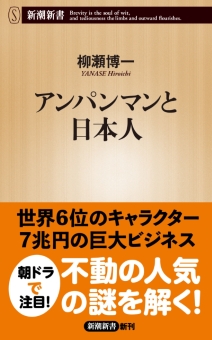書評
2025年4月号掲載
柳瀬博一『アンパンマンと日本人』(新潮新書)刊行記念特集
アンパンマンで語る野心的な「戦後文化論」
対象書籍名:『アンパンマンと日本人』
対象著者:柳瀬博一
対象書籍ISBN:978-4-10-611080-1
「アンパンマン」についての紋切り型の理解はざっと以下のようなものだろう。アンパンマンはお腹が空いている子供たちに、自らの「顔」を与える。決して正義の名の下に悪を撃つことに酔うタイプの、ありふれた幼稚な「ヒーロー」ではなく、あくまで空腹者に自己犠牲を払い手を差し伸べる真の強さと正しさに溢れた本当の「ヒーロー」なのだ、と。これにやなせたかしの戦争体験のエピソードを加えてそこに「戦後民主主義の精神」でも見出せば完璧だ。
嫌味な書き方をしたが、本書の著者柳瀬はこうした紋切り型の理解を「否定」しはしない。それはやなせたかしの人生を振り返れば、自ずと見えてくる背景であり、アンパンマンとは作者の戦争体験から与えられたものとその後に経験した戦後民主主義が輝いていた時代のメンタリティを踏襲したものであることは自明だからだ。
しかし本書がこうした紋切り型の「文化論」に収まらない長い射程をもつのは、そのクリエイションの背景を総合的に探究しているからに他ならない。本書はこうした幼児向けの作品としては異様にイデオロギッシュな姿勢を含め、なぜこのようなある意味奇異(であるにもかかわらず、長く、広く愛されるよう)なキャラクターが生まれたのか、そのメカニズムを問うものに視点をアップデートする一冊なのだ。
おそらく次期の「朝ドラ」の題材となることでよりひろく知られることになるやなせたかしの(今日でいうところの)マルチクリエイター性を、著者柳瀬は当時のメディアの世界の手探りの、しかし爆発的な拡大への否応なき対応の結果として位置付ける。
物語作家として、詩人として、そしてデザイナーとして、縦横無尽に活躍してきたやなせたかしだが、そのアイデンティティはあくまで「漫画家」であった。しかし手塚治虫以降のストーリーマンガに国内市場は席巻され、ひと世代前の一コママンガを得意としていたやなせたかしはテレビや広告デザイン、音楽など周辺の文化産業でその才能を発揮せざるを得なかった。それが彼の「マルチ」な能力を育てたというのが本書の見立てであり、そしてその見立ては取り上げられる伝記的エピソードからも、作品内の表現の分析からも極めて説得力がある。
そして、やなせたかしが結果的に手がけることになった「絵本」のなかで生まれたアンパンマンには、やなせの思想とさまざまな分野の仕事で培われたスキルが当然のように注ぎ込まれた。誕生後のアンパンマンは昭和末期の、消費社会化する日本の幼児たちの心を少しずつ捉えていく。そしてバブル経済の絶頂期にテレビアニメ化されたアンパンマンは、そのブレイクにより今日に至るまで、全国の幼児たちの心を掴み続けている。
ここまで来れば、本書の裏テーマともいうべきものも、そして著者柳瀬のメタ・メッセージも明白だ。本書は「アンパンマン」というキャラクター成立の背景を探る文化論であり、同時に戦後論でもあるのだ。
もはや「日曜劇場」をポルノ的に消費して当時の記憶を上書きしてしまった老人たちくらいしか信じていない「ジャパン・アズ・ナンバーワン」的な物語をある種の「ケア」として「あの頃は良かった」と持ち上げるのも、こうした欺瞞を叩きのめして「そんなものは幻想だ」と批判するのも簡単だ。しかし本当に大事なのは「あの頃」から、今を生きる僕たちが何を持ち帰るかなのではないか? 端的に言えば著者柳瀬はその代表としてアンパンマンとやなせたかしの仕事を取り上げているのではないか。
戦後日本の達成と限界をフェアに吟味した上で、「あの頃」にしか絶対に成立せず、それでいてこの2020年代の「いま」も通用する作品から「戦後」というものの、あまり語られてこなかった側面にスポットを当てているのではないか。それはわかりやすく述べれば拙速さと混沌さが、半ば暴力的に人間の創造性を育んでいた時代の豊かさのようなものだ。その側面を描き出す試みは本書において、アカデミックな視点とジャーナリスティックな語り口を器用に使い分けながら実現されている。ノスタルジックな戦後文化「語り」のなかでハートフルなエピソードが先行してしまいがちな当時のカオティックなメディアの現場を平易に、しかし芯を食った分析を伴って提示する、リーダブルだが、総合的で、そして野心的な仕事……この巧みさと強いメッセージを両立させる著者「柳瀬」博一の手捌きに、本書が伝えるかつての「やなせ」たかしの姿を、多くの読者は重ね合わせざるを得ないだろう。
(うの・つねひろ 批評家)