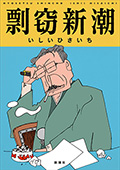書評
2025年4月号掲載
私の好きな新潮文庫
学校司書がおすすめする高校生に人気の三冊
対象書籍名:『世界でいちばん透きとおった物語』/『月まで三キロ』/『財布は踊る』
対象著者:杉井光/伊与原新/原田ひ香
対象書籍ISBN:978-4-10-180262-6/978-4-10-120762-9/978-4-10-103682-3
埼玉県立高校の司書は県立図書館と同採用で、一校につき一人、ほぼ正規の職員として学校に配置されている。高校司書同士の横のつながりも強く、県内の有志で「埼玉県の高校図書館司書が選んだイチオシ本」など高校生の読書推進の活動をしている。選書は司書にとっていちばん大切な仕事で、出版社のブックガイドは重要なツールになっている。
新潮文庫は毎年春に「ワタシの一行教育プロジェクト」や「中学生に読んでほしい30冊」「高校生に読んでほしい50冊」を発表し、学校図書館に冊子を配布している。「高校生に読んでほしい50冊」は本校でも好評で、掲載本といっしょに展示すると、冊子はすぐに無くなってしまう。新潮文庫と学校図書館のかかわりは意外と深いのだ。
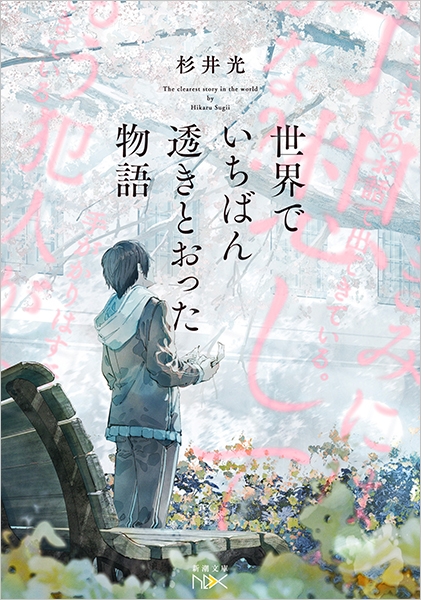
「高校生に読んでほしい50冊2024」の中で、昨年、うちの図書館でよく借りられたのは『世界でいちばん透きとおった物語』だ。なんと、中・高校生がバトラーとして出場するビブリオバトルでもこの本はよく紹介されている。
主人公の藤阪燈真は、校正者の母と大御所ミステリ作家の宮内彰吾との間に生まれた不貞の子だった。宮内に迷惑をかけないようにと慎ましく暮らしていた母子だったが、母がとつぜん交通事故で亡くなり、その二年後に父である宮内彰吾が病気で亡くなったことをきっかけに、燈真の人生が動き始める。宮内の死後すぐに、燈真のもとに宮内の嫡出子である松方朋晃から連絡が来て、宮内が生前書き残していた『世界でいちばん透きとおった物語』というタイトルの小説を探し出したいと伝えられる。その原稿を探すために、燈真は父と関係があった人物を訪ね……。というあらすじなのだが、この本の真骨頂は、「絶対に予測不能な衝撃のラスト。ネタバレ厳禁。紙の本でしか体験できない感動!」という仕掛けがあることだ。中・高校生に人気のこの本をぜひ、読んでみてほしい。
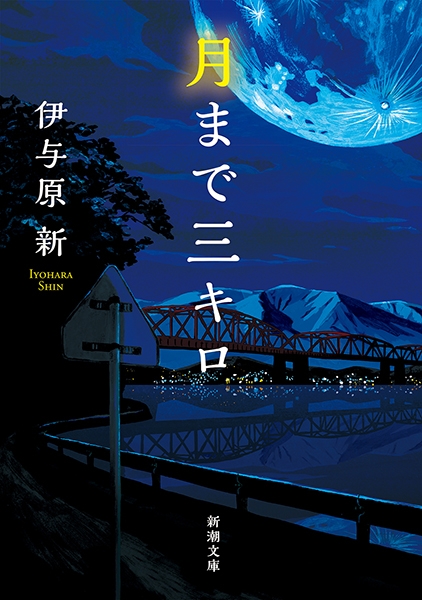
伊与原新さんというと、NHKでドラマ化された、定時制高校を舞台にした『宙わたる教室』、今回、直木賞を受賞した『藍を継ぐ海』が有名だが、新潮文庫の中では『月まで三キロ』をおすすめしたい。6つの短編が収録されているこの本で特におすすめなのが表題になっている「月まで三キロ」と「エイリアンの食堂」。
「月まで三キロ」は死に場所を探すためタクシーに乗った男と、自分も過去に死ぬことを考えた元教師のタクシー運転手とのやりとりがほろりとさせられる作品だ。もう一作、「エイリアンの食堂」は妻を亡くした男が営む食堂に、毎晩同じ時間に定食を食べにくる女性との交流の話。店主の小学生の娘が、研究所に勤める彼女のことを「プレアさん」とよび、宇宙人だと信じていて、店主が彼女に話しかけるところから物語が始まる。思いやり溢れる言葉のやりとりが琴線に触れる。
伊与原新さんは、地球惑星科学が専門で、大学でも教鞭をとっていた研究者。実は、本校が高校生直木賞に参加しているご縁で、高校生向けの講演を拝聴したことがあるのだが、科学的なことをわかりやすく解説される、高校生にぴったりの講演会だった。中・高校生にわかりやすく理系の話をきかせてくれる作家さんはなかなかいない。学校関係者への講演はぜひ、続けてほしい。

最後に紹介するのは、原田ひ香さんの『財布は踊る』。
お金にまつわる人間模様を書かせたら右に出るものはない原田ひ香さんは、女子高校生にも人気の作家だ。「お金について考えるきっかけになるし、勉強になる」と、生徒たちは本を借りている。
平凡な専業主婦のみづほがこの物語の主人公。ルイ・ヴィトンの財布を買うためにコツコツと節約をする毎日を送っている。ところが、夫の圭太の負債を払うためにせっかく手に入れたルイ・ヴィトンの財布をメルカリで手放してしまう。その財布が流れ流れて……。株や投資に精を出す人、奨学金返済に苦しむ契約社員など、いろいろな人の手に財布が渡っていくのだが、最後はいい塩梅で物語が着地し、読者を唸らせる。原田ひ香さんの小説はとても読後感がよく、かつ、お金の知識も学べるので高校生と保護者がいっしょに読めるエンタメ小説だ。新潮社の特設サイトに掲載されている投資家の桐谷広人さんとの対談も、ぜひ、読んでほしい。
子ども達は、身近な大人の話を意外と聞いている。読書離れと言われる高校生も、紹介されれば本を手に取るし、内容がおもしろければしっかり本を読む。学校図書館を本との出会いの場にできるよう、学校司書はアンテナを高くして、本と子どもたちをつなぐ努力をしている。
(きのした・みちこ 社会教育士/学校司書)