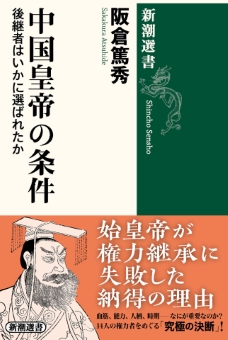書評
2025年5月号掲載
「名君」の素質でもどうしようもない「命運」
阪倉篤秀『中国皇帝の条件─後継者はいかに選ばれたか─』(新潮選書)
対象書籍名:『中国皇帝の条件─後継者はいかに選ばれたか─』
対象著者:阪倉篤秀
対象書籍ISBN:978-4-10-603925-6
「天子」とも称された中国の皇帝は、紀元前221年に、秦王政(始皇帝)が、天下平定の偉業を喧伝し、後世にそれを伝えんとして、新たに造語した帝号である。以後、清宣統帝(在位1908-1911)に至る二千余年間、皇帝のもとでの政治体制が続き、歴史家はその時代を「帝政中国」とも呼んでいる。
本来「帝」とは、「天帝」「上帝」を意味するが、始皇帝が自己を天帝に擬えたことから始まって、神秘性をもつ絶対君主と見なされていた。しかしながら、現実はそうではない。いったい、帝政中国において、何人の皇帝が登場したのか、これは歴代王朝をどう数えるのか、殺害された幼帝、廃位された皇帝を含むかどうかで、あがる数は異なるが、おおよそのところ、二百人余と見てよいだろう。その二百余の皇帝のなかで、「三皇」「五帝」を兼ね備えた名に値する人物が果たして何人いるのか、著者はまず皇帝たるべき素質をあげる。冷酷ともいえる決断力、自己のおかれた立場の冷静な認識、軍事と民政の両面に優れた能力、このような条件を備えた皇帝は、数えるほどしかいないこと、本書を読み進んでいくなかで、我々は実感させられる。
本書では、二十七人の皇帝が登場する。すべて中国史上有名な皇帝であり、高校世界史の教科書にも彼らの治績はとりあげられ解説されている。なかでも、漢武帝、唐太宗、この二人は、歴代皇帝の中で屈指の名君、偉大な皇帝として以後の王朝を通じて高く評価されてきた。
積年の敵であった匈奴をゴビ砂漠の北に駆逐した対外政策、以後二千年にわたって王朝支配の基本となる儒教を官学化した内政、何にもまして「漢」という帝国が以後の王朝の理想となったことが武帝の偉業を物語っている。また太宗李世民の治世は、「貞観の治」と称賛され、太宗は、有能な臣下を適材適所に用い、対外的には周辺異民族を従える「天可汗」の称号をもって、ユーラシアに君臨する大唐帝国を築き上げた。著者があげる皇帝たるべき素質、能力を十二分に備えていたからにほかならない。
しかしながら、名君の誉れ高い彼らにおいても、その能力が及ばず、失敗に終わったことがある。それは後継者問題であり、後継者の選択が帝政中国の歴史を左右したのである。
先の漢武帝においては、晩年の立太子をめぐっての冤罪事件と、後継者の力量不足がもたらす政治の混乱、李世民にあっても、嫡長子を太子に立てたものの、後継の重圧が彼の精神を壊して太子の廃位を招き、最終的に後を継いだ三男(高宗)の気弱な性格が唐王朝の転覆(武則天による武周革命)の原因をつくったのである。もとより、武帝も太宗も熟慮の上の後継者選びであったのだが、それは名君の素質をもってしてもどうしようもない命運であったのか。
「後継者はいかに選ばれたか」を副題にもつ本書は、とりあげた皇帝にかんして、この後継者の選出、後継者となろうとした経緯、即位した後の行動を解説したものであり、皇帝中心史観でもって中国史を概説することを意図したわけではない。
――「あとがき」で「皇帝ははずせない」ということを著者は言を尽くして述べているが、人間がもつ打算と失敗、傲慢の内にある小心、慢心と悲哀、さらには力ではどうしようもない命運、これらは普通の人間だけでなく、特別な存在である皇帝でも同じい。この特別な存在をとりあげることで、むしろその普遍性が明確となる、ということを読者に伝えたかったのではないだろうか。
簡潔、平易な文体で、テンポよくことがらの経緯を説明し、読者を牽きつける。中国史の概要も通史的にそこから得られる。行論において記述が制度、社会、名称の解説へと「脱線」する個所もあるが、それは一種の補助的「コラム」としての役割を担っている。
本書はおそらく読者の期待を裏切ることは無かろう。
この紹介文を閉じるに際して、評者から読者に向けてひとつ質問を出すことをお許しいただきたい。
本書にあがる二十七人の皇帝のなかで、皇帝たる条件、つまり冷静で非情ともいえる決断力と実行力をそなえ、独裁君主たりえることが義務付けられているにもかかわらず、それができないのは君主の怠慢だとする立場を認識し、強靭な精神力をもって、遊楽とは無縁でひたすら皇帝としての「職務」を全うした人物がいた。加えて彼は、斬新ともいえる後継者選びを成し遂げ、その後の王朝を一層隆盛にしたのである。
このことは、本書の行論の中から読み取れるのだが、その皇帝は誰だと思われますか?
(とみや・いたる 京都大学名誉教授)