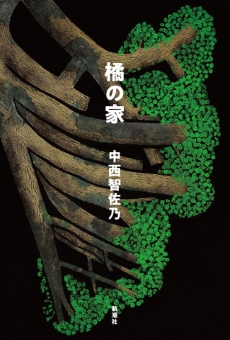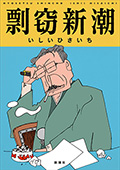書評
2025年7月号掲載
第38回三島由紀夫賞受賞作
時代の依り代として生きる女性
中西智佐乃『橘の家』
対象書籍名:『橘の家』
対象著者:中西智佐乃
対象書籍ISBN:978-4-10-355112-6
中西さんの名前を文芸誌で見るたび、頭をよぎる過去がある。2019年の3月に、私は純文学系新人賞の最終候補に残った。候補作五作の並びに「中西智佐乃」という名前があった。その回、二人の受賞者が出たが、私も中西さんもそうでない側だった。
それから半年後。本屋で文芸誌「新潮」の11月号を手に取ると、表紙には、新潮新人賞発表 中西智佐乃「尾を喰う蛇」とあった。名前に見覚えがあって、すぐにあの時に一緒に落選した人だと思い当たった。中西さんは半年前とは違う小説で最終候補に選ばれ、選考会で選考委員の支持を得て単独受賞されていた。私もその回に自分の新しい小説を投稿していたが、早々に落選していた。あぁ、中西さんはデビューされるのだな。となんだか知り合いが受賞した心地がして嬉しかった。
デビューしたとて死屍累々のこの業界にあって、中西さんはその後も「祈りの痕」「狭間の者たちへ」「長くなった夜を、」とたゆまず発表されている。書き続けるだけでも大変なことなのに、たとえば「狭間の者たちへ」では明らかに挑戦的な視点から書かれており、そういった姿勢に同世代の作家として大きな刺激を受けている。
五作目となる本作「橘の家」は今年4月に三島由紀夫賞の候補に選ばれた。候補となったその一か月後、私は自宅で「三島由紀夫賞・山本周五郎賞」のライブ配信をにらんでいた。六時半ころに、〈第三十八回三島由紀夫賞 中西智佐乃 「橘の家」〉という紙がかけられた。その瞬間、六年前の本屋で手に取った「新潮」の表紙にあった「新潮新人賞 中西智佐乃」という記憶の文字と重なった気がして、一人感慨にふけってしまった。
本作は橘の樹が立つ家にすむ守口家の物語だ。娘・恵実は幼児のときにある事故にあって以来、子孫繁栄の力を持つ橘の霊媒的な役割を担うこととなる。
懐妊を望むのは動物的には自然だが、本能だけで生きる存在ではない人間にとって、その意味や意義、時には価値も時代によって異なる。ただ、いつの時代にも普遍的な重みがある(今までのところは)。本作はある時代の人間社会における子孫繁栄の、業の側を照らしだしている。複数の視点から描かれており、妊娠における男女の不均衡さなどが炙りだされる。主な視点である恵実は、物心おぼつかない幼児の頃から生涯に渡って懐妊に向き合い続けることになり、その半生は過酷だ。
霊媒者本人あるいは周囲の者が、こういった特殊な状況に対抗できうるだけの宗教観や霊性を持たない場合、その特異な能力にすがってくる人物たち(ここでいうなら妊娠したい女性)を一方的に支配してカルトに至る道と、一方的にすがられ搾取される道を辿りがちで、本作ではおよそ後者の道を進むことになる。
橘が持つ不思議な力が恵実の身体を通っては、橘の家を訪れる女性の多くが懐妊を叶えられ、また、その有用さにあざとく気づく宮根のような者が富んでいく。恵実は霊媒であるがゆえ、橘の力も通り過ぎていくばかりで、彼女には何の恩恵も与えられない。懐妊の恩恵は他者で、不懐妊の責任は自分。あるいは子孫繁栄の喜びは向こう側で、その業は自分側。という不均衡な構造となる。この物語の中に出てくる女性のなかで、恵実はもっとも受容的な生き方を強いられ、社会に(男性だけではなく女性からも)消費され続ける。
霊媒として数十年過ごすなかで、恵実は霊性を得たり劇的に哲学性を深めたりすることがなく、そういった方向に導く人物も最後まで登場しない。恵実はあくまでも媒介者であり続ける。それによってある時代の、無私的な受容を無条件に求められ続けた女性たちの苦しみや不遇さ、あるいは女性性そのものが十全に表現されている。救いのないところが、まさに当時の女性性そのものだ。
最終盤に新たな展開がある。それに反発するのは女性ではなく、女性を今まで搾取して抑圧してきた者たちだろう。生殖を巡る意識の変化が起こるたびに今後も橘の樹は生え替わり、代行者として新たな能力と負担を女性に与えるのだろうか。
最後まで引きこまれて読み終わった。この高強度な物語を書くにあたって、それに耐えうる筆力と、どこにも依らない忍耐力にくらくらした。同時にその労と作為性を感じさせないところに、作者が物語に委ねていることが伝わってきて、同じ書き手として惚れ惚れしてしまう。作者と小説の関係性は技術とは別の問題で、結局のところ本人の性質による。私はこういった書き方が好きだ。瑕疵ひとつないこの小説がどのようにして書かれたのかと思うと、興味と感嘆の吐息がこみあげてくる。
(あさひな・あき 作家)