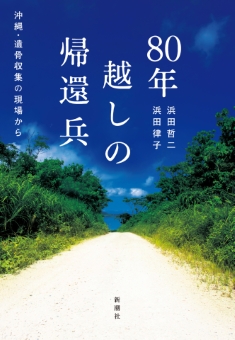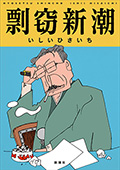書評
2025年7月号掲載
フィクションでは書けない驚きと深み
浜田哲二、浜田律子『80年越しの帰還兵─沖縄・遺骨収集の現場から─』
対象書籍名:『80年越しの帰還兵─沖縄・遺骨収集の現場から─』
対象著者:浜田哲二/浜田律子
対象書籍ISBN:978-4-10-355552-0
沖縄本島南部の壕内の一角。ツルハシで土を起こし、熊手でかき、細かくなった土砂を確認する。石、サンゴの破片、木片、虫の蛹や卵……。そんな中に時々出てくるのが遺骨と遺留品だ。
やっていくうちに違いや特徴がわかってくる。遺骨は「サンゴ片や石よりも柔らかくて軽く、腐った木片よりも硬い」。壕内ではつらい事実も目にする。手榴弾で自決をした兵士の遺骨だ。
「ひとつは頭部や胸部、腹部に大きな損傷を受けていることだ。頭蓋骨や全身骨がすべて吹き飛んでいる例は見たことがないが、この日午前中に発掘した遺骨の一部を見せてもらうと、下顎が無く、肋骨がバラバラに飛び散っていた」
そんな遺骨を探す活動をしてきたのが本書の著者夫妻だ。ただ、通常の遺骨収集とも少し違う。彼らは、出てきた遺留品をもとに身元を特定し、その遺骨や遺留品を現在の遺族に届けるという活動まで行っている。本書はそんな活動を綴ったノンフィクションである。その展開は遺骨収集の苦労話で終わらず、意外な驚きに満ちている。
著者夫妻は、夫の哲二が元朝日新聞のカメラマン、妻の律子が元読売新聞の記者で、2000年代初頭から沖縄本島中南部で遺骨収集の活動に勤しんできた。2010年に哲二が早期退職してからは毎年2ヶ月間、現地で活動してきたという。
遺骨収集のきっかけは、沖縄戦を視覚的に紹介したいと沖縄の本土復帰30年を前に遺骨収集の達人、国吉勇に声をかけたのが始まりだ。国吉を通じて北海道斜里町から遺骨収集に通って来ている高齢夫妻に出会い、浜田夫妻も遺骨収集に進んでいった。
そのため、本書でも最初はそんな遺骨収集の達人の話から進んでいくが、これも“ふつうのいい話”には落ち着かない。真面目に長年掘り出してきたはずなのに、そんな達人が収集遺骨をめぐって金儲けを企む人物に唆されてしまうような展開もある。
だが、なにより読みどころとなるのは、夫妻が遺留品を元に身元を調べ、遺族を探していく行程だ。
国吉から譲り受けたカメラを見て、夫の哲二は、日本人記者のカメラではないかと見当をつけ、その持ち主を探していく。カメラを調べ、殉職した記者を調べ、前職の関係者にもあたっていく。
「紛争地の取材を何度も経験した私にとって、この14人の殉職記者たちは戦場で仕事をしていた大先輩である。何とかしたい、してあげたい」――そう溢れる思いも記している。
妻の律子が傾注した捜索は、本書でももっとも胸を打たれるストーリーだ。米軍上陸前の1944年夏、現地の男児が鎌で顎をざっくり切る大怪我を負った。手当てを世話してくれた兵長が日本軍にいた。男児の母親は生前、男児を助けてくれた兵長の肖像写真を後生大事にもっていた。その兵長が誰だったのか、高齢になったかつての男児から夫妻は託され、捜索に乗り出す。兵長が北海道出身とわかり、夫妻は現地に向かう。すると、そこから人のつながりも予想もつかない方向に展開していく。この捜索の過程には、その兵長とつながる女性の存在があった。律子はそこに心を動かされていた。
「わたしの心の中には、まだ大きな引っ掛かりがあった。(中略)今回は、自身が女性としての感傷に揺さぶられているのである」
古い地縁、出兵前に祈願に訪れた神社仏閣、さまざまなルートを通じて関わった人のつながりを手繰り寄せていく。そして、その旅路の先に夫妻は知られざる事実と思いに触れる。そこにはフィクションでは書けない驚きと深みがある。
著者夫妻は1年ほど前、『ずっと、ずっと帰りを待っていました―「沖縄戦」指揮官と遺族の往復書簡―』という作品を書いている。沖縄戦で生き残った指揮官が戦後、部下の遺族と手紙をやりとりした。その手紙を託された夫妻は、兵の遺族を探し、手紙を届ける活動をしていた。前作にも本作にも共通しているのは、いまの人にあの戦争でなくなった人の証、そして思いを届けるということだ。その意味で前作と本作は前編・後編のようなつくりでもある。
両作を読み通して思うのは、人の思いをつなぐことの重さとあたたかさだ。遺骨を掘り出すことも身元を特定することも大事な仕事だ。だが、そこからさらに一歩進め、いまの遺族に受け渡す。その行いの中に心を強く揺さぶる何かがある。
今年は戦後80年。さまざまな戦争報道があるだろう。だが、時を超えて心に伝わるものとは何か。それはどういうときに起きるのか。そんな大事なことを本書は伝えようとしているように思う。
(もり・けん ジャーナリスト)