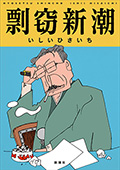書評
2025年8月号掲載
伊与原 新『翠雨の人』刊行記念特集
未来を変えた女性科学者
対象書籍名:『翠雨の人』
対象著者:伊与原 新
対象書籍ISBN:978-4-10-336215-9
猿橋勝子。
1920年、東京生まれ。中央気象台研究部(現・気象庁気象研究所)で研究に勤しんだ女性科学者である。1954年、アメリカの水爆実験で日本のマグロ漁船・第五福竜丸が被ばくした一件での、いわゆる「死の灰」による海洋・雨水汚染の研究に携わる。その研究結果は国際的に大きな評価を得て、のちの部分的核実験禁止条約に繫がった。
日本では科学の門戸が女性にはほぼ閉ざされていた時代の、女性科学者の草分け的存在であり、女性で初めて日本学術会議の会員になった人物である。複数の女性科学者の会の設立、女性科学者を表彰する「猿橋賞」の創設など、科学の世界での女性の地位向上に大きく寄与した。
ざっくばらんに言えば、すごい人なのだ。たとえば2018年3月22日(勝子の誕生日)には、地球温暖化研究のさきがけでもあるとして彼女の似顔絵がGoogleのロゴに採用されたほどである。にもかかわらず、その功績に対して一般にはあまり名前は知られていない印象が強い。
その勝子の生涯を描いた小説だ。しかも理系知識と人の営みを融合させた小説で名を馳せる伊与原新の直木賞受賞後第一作であり、そのうえ初の歴史小説だというんだから、期待せずにはいられないじゃないか!
物語は勝子が亡くなった後の一場面を描いた序章のあと、勝子が十六歳の女学生だった昭和初期に飛ぶ。夢は医者になることだったが、高等女学校を卒業して会社勤めをする。だが医者への夢を断ち切れず、東京女子医学専門学校を受験。だが、あるきっかけでその年開校予定の帝国女子理学専門学校の一期生として物理学を学ぶことになる。
――そこから勝子がどのような環境でどのような研究をし、それがどう実を結んだかが綴られるのだがこれが実に興味深い。朝ドラになりそうな人生だ。だがひとつ、驚いたことがある。この時代の、この手の女性の立身伝にはつきものの要素が極めて薄いのである。
その要素とは、女性差別と戦争だ。女性が結婚もせず科学者として身を立てることは障害が多かったはずだし、戦争の辛苦が皆無だったはずもない。もちろんどちらも作中には登場する。だがそれが御涙頂戴の苦労譚にはなっていないのである。
戦争の辛苦は、むしろ戦後に描かれる。広島で被爆した友人の存在と第五福竜丸だ。世界で唯一の被爆国である日本の科学者として、雨や海水に含まれる放射性物質の検出とその動きを研究し国際社会に問う。アメリカの研究所との検査結果に乖離があり、どちらが正しいかのアメリカでの相互検定では露骨な差別に遭うが、このときも勝子がとったのはただ真摯に数字を求めるという姿勢だった。
この描き方こそ、伊与原新だ。その人物のわかりやすい葛藤を押し出してドラマを演出するのではなく、何のために何をしたかという客観的事実に焦点が絞られる。なのにそこにドラマが、猿橋勝子という人物の内面が、浮かび上がるのである。
研究から離れた彼女の内面が描かれるのは、終盤、子どもを持たない自分は誰に何が残せるだろうと考える場面だ。だがその答えはすぐにわかる。血を分けた子どもこそいなくても、彼女は多くの女性科学者という子どもたちを生み出した。また彼女が生み出した海水の炭酸物質量の変化を示す計算表「サルハシ・テーブル」は、コンピュータが普及するまで三十年にわたって世界の海洋学者に使われ続けた。彼女をそこに至らせたものは何だったのか、それが本書から沁みるように伝わってくる。
多くの人に読んでほしい小説だ。科学への真摯な探究心が社会を変え、人を変え、未来を変えたのだ。こんな人がいたのだ、この人がいたからこそ今があるのだと感じ入る。今日の私たちの生活は、多くの「こんな人」たちの上に成り立っているのだ。
勝子の物語は雨で始まり、虹で終わる。これは実に象徴的だ。
雨のあとに、虹が出る――文章として見れば詩であり、さまざまな比喩やメッセージを思わせる文学表現である。だが同時に現象として見れば、大気中の水分が太陽光を分散させて起きる大気光学という科学である。
私たちは科学の中に文学を見る。文学の中に科学を見る。そのふたつが結びつくことで、人の世が決して単体として存在するものではなく、あらゆるものが分かち難く結びついた化学反応によって営まれているという事実が浮かび上がってくる。
それこそが伊与原新がデビュー以来追求しつづけている文学の形なのだ。
(おおや・ひろこ 書評家)