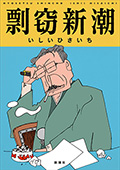書評
2025年8月号掲載
伊与原 新『翠雨の人』刊行記念特集
「面倒くさい人間愛」の人
対象書籍名:『翠雨の人』
対象著者:伊与原 新
対象書籍ISBN:978-4-10-336215-9

もう十年近く前のことだ。ある日、大学院時代の恩師、浜野洋三先生から一通のメールが届いた。用件とは別に近況を知らせてくださる文章の中で、私は「猿橋勝子」と出会った。先生が選考委員をつとめている「猿橋賞」の選考会があったとのことで、こんなことが書かれていたのである。
〈猿橋さんは、1950~1960年代初頭の米ソの原水爆実験が引き起こした海洋の放射能汚染を追究した地球化学者です。道場破りさながらに単身渡米し、汚染を過小評価するアメリカ側の権威と海水の分析勝負をして見事勝利したという、すごい人なんですよ〉
私は驚いた。「猿橋賞」が女性科学者を対象とする国内でもっとも権威ある学術賞の一つだということは知っていたが、賞の設立者である猿橋勝子についてはほとんど何の知識もなかったからだ。私はすぐに、物理学者で猿橋賞受賞者でもある米沢富美子による評伝、『猿橋勝子という生き方』を買い求め、夢中でページをめくった。
一晩で読み終えると、深い感動に包まれるとともに、こんな思いも溢れてきた。「猿橋賞」の知名度に比して、勝子自身の成し遂げたことが、なぜこうも世間に知られていないのか。波瀾万丈で痛快な彼女の生き様から私が受けた励ましは、もっと多くの人と共有するべきだ。それが小説という形でもできるのであれば、いつかこの手で書きたい――。
数年後、その願いが本誌「波」での連載という形で実現したのが、『翠雨の人』である。執筆を始めるにあたって担当編集者とまず訪れたのは、東京は小平霊園にある、勝子が眠る猿橋家の墓だ。線香をあげて手を合わせ、「精一杯書かせていただきます」と心の中で伝えてはみたものの、勝子が何か応えてくれた気はしなかった。
実在の人物の生涯を小説にするのは初めてである。しかも、歴史に明るいとはとてもいえない身で大正生まれの女性の一生を書こうというのだから、一筋縄ではいかない。図書館をあちこち回って乏しい資料を集め、当時を知る方々から話をうかがいながら、勝子の人生というパズルを、見つかったピースで一つずつ埋めていくような作業が続いた。
勝子は帝国女子理学専門学校を卒業後、大戦中に中央気象台に就職し、戦後は気象庁気象研究所で研究に従事した。数多くの論文から研究の中身は把握できるのだが、戦中から戦後すぐにかけての研究現場の具体的な様子についてはほとんど情報がなく、描出に苦労した。当時の実験室の写真が一枚残されていたとしても、そこに写っている装置や器具が何なのか、専門家でもはっきりとはわからないということも多かった。
しかし、もっとも難しかったのは、そこではない。研究者としてではなく、生身の人間としての猿橋勝子に迫れているという実感が、なかなか得られなかったということだ。それでも、勝子自身が書き残したエッセイやインタビュー記事を読み込み、実際に彼女と交流のあった方々の話をうかがって、私なりの勝子像を作り上げた。
それをひと言に凝縮した人物評を、この小説の架空の登場人物、勝子の後輩となる奈良岡という研究者に作中で何度か代弁させた。「面倒くさい人」である。
勝子の「面倒くささ」の基底にあるのは、生来の生真面目さ、融通のきかなさ、頑固さであろう。ただ、本人もおそらくそのことに自覚的でありながら、そんな自分でしかいられないという不器用さ、表裏のない真っすぐさに、私は勝子ならではのチャームを見出していた。
そして、二年間におよぶ連載期間中、私なりに彼女と向き合い、語り合う中で、勝子像も少しずつ変容していった。勝子の「面倒くささ」が、俄然ポジティブな光を放ち始めたのだ。私同様、後輩として付き合ううちに勝子への見方を変えていったであろう奈良岡に、私はまた自分の思いを代弁させた。単身渡米した勝子に奈良岡が送った手紙の一節である。
〈あなたの面倒くささは、世界に通用します。面倒くささはすなわち、誠実さであり、粘り強さであり、正しさです〉
勝子のそんな性質はいつも、社会に、仲間に、女性たちに向けられていた。彼女の核をなすのはすなわち、面倒くさいほどの「人間愛」ではなかったかと思うのだ。
本ができたら、それを持って再び勝子の墓前に報告にいくつもりである。ヨーロッパや中東で紛争が続き、核の脅威が再び高まっていることとともに、今この小説を世に問う意義を伝えたい。今度は何かひと言ぐらいは意見を言ってくれる気もするのだが、どうだろうか。もちろんその前に、「『面倒くさい人』って、何よ」と𠮟られる覚悟はできている。
(いよはら・しん 作家)